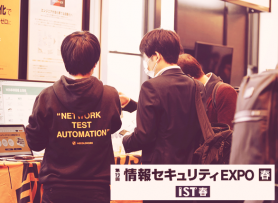2025/07/08
【事業部紹介:UPS(前編)】挑戦の原点──TradeOCR誕生秘話と課題への挑戦

こんにちは。エーピーコミュニケーションズでキャリア採用を担当している小宮山です。
わたしたち、エーピーコミュニケーションズ(以下、APC)は、ネットワークやクラウド領域に強みを持ち、ITインフラ分野を中心に技術支援を行っている会社です。
そんな「インフラの会社」である当社内に、実は貿易業界向けのプロダクト開発を手がける部門があることをご存知でしょうか。
その名も、UPS(Universal Product-development Section/呼称:アップス)。
今回は、当部門責任者の井上にインタビューを行い、自社プロダクト「TradeOCR」誕生の背景や込められた想いについて聞いてみました。
▼貿易書類に特化したAI-OCR「TradeOCR」
https://www.ap-com.co.jp/trade-ocr/
インタビューを通じて見えてきたのは、これまでの試行錯誤の数々や水産業から貿易業界へと視野を広げながら、現場に根ざした課題に向き合ってきたUPSの挑戦の数々でした。
この記事【前編】では、「TradeOCR」誕生の秘話をお届けします。
それではいってみましょう!
井上 竜太郎 (イノウエ リュウタロウ)
Universal Product-development Section 室長
2018年に新卒で入社。大学院では情報工学とプロジェクトマネジメントを学び、他の大学と共同でプロダクト開発。インフラエンジニアとしてクラウド案件に関わったのち、新規社内サービス開発チームに参画。2022年にUniversal Product-development Sectionを立ち上げ今に至る。
▼インタビュー記事
「やりたいこと」軸を持ち、それができる環境をフル活用する~インフラエンジニアを経て、念願のソフトウェアエンジニアへ~
TradeOCR誕生の背景
小宮山
まず、TradeOCRについて教えてください。
井上
はい、「TradeOCR」は、通関業務の現場で“当たり前”となっている手作業を変えるために開発した、貿易書類専用のAI-OCR(光学文字認識)プロダクトです。
インボイスやパッキングリストといった非定型な貿易書類(PDF)から、通関手続きに必要な情報を自動で読み取り、整理・出力できるクラウドサービスとなっています。
従来の貿易業界向けOCRでは対応が難しかった“フォーマットの違い”にも柔軟に対応でき、読み取り範囲の事前設定なしでも必要な情報を自動抽出できるのが、TradeOCRの最大の特長です。
小宮山
TradeOCRはどういう経緯で生まれたのでしょうか?
井上
「TradeOCR」は貿易業界向けのプロダクトですが、はじめから通関事業者向けのプロダクトを作ろうとは考えていませんでした。
スタートは水産業に関わる人の課題を解決したいという思いがきっかけです。
私は、高知県の海辺の町出身で、祖父は漁師でした。
時代の流れとともに水産業がどんどん衰退していくのを間近で見てきたんです。
その光景に、「なんとかしたい」と漠然とした課題意識を持つようになりました。
社会人になってからもその思いは消えず、個人的に地元や周辺地域の水産業者や企業へヒアリングを始めました。
ヒアリングを通して、漁師の人手不足(高齢化の影響、後継者不足)、国内の魚価停滞など様々な課題が見えてきました。しかし、水産業の課題に直接アプローチすることは非常に難しいと感じ、一旦方針転換することを決めました。
視野を広げるため、さらにヒアリングを行っていると、海外での魚需要が高まっていることもあり、漁業関係者が販路を拡大する中で、海外への輸出や飼料の輸入など、貿易機会が増えていることを知り、貿易業界に着目しました。
そこから紆余曲折があって、今の通関事業者向けのプロダクトにたどり着いています。

貿易業界で直面した新たな社会課題
小宮山
水産業から貿易業界にピボットされたわけですが、具体的にはどんな課題が見えてきたのでしょうか?
井上
はい、通関業務を担う企業さんへのヒアリングを通じて、通関業務(輸出入の際に税関へ必要な手続きをする業務)に大きな課題があることが分かりました。
業界全体の人手不足に加え、近年の輸出入件数の増加に伴い、書類の確認・入力業務が増加し、現場の通関士(輸出入される貨物を通関業者に代わって税関に申告する専門家)の業務負担が非常に大きくなっています。それにもかかわらず、システムによる業務効率化は進んでいません。
書類をデータ化するOCRサービスは、貿易業界でも展開されていたものの、現場では浸透していませんでした。理由を尋ねてみると、「荷主ごとに書類のフォーマットが違うから、忙しい時に読み取り位置を設定なんてしていられない。それなら使わない方が効率的だから結局手作業で入力することになる」という声を多く聞きました。
課題を生み出す構造に挑む決意
小宮山
それだけ大きな課題を抱えているにもかかわらず、現場では手作業が続いていたんですね…。
井上
はい、そうなんです。結局、通関業務は、属人化と手作業が多いと伺っています。
日々の業務だけでも負荷がものすごく高いのに、少しでもミスをしたら、税関から指導を受けたり……。それくらい責任の大きな仕事を、現場の人たちは本当にギリギリの状態で回している。でも、こういう仕組み自体がもう、ミスを誘発するリスクを生み出す構造になってしまっていると思うんです。
みんな頑張っている。だけど、輸出入の取引件数は年々増えており、どうしても限界がきてしまう。そこを変えなければ、現場も、業界も、持続できない。だからこそ私たちは、「現場の負担を減らして、ミスやリスクを根本から減らしていけるような仕組みを作ろう」そう強く思うようになりました。そして、試行錯誤の末にたどり着いたのが、「TradeOCR」だったんです。
(後編へ続く)
今回のインタビューでは、現場ヒアリングを重ねる中で見えてきた、貿易業界が抱える大きな社会課題、 そしてUPSの「挑戦の原点」をお届けしました。
次回【後編】では、 TradeOCRに込められた開発秘話と、UPSの今、そしてこれから目指す未来について、さらに深掘りしていきます。ぜひ続きもご一読ください!
井上が所属する部門(UPS)では、エンジニアを募集中です
▼募集要項(カジュアル面談もこちらからお申込みいただけます)
・リード開発エンジニア
* * * *
エーピーコミュニケーションズでは中途も新卒も積極的に採用中です。
お気軽にご連絡ください!
▼エンジニアによる技術情報発信
tech blog APC
Qiita