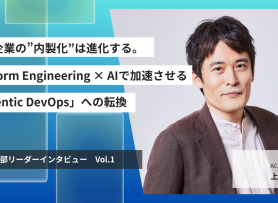2025/07/11
エンジニアの成長と働きがいを最大化。APCの「エンジニアリングメンター室」の取り組みを聞く
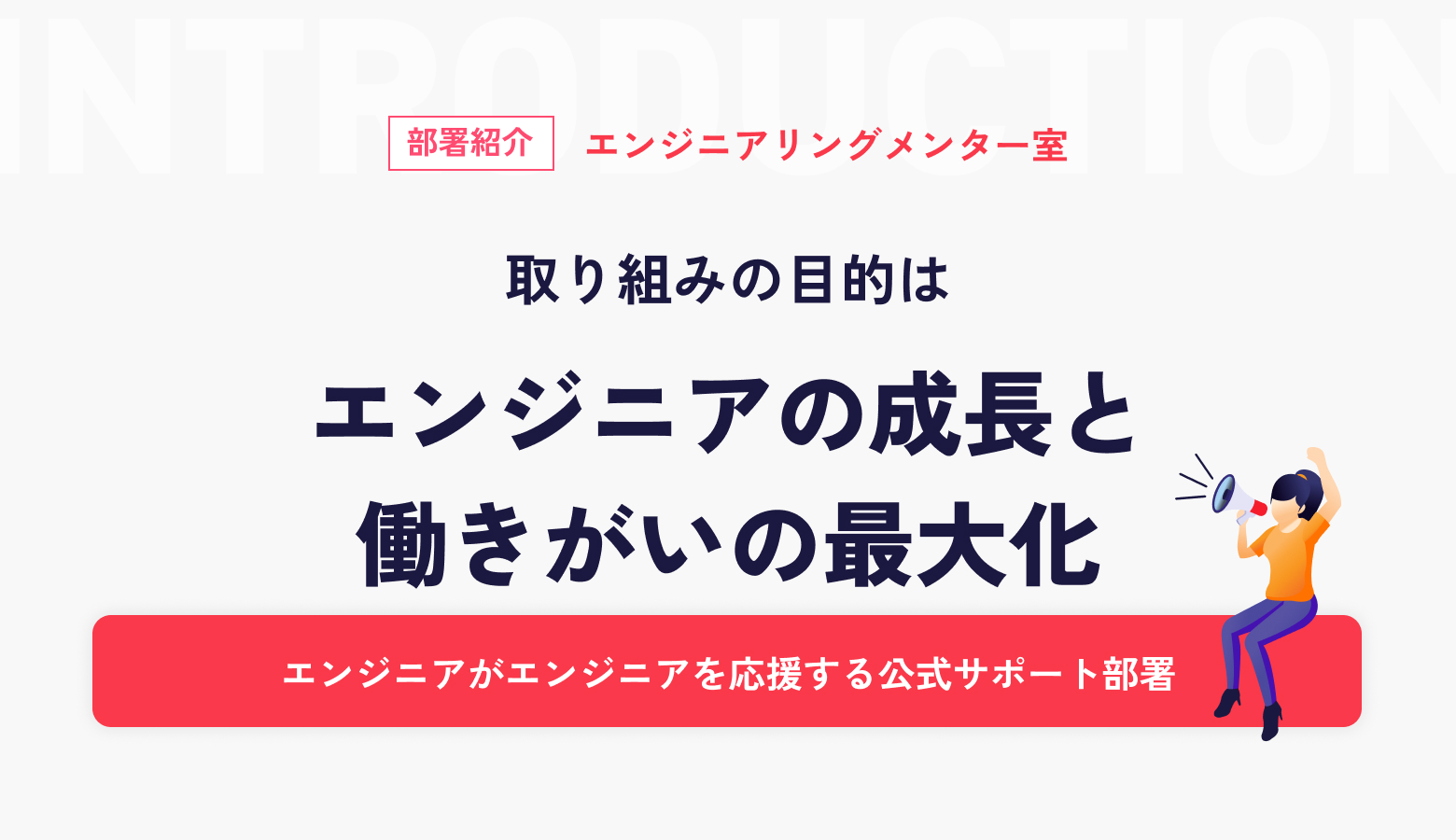
エーピーコミュニケーションズ(以下、APC)には、エンジニアが主体的に学び、成長できる文化を醸成するユニークな部署があります。それが「エンジニアリングメンター室」(以下、EM室)。特徴的なのは、EM室のメンバーは全員エンジニアという点です。エンジニアがエンジニアを応援することを目指しています。
今回はEM室が推進する「新しい学習体験を通じた働きがいの向上」について、具体的な取り組みや工夫したこと、EM室が目指す未来について、発足者である横地さん、メンバーの山路さん、海老澤さんに話を聞きました。

エンジニアがエンジニアを応援する公式サポート部署
——まず最初にEM室の設立経緯や役割について、教えてください。
横地:EM室は、APCのエンジニア一人ひとりが「楽しいエンジニアライフ」を送れるように応援する、エンジニアによる公式サポート部署です。エンジニアの成長を支援する相談役として、主にメンタリングを行っています。
——EM室では「エンジニアがエンジニアを応援する」ことを大切にしているそうですが、それはどんな関係性や距離感を意識しているのでしょうか?
横地:「利害関係がないこと」を重視しています。上司と部下、あるいは先輩と後輩といった上下の関係性の中では、本人の意図とは無関係に、プレッシャーや忖度のような“好ましくない利害関係”が少なからず生じてしまう可能性があります。EM室では、そうした関係性から切り離されたフラットな環境を提供したいと考えています。
例えるなら、親ではなく、親戚のおじさんやお兄さんのような距離感で相談できるイメージでしょうか。少し離れた関係性だから言えることがあると思いますし、上下のラインとは別の相談先があること自体に価値があると考えています。
「新しい学習体験」を新たな切り口に
——今、注力しているという「新しい学習体験を通じた働きがいの向上」の取り組みについて聞かせてください。
横地:今回は、APCの中期経営計画(2025〜2027年)に掲げられた「働きがいの向上」という大きなテーマに着目しました。EM室としては、このテーマに対して「新しい学習体験」という切り口で貢献することを目指します。
——「新しい学習体験」と「働きがいの向上」の関係性について、どのように捉えるとよいでしょうか?
横地: 「働きがいの向上」には、給料を上げる、魅力的な仕事をつくりだすなど様々なアプローチがありますが、私たちEM室ではそのような直接的な手段は担えません。
では何ができるのか?と考えたとき、一番に想起したのが「学習体験の提供」です。個人的な意見ではありますが、やっぱりエンジニアは本質的に学習を好むと考えていて、その機会を生み出すことが、働きがい向上につながるのではないかと考えたのです。
APCには既に、約100もの講座が用意された社内大学「APアカデミー」や資格取得のための費用補助といった学習支援制度がありますが、私たちはそれらとは別の切り口を探しました。エンジニアが「なぜこの会社にいるのか?」という、根本の存在意義を見出すような「新しい学習体験」が、 「働きがいの向上」に効果的なのではないかと考えました。今回、部署横断の施策として「現場報告会」「Slack活用アカデミー」の2つを開催しました。
——「部署横断の施策」なんですね。
横地:そうですね、部署内に閉じていては面白くないと考えています。APCにはたくさんの部署があり、多様な技術を扱い、いろいろな業種のお客様を支援しています。一つの部門に閉じず、横断的にシャッフルしたら、もっと面白い化学反応が起きるのではないかというのが私の想いです。いろいろあるからこそ面白いですし、得られるものや見える世界は倍以上に広がっていくと思うんです。
「現場報告会」~実践知を共有し、学びへ
——山路さんが担当した「現場報告会」について、具体的な内容と工夫点について教えてください。
山路: 今回の現場報告会では「経験を、伝えよう」というテーマを掲げ、各現場の案件で得た知識や学びにフォーカスすることで、新たな学習体験の場を作ることを目指しました。
従来の現場報告会は、プロジェクトや業務の紹介がメインで、参加者にとってはどのチームがどんな技術を使ってどんな仕事をしているのかを「知る場」でした。しかし、今回は「経験から得られた知見を学ぶ場」として設計しています。現場で得た知識や知恵を共有することで、そこまでの経緯や工夫、失敗からの学びが得られると考えました。
実施にあたり工夫した点は、EM室で発表準備の全工程をサポートしたことです。例えば、発表ネタの切り口、内容の整理、アウトライン検討、資料レビュー、改善案の提案なども行いました。プロジェクトの紹介で終わらず、そこから「何を学んだか」という点が中心になるよう、EM室でディレクションを行っています。
——具体的にはどのように開催されたのでしょうか?
山路:9つのプロジェクトが登壇してくれたので、当日は、オンライン会議室を3つ並行で立ち上げ、参加者は好きな発表を自由に行き来できるカンファレンス形式を取りました。セッションの中では、エンジニアが発表を行なった後、それに対して参加者から質疑応答を受けたり、EM室のメンバーが登壇者とディスカッションしたりすることで、内容をさらに掘り下げていきました。今回は発表者が気づかなかった「暗黙知」を掘り出すことも目指しており、質疑応答やディスカッションの時間を多く確保した点も工夫の一つです。
——開催して、どのような手応えを感じていますか?
山路:発表後の質疑応答が活発であり、時間内に拾いきれないほど多くの質問を頂けたことから、参加者の興味を惹くことができたという手ごたえを感じました。参加者の方からは、「自分のことに置き換えて共感しやすかった」「各チームがどのようにしてプロジェクトを進めているのか、どのように課題をクリアしているのかを聞くことができる貴重な機会だった」「現場で得られる体験は、独学や資格の勉強では得られないもの」といった声が寄せられました。
今回の現場報告会を通じて、技術書や資格取得では得られない「生きた知識・学び」を持ち帰ってもらい、業務改善や個人スキル向上につなげる機会になったのではないかと感じています。また、登壇者にとっても、「経験の言語化」によって、自身の活動の価値や存在意義を再認識できる機会になったのではないかと思います。
「Slack活用アカデミー」〜日常を変えるコミュニケーション基盤
——次に、海老澤さんが担当した「Slack活用アカデミー」ついて聞かせてください。
海老澤: 社内のコミュニケーションに対する考え方や、技術的な質問の仕方を学ぶ講座を開催しました。
背景として、APCがリモートワーク中心の働き方を継続していく方針であること、そして実際にリモートワーク中心で働く社員が多いことがあります。そうした方々に対して、何かしらのアプローチができないかと考えました。
特に、新卒社員などIT業務の知識があまりない人や、中途入社でもリモートワークに不慣れな人にとっては、リモート環境に入った途端、孤独感を覚えたり、分からないことがあっても質問しづらい状況に陥りがちです。そうした環境では、社内の多くのエンジニアが持つ知見が組織全体で共有されず、眠ってしまう危険性があります。そうした機会損失を防ぐためにも、知見の活性化を促したいと思い今回の講義を企画しました。
——具体的な内容についても教えて下さい。
海老澤:この講座は、Slackとは何か?を学ぶ「知識」、使う上での心構えを学ぶ「マインド」、活用するための方法論を学ぶ「テクニック」の3部構成になっています。コーポレート部門や新卒社員も対象なので、IT業務の知識があまりない方や、Slackを使ったことがない方でも理解できるように、Slackの特徴や用語、使い方から解説しています。
この講座の内容を作るにあたって工夫した点は、活用するための方法論を学ぶ「テクニック」において、質問の仕方にフォーカスしたことです。とりわけチャットに慣れていないとSlack上での質問は難しく、必要な情報が抜け落ちがちです。結果的に有益な回答が得られないという体験を防ぐため、質問のコツとして「フォーマット」を伝えられればと思い、内容に含めました。
——参加者からの手応えや反響はいかがでしたか。
海老澤:参加者からは、「基礎的なところがよく分かって助かった」「Slackでの質問方法について気になっていたので、知ることができて良かった」「フルリモート環境において、質問の仕方や積極的なリアクションが重要であるなど、学びのある有意義な時間だった」といった声をもらいました。
現段階では、Slackの活用法をテーマにしていますが、将来的には「リモートワーク全般」といった、より大きなテーマを扱っていきたいです。リモートワークにおける業務の進め方、仕事との向き合い方、さらには自宅の執務環境の整備など、リモートワークで重要になることは多岐にわたるので、そうした内容も拡充していければと考えています。
部署を超えて、コミュニケーションが自然に生まれる文化を
——今後、EM室としてどのような展開を目指していますか。
横地:EM室の取り組みを通じて、部署の枠を超えて自然にコミュニケーションが生まれる、そんなエンジニア文化の醸成を理想としています。
少し前の話になりますが、経験の浅いエンジニアと交わした何気ない会話をする中で、私が「技術は自分の興味で学んでもいいんだよ」と伝えたところ、その方が「そうか、楽しんでやってもいいんですね」と非常に驚いていたんです。
逆にその反応に私は驚いてしまい、「自分で自分の可能性を閉じてしまっているのではないか」「それぞれの部署が独立した会社のようになって部署間の交流が減ってしまうと、その中で価値観が固定化されて、多様な視点を失ってしまうのではないか」という懸念を感じました。そこから改めて「部署の枠を超えたコミュニケーション」は重要だと考えるようになりました。
APCの業態の特性上、現場で扱う技術や顧客の業種は多種多様です。この多様な技術やプロジェクトがあること自体が、APCで働く面白さであり、組織としての大きな強みだと思っています。私たちは、APCのエンジニアがこの面白さや強みを自身の「働きがい」に繋げるきっかけを作る部署として、組織に価値を提供していきたいです。
横地 晃(よこち あきら) iTOC事業部 BzD部 ACT 兼 エンジニアリングメンター室
テクニカルエバンジェリスト。2012年、APCに入社。ネットワーク設計構築を経て、近年はAnsibleを活用したネットワーク自動化支援に注力。技術ブログ執筆、技術書執筆、社内外イベント登壇など、幅広い活動を通じて技術コミュニティに貢献。noteでもEM室の取り組み情報を発信中。
山路 風太(やまじ ふうた) クラウド事業部 IaC技術推進部 Cloud Native Group 兼 エンジニアリングメンター室
シニアプロフェッショナル職。2017年、非IT系の学部から新卒でAPCに入社。わずか2年でプロフェッショナル職エンジニアに就任。EM室の主要メンバーとしても活躍
海老澤 直輝(えびさわ なおき)iTOC事業部 BzD部 ACT 兼 エンジニアリングメンター室
プロフェッショナル職。2021年、新卒でAPCに入社。ITOC事業部でAnsibleを用いたITインフラ自動化に携わる。2022年1月にはプロフェッショナル職に就任し、技術ブログや登壇を通じてAnsibleの技術進化に貢献。過去記事はこちら
* * * *
エーピーコミュニケーションズでは中途も新卒も積極的に採用中です。
お気軽にご連絡ください!
▼エンジニアによる技術情報発信
tech blog APC
Qiita