2025/10/22
インフラエンジニアのホントのところ #24|実務経験が少なくても転職できる、インフラエンジニアの共通点
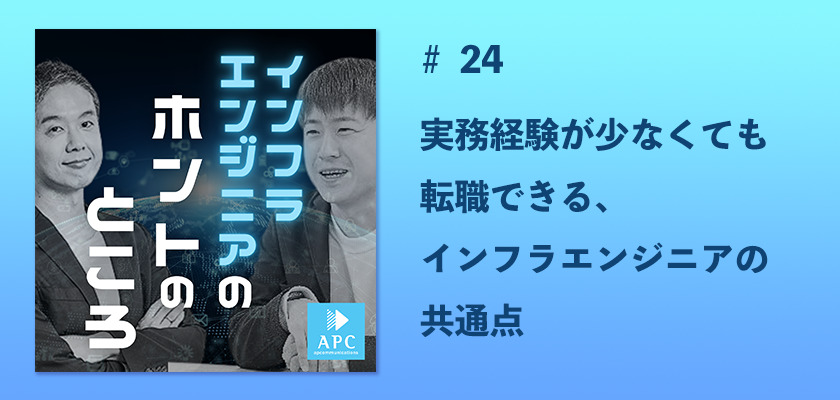
ITインフラって、「なんだか難しそう」「地味で大変そう」と思われがち。
でも実は、社会を支える根幹にある、とてもやりがいのある仕事なんです。
そんなリアルをお届けするPodcast 「インフラエンジニアのホントのところ」。
MCにはベンチャー女優の寺田有希さんを迎え、当社の副社長 永江耕治と採用責任者 小山清和が、現場・経営・採用の視点から語ります。
今回のテーマは「実務経験が少なくても転職できる、インフラエンジニアの共通点」。
実務経験が少なくてもインフラエンジニアとして転職できる人には、「共通点」があります!
共通点を解き明かすとともに、企業が実は重視しているポイントなど、元エンジニアの現役経営者と採用責任者が徹底解剖します。
<目次>
1.オープニング
2.実務経験が少なくても転職できる人の共通点とは?(現役経営者の視点)
3. 実務経験が少なくても転職できる人の共通点とは?(採用責任者の視点)
4. 意外と評価される「継続力」という才能
5. 企業側が面接で見ているポイント
6. クロージング
1.オープニング
寺田:インフラエンジニアの本当のところ。言葉は有名でも、何かと知らないことが多いインフラエンジニアの世界。この番組は、キャリアや将来性、魅力など、ついつい隠れがちな「本当のところ」、インフラエンジニアキャリアの真実を、業界のプロであるエーピーコミュニケーションズの永江さん、小山さんと共に徹底解剖していくポッドキャストです。今回も始まりました、「インフラエンジニアの本当のところ」。
永江:エーピーコミュニケーションズの永江です。インフラエンジニア業界に23年以上携わっており、現在はエーピーコミュニケーションズで取締役副社長をしています。どうぞよろしくお願いいたします。
小山:エーピーコミュニケーションズの小山です。私は10年以上のIT業界での採用経験と、7回にわたる転職でキャリアを形成してきた人事です。エーピーコミュニケーションズでは採用責任者をしています。よろしくお願いします。
寺田:そしてMCを務めます、ベンチャー女優の寺田有希です。
私がお2人にすごくお聞きしたくて、知りたかったことなんですけど、パソコン周辺機器で何かおすすめのガジェットってありますか?
永江:私はずっとApple製品を使っているので、自宅でもMagic KeyboardとMagic Mouseをずっと使っていますね。Apple純正のマウスとキーボードです。それがやっぱり使いやすいな、と思っています。
寺田:何が違うんですか?
永江:なんだろう…もうそれが当たり前だと思っているので、他との比較が分からなくなっているんですが、直感的に色々できるところとか、操作感ですかね。
寺田:使ったことなかったです。超Macユーザーですけど。小山さんは何かありますか?
小山:僕もAppleユーザーなのに、全然Magic系は使っていないんですけど、パソコンのガジェットだと、僕はディスプレイにモバイルディスプレイを使っているんですよ。固定ではなくて、持ち運びができるディスプレイです。場所を取らないというのもあるんですけど、例えばどこか出先に行った時でもデュアルディスプレイで仕事ができたりします。
普通のディスプレイは持ち運びができませんが、これはサイズが少し小さいという欠点はあるものの、結構どこでも使えて場所を取らない。たためば終わりですし、バッグに入れてもそんなに重くないんです。
値段も意外とそんなに高くなくて、2万円台とかで買えるので、僕はもうずっとモバイルディスプレイで仕事をしています。割と自分には合っているな、という感じがしますね。
寺田:デュアルディスプレイって、やっぱり便利ですか?私、ノートパソコン1台でずっと戦っているんですけど。
永江:そうなんですね。僕はもうずっとデュアルディスプレイでやっているので、もう戻れないですね。
小山:慣れるまではちょっと時間が必要でしたけど、慣れちゃったら逆に仕事がしづらくなるくらい、差はありますね。
寺田:いや、ちょっとこの後探します。
小山:調べながら資料を作れたりするので、やっぱり作業スピードは早いですよね。
寺田:いつもブラウザを切り替えていました。
小山:そう、それが一番大変だったりするので。
寺田:ありがとうございます。皆さんもぜひ参考にしてみてください。
2. 実務経験が少なくても転職できる人の共通点とは?(現役経営者の視点)
寺田:本日のテーマは「実務経験が少なくても転職できるインフラエンジニアの共通点」です。転職において、やはり実務経験は大きな武器となるもの。しかし、少ない経験値でも転職を成功させている人もいます。その人たちに共通していることは何なのでしょうか?
面接で伝えるべきことや必要なスキルまで、元エンジニアで現役経営者の永江さんと、採用責任者の小山さんと共に徹底解剖してまいります。
まず前提としてなんですが、永江さん、実務経験が少なくても転職は可能ですか?
永江:結論から言いますと、転職は可能です。業界全体で考えると人は足りていない状況があるので、私たちの会社というよりは、業界全体で考えると、経験が少なくても転職されている方は一定数いらっしゃると思います。
寺田:その状況は今後も続いていきそうですか?
永江:そうですね。もちろん実務経験があった方が転職しやすいんですけれども、絶対になければできない、というわけではないと思います。
寺田:じゃあ、実務経験が少ないことが極端に不利になったり、「絶対できない」という理由にはならないですね。
永江:ただ、やはり実務経験がある人の方が企業は採用したいと思うので、ここはプラスアルファの何かを、ちゃんと用意していかないと難しくはなると思います。
寺田:気になるのは、実務経験が少なくても採用されるのがどんな人なのか、どんなケースなのか、なんですけど、これはいかがですか?
永江:当社の例でお話ししますと、実務経験が少ない方の採用というのは実はそこまで多くはなく、それなりのハードルの高さはあります。
ただ、そんな中でも「実務経験が少ない」方が入社されることもあります。そのケースでどういう方かと言いますと、一番分かりやすいのは、「学習能力の高さがある」と判断できた時ですね。
「勉強したいです」とか「こういうのをやっていきたいです」という意欲として「この期間でこれだけの勉強を実際にした」ということが分かると、一つのプラスになるかなと思います。
寺田:勉強する「長さ」とかでいいんですか?「これだけ勉強しました」とか。意欲って、あまり測れないものじゃないですか。
永江:「長さ」で判断するということはないと思っています。
一例を挙げますと、とあるITベンダーの資格があって、多くの人は大体1年ぐらいかけて勉強して合格する難易度だとします。それに対して、「勉強期間1ヶ月で集中的にやって取得した」という場合、同じ資格を持っていても、印象は全然違いますよね。「早くキャッチアップできる人だな」ということが分かります。
また、どこかの期間で、複数の、しかも難易度がそれなりのものを連続で取得されている方というのは、それだけ早く色々なものを吸収していける、という一つの客観的な証拠になるかなと思います。
寺田:確かに、学習効率の高さ、集中力の高さとか、色々アピールになりますね。
永江:そうですね。どれくらいの期間で、とか、どういう状況の中で、とか。
寺田:「子育てもしながらやりました」とか、そういうことですよね。少ない時間でやりました、とか。
永江:「すごく忙しい業務の中でやりました」というのと、「仕事を辞めて、時間がまるまる空いていました」というのとでは、また評価が違ってきますよね。
3. 実務経験が少なくても転職できる人の共通点とは?(採用責任者の視点)
寺田:前提として実務経験が少なくても転職ができるというのが分かったところで、もっと詳しく共通点を解き明かしていきたいと思います。ではここからは、採用責任者である小山さんと一緒に、色々深掘りしていきます。
寺田:まず、経験が少なくても内定を勝ち取った人の共通点ってありますか?
小山:共通して持たれているのは「目的志向」。ちゃんと目的を考えた上で面接に臨んでいる、という点です。例えば、「自分は経験は浅いけれども、この会社で内定を得るためには、何を事前にキャッチアップすべきか、何を伝えるべきか」を、内定から逆算して考えられる人がいるんです。
エンジニアの仕事って、「こういう状態にしたい」というゴールがあって逆算して物事を考えていくんですよね。なので、そういう素養は実は結構大事です。
もちろん直感もあってもいいと思うんですが、経験がある人の直感は、経験に裏打ちされた「勘」なので割と当たるんです。ところが、経験がない人の「勘」って、何も分かっていない状態でなので、ほぼうまくいかないんですよ。
寺田:「あてずっぽう」ってことですね。
小山:そうです。だから、会社を調べたり、自己アピールを研究したりすることが大事なのではなく、自分の「スイートスポット」を探すような行為だと思うんです。「どこを伝えれば、この会社の人事の人は私を採用したいと思ってくれるだろうか?」「どこの情報を見れば、会社をよく調べているな、と思ってもらえるんだろうか?」ということが、結構できている。これ、新卒でもできている方はいます。
寺田:ええ、新卒ですか?!
小山:そうなんです。目的から考えているんです。なんだかんだ言っても、ゴールとしては内定とか、面接を通過することがポイントなので。
もちろん、それをやっても落ちることはあります。相性みたいなものもあるので。ただ、経験が浅くても受かる人は、そこら辺のポイントをちゃんと押さえて、準備してきています。これはエンジニアの思考性としても、実は大事なことなんです。
寺田:エンジニアの仕事と共通しますね。
寺田:他の分野でも絶対に必要な力ですし、エンジニアとなると、もっと大事ってことですね。
小山:そうです。例えば、面接が60分間あったとして、その時間の使い方も分かっている人は考えています。
寺田:あ、そこまで考えるんですね。
小山:時折、自己紹介に20分かける方がいらっしゃいます。
でも、自己紹介って、実は面接でそんなに重要ではないんです。「自分を採用した方がいい」と思ってもらうための、たった60分のうち、1/3を自分の紹介だけに使ってしまう行為が、後でどれぐらい影響を及ぼすか考えられていない。
本人としてはアピールしているつもりでも、企業側が「20分で自己紹介してください」と求めているならいいですが、自己アピールが良かったから採用する、ということってたぶん、ほとんどないと思うんです。経験が浅い人であればなおさら、この人が入社して活躍してくれるだろうか、というところを見るために、自己紹介だけだと不十分ですよね。
というように、「目的志向」の方は面接官の視点を持って考えているんですよね。
4. 意外と評価される「継続力」という才能
寺田:大事なポイントが分かった上で、実務経験よりも評価される「意外なポイント」ってありますか?
小山:継続してきているものが何かあるかどうか、というのは結構大事ですね。
寺田:例えば学生時代にこれをやってました、とかでもいいんですか?
小山:まず、なぜ継続が大事かというと、実務力はあくまで「現時点」での力なんです。現時点では実務力がある、という判断にはなりますが、その後伸びるかどうかは分かりません。入ってから伸びない人もいます。
僕らとしては、入った時点での能力のままだと困るんです。当然、本人も困ると思います。やはり成長していかなきゃいけない。
じゃあ、その「伸びしろ」をどこで見るか。センスや学習意欲も大事でしょうけど、何かを続けてきた実績も大事なんです。
ただ、気をつけてほしいのは、何でもいいかというと、そうでもない。中途採用の人が「学生時代に…」と言っても、ちょっと微妙ですよね。
寺田:確かに。
小山:それは過去すぎるので。現時点でやっていることで、もっと言えば、年単位で続いているといいですね。
加えて、何かしらのやったことがわかるアウトプットがある。例えばランニングだったら、「マラソン大会に出ています」でもいいんですよ。
寺田:あ、それは業務に直結していなくてもいいんですか?例えば小山さんだったら「毎日走っています」とか、そのために「トレーニングしています」とか、「毎日英語の勉強を続けています」とか。仕事に直結しないと思うんですけど。
小山:いと思います。続けることって、本当に立派な才能なんですよ。
たとえば、1万人が「これをやろう!」と盛り上がっても、実際に行動に移すのは100人ほど。そして、その中で継続できるのは、たった1人か2人くらいなんです。つまり、“続ける”というだけで、それだけ希少で貴重な才能なんです。
ただし、1〜2週間程度ではまだ「継続」とは言えません。人は何かを習慣化するまでに、少なくとも3ヶ月はかかると言われています。だから、続けるなら最低でも3ヶ月以上は取り組む必要がある。
頻度も重要です。週1回で3ヶ月なのか、毎日なのか。もし年単位で続けている人がいたら、それは本当にすごいことだと思います。
寺田:確かに。気合が入っている最初の1週間だけやって、何ヶ月か経って「あ、やってない」みたいなことって、よくありますよね。
小山:そうなんです。ただ、自分で意志を持って継続していることも大事ですね。言われてやっている、やらされている継続は、あんまり価値がないかもしれない。それは自分が主体になっていないからですね。
資格も自分でやろうと思ったのか、会社が取れと言ってるからなのか、全然違うと思うんですよ。
寺田:じゃあ、「実務経験の代わりに身につけるべきスキルは何でしょう?」というのもお聞きしたかったんですけど、やはりそれって「継続力」が一番大きいですか?
小山:「継続できること」が一番ではないんですけど、世の中で活躍している方、成功している方って、やっぱり続けているんですよ。失敗もたくさんするんですけど、そこで歩みを止めない。そういう人がやっぱり成功したり、活躍したりしていると思います。
5. 企業側が面接で見ているポイント
寺田:せっかく採用責任者の方がいらっしゃるので、ここで企業側の本音をお聞きしたいなと思っています。まずこれ、聞きたいんですけど、実務経験以外で企業が特に見ているポイントって何ですか?
小山:私個人としてよく気にしているポイントとしては、見られ方を意識しているかどうかは見ていますね。
例えば、面接に来た時に、加点する以前に、自ら自分の価値を下げてしまうような振る舞いをしている方っているんですよ。
寺田:それは謙遜とは違いますか?
小山:相手からどう見られているか、という視点を持っているかです。
例えば、清潔感のある服装で面接に臨むのと、そうでない格好で行くのとでは、相手の印象は大きく変わりますよね。第一印象は非常に重要ですし、自分からマイナスな印象を与える必要はありません。
面接官は「この人が入社してお客様の前に出たとき、リスクにならないだろうか」といった視点で見ています。
もちろん、「身だしなみにあまり関心がない」というのも個人の自由ですし、「おしゃれをしなさい」と言っているわけではありません。
ただし、会社に入れば「会社の一員」として見られることになります。場合によっては、自分の振る舞いが周囲の評価にも影響を及ぼす可能性がある。だからこそ、そうした影響を想像できる力、いわば“想像力”を持っているかどうかを見ています。
寺田:「看板を背負ってもらえるかな」ってことですね。
小山:そうなんです。会社の顔でもありますからね。そこは意識した方がいいと思います。
寺田:最後に面接の時、どういうことをアピールされるとグッときますか?実務経験よりも「あ、この人いいな」って思いますか?
小山:なぜ、その会社に入りたいと思っているかを、ちゃんと言語化できる人ですね。「頑張ります」ではなく、「こういう理由があって、御社がいいんです」と具体的に言えること。
そのためには、会社のことをきちんと調べて理解し、自分が持っている強みと結びつけて話せる必要があります。
自分のスキルすべてがその会社で活かせるわけではありません。でも、調べた上で「このスキルなら役に立てるかもしれない」と仮説を立て、それをどう活かせるかを考えて伝えられると、とても良いアピールになります。
そうすると、面接官にも「うちが求めているのはまさにこういう人だ」と伝わるんです。
「会社のことをちゃんと理解してくれているし、その上で自分をどう重ねられるか考えているんだな」と感じてもらえる。実際に、学生でもここまでできている人はいますよ。
寺田:すごいですね、最近の方は本当に。
小山:よく考えて、自分の言葉で言っていますからね。これは、多分AIじゃ作れないんですよ。その人の感情が入っているので。
寺田:そっか。リサーチとかにAIを活用しているかもしれませんけど、最終的にはちゃんとご自身で考えて言葉にする、というのが大事ってことですよね。
小山:そうなんです。人って感情で生きていますから。そういうところが、相手の共感を呼ぶんだと思うんですよね。
6. クロージング
寺田:ちょっとこの採用の視点というのは話が尽きなくて、まだまだお聞きしたいところなんですけれども、永江さん、いかがでしたか?
永江:はい。このテーマだともう色々なことがお話しできるので、まだまだお話ししたいことがあります。例えば、コミュニケーションの部分。「チームと一緒に協調して働けそうか」とか、そういう要素もいっぱいあるんですけど…。
ちょっと時間の都合で、語り尽くせなかったという感じですね。
寺田:採用で大事なポイントなので、もう1回ぐらいお話を広げてもいいかもしれないですね。小山さんどうでしょう?
小山:聞いている皆さんには、「今の話だけがすべて」というふうには捉えないでいただいて、あくまで一つの観点として捉えていただけると、と思います。
寺田:ぜひ皆さん、こちらも参考にしていただけたらと思います。
この番組はSpotify、Apple Podcast、Amazon Musicで配信中です。
ポッドキャストへのフォローとレビューもぜひお願いいたします。
番組へのご質問やリクエストは、専用フォームか、各種SNSから受け付けております。気になることがありましたら、ぜひお寄せください。


