2025/11/12
インフラエンジニアのホントのところ #27|クライアントワークはやめとけって本当? 今こそ見直されるべき真実
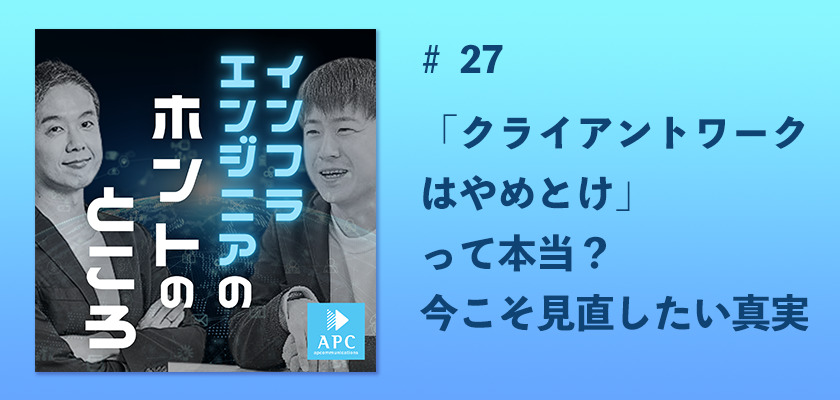
ITインフラって、「なんだか難しそう」「地味で大変そう」と思われがち。
でも実は、社会を支える根幹にある、とてもやりがいのある仕事なんです。
そんなリアルをお届けするPodcast 「インフラエンジニアのホントのところ」。
MCにはベンチャー女優の寺田有希さんを迎え、当社の副社長 永江耕治と採用責任者 小山清和が、現場・経営・採用の視点から語ります。
今回のテーマは「クライアントワークはやめとけって本当? 今こそ見直されるべき真実」。
「成長できない」「キャリアがブレる」など、マイナスなイメージが先行しがちな「クライアントワーク」。
でも実際は、スキルもキャリアも大きく広げられるチャンスが眠っています!
今回は現場の最前線で活躍するお二人をゲストにお迎えし、そのリアルを語っていただきます!
<ゲスト>
– 石井 克尚(いしいかつひさ):株式会社グッドパッチ 執行役員
– 高橋 裕行 (たかはしひろゆき):株式会社エーピーコミュニケーションズ iTOC事業部 EDT部 部長
<目次>
1.オープニング
2. クライアントワークとは?
3. モチベーションの保ち方
4. 顧客との対等な関係性の築き方
5. キャリアがブレる不安への対処法
6. これからの時代にクライアントワークをやる理由
7. クロージング
1.オープニング
寺田:インフラエンジニアのホントのところ。言葉は有名でも、何かと知らないことが多いインフラエンジニアの世界。この番組は、キャリアや将来性、魅力など、ついつい隠れがちな「ホントのところ」、インフラエンジニアキャリアの真実を、業界のプロであるエーピーコミュニケーションズの永江さん、小山さんと共に徹底解剖していくポッドキャストです。今回も始まりました、「インフラエンジニアのホントのところ」。
小山:エーピーコミュニケーションズの小山です。私は10年以上のIT業界での採用経験と、7回にわたる転職でキャリアを形成してきた人事です。エーピーコミュニケーションズでは採用責任者をしています。よろしくお願いします。
寺田:そしてMCを務めます、ベンチャー女優の寺田有希です。さてさて小山さん、今回は2人で始めています。
小山:そうですね。永江さんの最初の紹介がないのは、若干新鮮です。「あ、そうだった。今日は1人だった」という感じでした。
寺田:なぜ2人なのかと言いますと、またまたゲスト回です。
小山:そうなんですよ。前回も非常にいい話が聞けましたけど、今回もまた楽しみです。
寺田:なんで楽しみなんですか?
小山:今日はですね、まさかなのですが、前職が絡むコラボレーション配信です。こんな機会はなかなかないので、ちょっとドキドキしています。
寺田:でも素敵ですね、こういうつながりがあるって。
小山:そうですね。受けていただいたこと自体も非常にありがたいんですけれども、僕も前職は非常にいい経験をさせてもらえた会社だと思っています。何か一緒にできたらいいなと思っていたところもあったので、この日が来て嬉しく思いますね。
2. クライアントワークとは?
寺田:本日のテーマは、「クライアントワークはやめとけって本当? 今こそ見直されるべき真実」です。「ただの下請けだ」「キャリアがブレる」「会社とのつながりが薄い」など、マイナスイメージが多いクライアントワーク。しかし、実は自分を成長させることができるフィールドもあります。本日はゲストをお迎えし、クライアントワークの魅力と、今やるべき理由に迫ってまいります。
それではゲストをご紹介いたしましょう。株式会社グッドパッチ 執行役員 石井さん、そして株式会社エーピーコミュニケーションズ iTOC事業部 EDT部 部長 高橋さんです。お2人、よろしくお願いします。
石井:よろしくお願いします。
高橋:お願いします。
寺田:早速なんですけれども、これまでどんなことをされてきたか、今どんなことをされているかなど、簡単に自己紹介をお願いしてもいいでしょうか?まず石井さんからお願いします。
石井:皆様、初めまして。株式会社グッドパッチで執行役員をしております、石井と申します。
私は、キャリアはプログラマーとしてスタートし、クライアントワークや事業会社のインハウスエンジニアを経験した後、現職のグッドパッチには、最初はエンジニアとして入社しました。そこからデザイナーにジョブチェンジするなど、様々な経験を経て、その後マネジメントとしてのキャリアを重ね、現在は執行役員としてクライアントワーク部門の管掌役員をしております。
本日はよろしくお願いいたします。
寺田:それでは高橋さん、お願いします。
高橋:エーピーコミュニケーションズの高橋と申します。
私は大学卒業後プログラマーを3年ほど経験し、その後、司法書士の資格を取ろうと2年ほど勉強していたんですが、結果は出ず、インフラエンジニアを目指すことになり、2006年にエーピーコミュニケーションズに入社しました。
入社後は、クライアントワークの形態でプロバイダーのネットワークに関する保守・運用・構築といった、インフラの基盤となるような業務を一通り担当させていただきました。それ以降は管理職として、様々な現場を間接的に統括・管掌するような立場を経験してきました。
2019年からは現場を離れ、プロフィット部門の事業推進という部署で「何でも屋」のような業務を担当した後に、今年から再びプロフィット部門の方に戻ってきた、という形です。来年で入社から20年目の節目を迎えます。
よろしくお願いします。
寺田:さてさて、今回のテーマが「クライアントワークはやめとけって本当?」ということなんですけど、まずはこの「そもそもクライアントワークとは何だ?」というところから深掘りしていきたいなと思います。
小山さん、このクライアントワークってそもそも何ですか?
小山:基本的には依頼をする人、クライアントがいるわけですね。そのクライアントの「こういうものを制作したい」という意向があって、それに基づいてサービスや物を作ったりして提供する、というのが一般的にクライアントワークの内容になります。
それがデザインなのか、開発なのか、インフラなのか…色々種類はあります。なので、いろいろな分野で使われている言葉だと思います。その反対が、自主制作とか自社プロダクトになります。
寺田:他社から依頼を頂いて仕事をする、という感じですかね。
小山:本当にざっくり言うとそんな感じですが、細かいところまで言語化して話す人はあまりいないかもしれません。『言われたことをやる』程度に思っている人もいるかもしれませんね。
寺田:でも実際はそれだけじゃない、と。
小山:奥が深いんですよ。今日はそれをぜひお2人にお話ししていただきたいなと思っています。
寺田:まず、この「クライアントワーク」を検索したりすると、やはりマイナスイメージが結構出てきちゃいます。これに対して、まずグッドパッチ石井さん、いかがですか?
石井:確かにクライアントワーク、別の言い方をすれば「受託」という事業形態は、「ずっと残業してそう」「何日も徹夜してそう」「クライアントにただ言われたものを作る」といったイメージを持たれていることは、確かに多いと思います。
そういった組織もあるのかもしれませんが、マイナスイメージが拡大解釈されているような部分もあるのではないか、と思います。
逆に「クライアントワークが楽しい」という情報がWeb上であまり多く出てこない、というのもあると思います。なかなか良いイメージを持ちにくいのかもしれません。結構楽しいですよ。
寺田:高橋さんどうでしょう?
高橋:そうですね。まず、クライアントワークをやる目的は、シンプルにクライアントさんの課題を解決することです。
例えば、社内リソースが足りないとか、自社では実現できないデザインやシステム開発とか、そういった課題に対して、外部の専門家として解決していくのが本質だと思っています。
そういった意味では、クライアントワークの代表的な形は「コンサルタント」じゃないかと思います。高い専門性を持って、お客さんの課題を一緒に解決していく。それはデザインもシステム開発もコンサルも、構造としては同じだと捉えています。
ちょっと考えてみてほしいんですが、「コンサルタント」という仕事もクライアントワークですが、それに悪いイメージを持っている人はあまり多くないと思うんですよね。
寺田:そうかもしれないです。
高橋:おそらく、クライアントワークに対するマイナスのイメージって、仕事の形態そのものではなく、例えば多重下請け構造、下請けいじめみたいな、そういう構造的な問題から来ているんじゃないか、と捉えています。
寺田:出来上がってしまった仕組みの、マイナスの部分が拡大解釈されてしまっているイメージですかね。
高橋:そうですね。もちろん、その構造自体は是正されるべき課題だとは思いますが、だからといって、クライアントワークそのものが悪いというわけではない、と思っています。
寺田:ちょっとそこを切り分けて考えられるように、ヒントをいただけたらと思います。
3. クライアントワークは「成長できない」は本当か?
寺田:「成長につながらない」というイメージについて、石井さんはいかがでしょう?指示に従うだけでは成長につながらない、という声をよく聞きますが、実際どうなんですか?
石井:「指示に従ってこれ作ってください」「はい、作りました」「どうでしょう?」「こうじゃない?」「じゃあ、こうでどうでしょう?」といったラリーの中では、なかなか成長を実感することも難しいとは思います。
先ほど高橋さんもおっしゃっていましたが、我々の仕事は、クライアントさんと課題を解決したり、事業の成長を後押し・伴走したりすることだと考えています。クライアントワークは期間が限られている中で、どれだけの成果を出せるか、ご支援できるか、という仕事です。
プロジェクトによってドメインも組織も異なりますし、場合によっては自社側のチームメンバーも毎回変わったりします。この「自分の周辺にある変数」がすごく大きく変わるのがクライアントワークであり、その中でどう成長を作っていくか。
ここで、個人としての「再現性」が大事なところだと思っています。
どんな環境であっても、しっかりと成果に向かって行動し、その行動の中に自分自身が成功するための再現性をどう蓄積していけるか。クライアントワークで多様なプロジェクトを経験することによって、どんな環境でも成果を創出できる、再現性を持った人材へと成長できます。それがクライアントワークだからこそ実現できる「成長の仕方」なのだと考えています。
寺田:個の力、あるいは個人のスタイルといったものが、他の働き方よりも確立しやすい、ということでしょうか。
石井:そうですね。1つはクライアントという、毎回異なる組織、異なる会社、異なる文化の方と仕事をするということです。クライアントと伴走しながら、事業成長を考えて実行していくというのは、インハウスと呼ばれる事業会社でのお仕事とは大きな違いですね。
寺田:クライアントワークをキャリアの場として活用していくには、「自分のスタイルを確立していく」ということが大事なんですかね。
石井:はい。個人の成長としては、一つそれがあると思っています。
あとは、僕自身もすごく実感したんですが、似たようなドメインのプロダクトであっても、組織によって「どうやって成長させるか」というアクションプランは全然違ったりするんです。その会社が得意としている事業の成長パターンがあります。
組織として事業をどう成長させるのか、その色々なパターンを、自分自身が身を投じて体験できる。将来的に自分で事業を持ちたいと考えている方は、そういったところに強く意識を向けながらクライアントワークをやるのもいいと思います。
その経験によって、「あのプロジェクトではこうやって事業を成長させていたな」という引き出しができていきます。そういった手段を獲得しながら、自分の次のキャリアを作っていく。そういう考え方もいいんじゃないでしょうか。
寺田:自社だけだと、自社のサービス、自社のやり方だけですもんね。他社のサービス、他社のやり方に触れられるって貴重ですよね。
石井:そうですね。クライアントさんの事業責任者の方や、ボードメンバーの方とお話しする機会も割と多いので、新しい考え方に触れられるのは、すごく刺激的だと思います。
寺田:しかも、そこに自分がアダプトしていくと思うと、きっとたくさん調べなきゃいけないし、勉強しなきゃいけない。それも成長に繋がりますよね。
石井:そうですね。今まで自分が全く触れてこなかった業界のことであったり、社会課題に触れることも数多くありますし、自分自身の興味の範囲も広がっていくので、その中で新しいキャリアを見つけていくこともあるんじゃないかと思います。
3. モチベーションの保ち方
寺田:お2人に、クライアントワークの中でご自身がモチベーション高く仕事を続けていくために、どうしたらいいかをお聞きしたいです。
まず、インフラエンジニアとして高橋さんはいかがですか?
高橋:そうですね、実は私自身は、モチベーション高く働くのはあんまり得意じゃないんですよ。
寺田:そうなんですね。
高橋:どちらかというと「モチベーションに頼らず働く」ということを、若い頃は意識していました。
あまり気乗りしない仕事を頼まれることも、当然あります。正直、それに対してモチベーション高く取り組むって難しいと思うんです。でも、仕事は仕事としてやらなければいけない。
なので、私自身は気持ちよりも「やるべきこと」を優先してやるように意識してきました。モチベーションに左右されてしまうと、やるべきことができなくなってしまうので。意識していたのは、依頼されたものが100%だとすると、105%でお返しする、といったことですかね。
寺田:モチベーションは関係なく、成果を上げに行くためにどう努力できるか。そこにフォーカスされる、というイメージですかね。
高橋:ちょっとだけでも相手の期待を超えたいな、と。
期日を1日早めるとか、資料を少し見やすく工夫するとか、それぐらいのことでも「お、早いね」「見やすかったよ」みたいに言われると嬉しいじゃないですか。そういう小さな「期待を超える」という点に、こだわりを持ってやっていましたね。
寺田:それがまた成長に繋がりそうですね。グッドパッチ石井さんいかがでしょう?
石井:難しいのは、クライアントワークという括りで考えていくと、モチベーションとかエンゲージメントというのは結構難しい、と思うところはあります。
個人のエンゲージメントに影響するのは、事業形態というよりは「組織のあり方」ではないかと思っています。その組織が中長期的にどんなことを実現したいのか、世の中にどんなインパクトを与えたいのか。そこの部分で、しっかりと人と組織が繋がっていくのが大事だと思います。
組織の「Will(やりたいこと)」と、個人の「Will」を、どうやって重ね合わせることができるかが、大事なポイントだと思っています。組織の戦略や戦術は、その大上段にあるビジョンからブレイクダウンされて実行されます。点としての施策ではなく、大元である会社のビジョンやミッションに共感が持てていると、戦略や戦術も自分ごと化しながら仕事ができる。それが「働きがい」にもつながってくるんじゃないでしょうか。
あるべき状態を実現するための「クライアントワーク」という考え方で仕事に向き合えると、たまにモチベーションが上がったりするのかなと。
寺田:たまにでいいんですね。
石井:たまにでいいんじゃないでしょうか。僕もモチベーションに依存するのは良くないと思っています。例えるなら、マリオカートで1周ごとにアイテムが取れますけど、あそこでキノコが出てきた、みたいな。
モチベーションが高い状態っていうのは「ラッキー状態」くらいに思っているので、それよりは、所属の欲求などを満たせる環境に自分自身を置く、というところの方が大事ではないかと思います。
寺田:そこの環境選びとかは、すごく重要そうですね。
4. 顧客との対等な関係性の築き方
寺田:ここからは、「顧客との対等な関係」という点について、お2人と考えていきたいなと思います。
エーピーコミュニケーションズの高橋さん、顧客との対等な関係は築けるものなんですか?
高橋:そうですね。これは正直に言うと、言うほど簡単ではなく、むしろ難しいのではないかと思っています。少なくとも、個人の力だけでできるものではないと思います。
寺田:でも、これは実現していかなければいけないですよね。
高橋:はい。お客様は組織として動いているので、個人のレベルでは限界があります。だからこそ、会社とか組織の力を取り込んでいくのが大事だと考えています。
例えば、現場の担当者は担当者同士、我々のような管理職は相手方の管理職、役員は相手方の役員、というように、それぞれのレイヤーごとに関係を築いていくのが大事だと思います。
現場は日々、課題解決を通じて信頼を積み上げ、管理職は月の定例などで組織としての課題をお客様と一緒に考える。役員同士は会社の方向性を理解し、互いのビジネスがうまくいくような関係を作る。
対等な関係って、単に遠慮なく話すということではなく、お互いの役割や視点を理解し合える関係なのだと思います。各レイヤーそれぞれで信頼を積み上げていく、そこを目指すのが大事だと考えています。
寺田:レイヤーを合わせていくんですね。ちなみに、エーピーコミュニケーションズで実際にやっている取り組みはありますか?
高橋:そうですね。先ほどお伝えしたように、現場同士はもちろんやりますが、管理職とか役員の方と、いかにコミュニケーションが取れるかというところで、定例化をするとか。あとは、たまには会食の席で、ミーティングではできないようなお話をして関係性を深めていく。そういう場を役員にお願いしてセットしてもらったりしています。
寺田:やっぱりお食事って大事なんですね。
高橋:はい、大事だと思います。一気にそこで距離が縮むこともあったりするので。
寺田:石井さんの会社ではいかがですか?対等な関係を築くために工夫されていることは。
石井:私たちで言いますと、まず最初にヒアリングをしてご提案する際、その中の一部として「デザインパートナーとして一緒にお仕事をさせていただきたい」とか、「我々は伴走型のプロジェクトの進め方を得意としておりますので、そのような進め方をさせていただきたい」というお願いをしています。
なので、クライアントさん側にも、一定のコミットをお願いしています。クライアントワークと言うと、「週に1回定例を持って提案し、OKかNGかの判断をしてもらう」というイメージがあるかもしれませんが、我々はクライアントさんとのコミュニケーションは、Slackなどで日常的に行っており、インハウスのデザイナーやエンジニアと似たような形を取っています。
意思決定のタイミングを定例の場だけにせず、「今こんなデザインを考えてみたんですけど」「こんなシステム構成でAPIはこうしようと思うんですけど」といった話を、日常的にしながら進めていきます。
場合によっては、クライアントさんが立てている計画や戦略を覆すようなご提案をさせていただくこともあります。「この方が事業のロードマップを早く達成できるのでは?」「KPIはこういったものを据えるべきでは?」と提案をさせてもらう。そのような形で、我々は「パートナー」としてお仕事をさせてください、というところを強く意識しています。
寺田:もうスタートから「対等ですよ」という定義付けと、伴走の仕方も全て工夫されているんですね。
石井:そうですね。プロジェクトの区切りのいいタイミングなどで、弊社の代表がクライアントさんにインタビューを実施しています。良い評価をいただける場合は、大体「予想以上のコミットだった」と言っていただけます。
社外の人間ではあるんですけども、中にいる人のように事業のことを考え、意見を出し、実行していく。それが我々の伴走の形かな、と考えています。
寺田:高橋さんと石井さん、それぞれアプローチは違いますが、対等な関係の築き方も色々形があるんですね。
5. キャリアがブレる不安への対処法
寺田:「キャリアがぶれそう」「帰属意識が薄くなる」というのは、現場で働く方々が感じることだと思います。そういう声にはどう向き合っていきますか?
インフラエンジニアとして高橋さんはどうですか?
高橋:確かに、キャリアについて不安を持つ人は多いと思います。自分が望まない案件に配属されることを、いわゆる「配属ガチャ」みたいに感じてしまうケースなどです。特に、経験や実力が十分でないうちは、希望通りの現場に行けないこともある。これは、どんな会社でも起こり得ることだと思います。
じゃあ、どうすればキャリアを主体的に生きられるようになるか。大事なのは2つあって、1つ目は、自分の考えを言語化して伝えることです。弊社では、年単位でキャリアを振り返る「キャリアシート」という仕組みがあります。自分がどんな方向に進みたいか、何ができてどんな価値を出せるのかを整理して、上司と共有する機会です。他にも、日々の1on1でもキャリアの話はできます。それらの機会を通じて、自分の考えを上司に伝える。そうすると、何をしていきたいのかが理解され、実際のアサインにも反映されやすくなります。
2つ目は、今の仕事の中で結果を出していくことです。色々思うところはあっても、今のところで結果を出す。その積み重ねによって、希望も通りやすくなりますし、キャリアの選択肢を広げていけるんだと思います。
寺田:105%を目指していかなきゃですね。
高橋:そうですね。
寺田:お話を聞いていて思うのが、「こなす」だけだと、キャリアアップにもつながりにくいし、不満も溜まってしまうのでしょうか。プラスアルファの努力ができるかどうかが、クライアントワークをキャリアにつなげていけるポイントなんですかね。
高橋:そうですね。それに加えて、「主体的に考える」というところですかね。仕事を「やらされている」と思うのか、「いい仕事をしている」と思うのか。キャリアも「こういうことがやりたい」と主体的に考えて、それを伝えることが大事なのだと思います。
寺田:では、石井さんどうでしょう。
石井:グッドパッチはデザイン会社でもあるので、デザイナーにとっての「ホーム」になれるかどうかが、結構重要だと思っています。デザイナーにとって働きやすい、刺激がある、挑戦できる、そういった環境を構築できるかどうかが大事です。それが実現できると、グッドパッチに所属していることの意味を、一人ひとりのメンバーが作っていけるんじゃないかと思います。
逆に、帰属意識が薄れて転職になってしまったのなら、それはもう僕の責任だ、と考えています。デザイナーもエンジニアも転職市場は活発ですし、フリーランスや独立など多くの選択肢が常に開かれています。だから、会社として、組織として、そのキャリアの選択肢に勝ち続けなければいけない、選ばれ続けなければいけない。執行役員として仕事をする中で、ここは一つ重要な役割ではあるのかなと思っています。
所属しているデザイナーやエンジニアが、「これからどうしようかな」と考えた時に、「もう少しだけグッドパッチで仕事してみようかな」と思ってもらえるかどうか。そこを作っていくのが大事だと思います。
あとは、私もメンバーには「自律・自学・自責」というところを伝えています。自律してください、自分で学んでください、自分の責任として行動してください、と。この大前提は、とても大事だと思っています。
我々が、挑戦する機会を作ることはできますが、数は限られています。全員に同じだけの機会を提供するのは不可能ですから、そのスタンスを持ち、しっかりと成果を出してきた人に対して、次の挑戦機会を提供したい。そういう機会を提供された人を見て、「自分もしっかりと機会を得たい」と前向きに取り組んでもらえるような制度設計や、マネジメントからのコミュニケーションも重要になってくると思います。
6. これからの時代にクライアントワークをやる理由
寺田:最後に、これからの時代、クライアントワークをやるべき理由って何なんだろうと思ったので、お2人に聞きたいと思います。高橋さん、まずいかがでしょう。
高橋:技術はインフラエンジニアとしてすごく大事ですが、単に技術力で課題を解決するだけでは不十分だと思っています。
お客様の中に入って仕事をしていると、技術的な課題の裏に、根深い「アダプティブな問題」があることに気づきます。例えば、人間関係がうまくいっていない、組織間の対立がある、意思決定のプロセスが曖昧、とか。そういう人や組織の関係性に起因する問題です。
これは、外から見ているだけでは絶対に分からない、一緒に働いてみて初めて見えてくる部分です。これは技術的な課題よりも扱いが難しい領域で、だからこそクライアントワークの価値があると思っています。
外部の人間だからこそ、社内の利害や力関係に囚われず、客観的にその部分に介入できるからです。そこを一緒に整理したり、対話を促したりすることで、結果的に、お客様のビジネス全体がうまく回るようになる。そこをお客様と一緒に目指していく必要があると考えています。
技術的な問題解決は前提ですが、それだけではお客様のビジネスの成果が出ないケースも多い。その時にどうアプローチしていくか。それが、これからの時代のクライアントワークの本当の価値ではないかと、おぼろげながら思っています。
難しい領域ではありますが、そこに挑戦していきたいというのが私が掲げているテーマのひとつです。
寺田:この番組でも度々、技術プラス、コミュニケーション力などが必要だというお話が出てきますが、まさにそういう力を磨いていけそうですね。
高橋:そうですね。これも主体的に考えて、「技術もそうだけど、裏側にそういう問題がありそうだな」と気づけると、「じゃあどうしよう」という発想になると思うので。そこからお客様の様子を見ると、少しずつ分かってくるのだと思います。
寺田:石井さんいかがでしょう。
石井:「やるべき理由」という考え方だと、結構難しいですね。基本的には、個人や組織の「あるべき姿」「ありたい姿」から逆算して考えた時に「クライアントワークという手段が最適だよね」と自分自身が思えるかどうか、なのではないかと思います。
僕個人の話をさせていただくと、僕は「世の中に、いいサービスやプロダクトを増やしたい」「自分のスマホのホーム画面を、自分の好きなアプリでいっぱいにしたい」とか、そんなことを思っています。それを実現しようとした時、自分の手足や頭だけで作ろうとすると、限界があります。
僕は、グッドパッチという「器」を使って、そういったことを実現できたらいいな、と考えています。その手段として、クライアントワークを長く続けている、というのがあります。これは、グッドパッチが掲げる「デザインの力を証明する」というミッションとも重なりが作れています。
「クライアントワークは事業会社ではない」と言う方もいるかもしれませんが、僕としては「デザイン」という事業をやっている会社、と自社を捉えています。このデザインという事業・産業を、どうやったら日本の中で成長させていけるか。クライアントワークというものとは少し違った見方で、「デザインという事業なんだ」「エンジニアリングなんだ」というところで見ると、また仕事の見え方や関わり方も変わって、面白くなったりすると思います。
寺田:お2人のお話を聞いて、ご自身がどう関わるか、ということがやはり重要ですね。今までとは違う見方ができた気がします。皆様もぜひ、色々参考にしていただけたらと思います。それでは石井さん、高橋さん、今日は本当にありがとうございました。
石井:ありがとうございました。
高橋:ありがとうございました。
7. クロージング
寺田:さて、小山さんいかがでしたか。
小山:前職(グッドパッチ)と現職(エーピーコミュニケーションズ)の話を聞いていて、共通しているところもあるな、と。特に前職は「デザインの力を証明する」ということで、私自身はデザイナーではなかったですが、採用という部分でどうやったらそれを証明できるかを考えながらやっていたな、と思い出していました。
今の会社では、「エンジニアとお客様を笑顔にする」というビジョンのために、採用部門の長としてどう立ち振る舞うべきかを考えてやっています。どんな仕事でも、クライアントワークに限らず、セルフモチベーションというか、意味付けをしてやることは、すごく大事だなと。
世の中に出ている話だけで思い込むのではなく、もうちょっと深掘りをして、自分自身が「これはいいな」と思うところがあるか、ちゃんと確認してから判断するのって、すごく必要だなと思いました。改めて初心に返ったような感じもします。
寺田:でもやはり、ご自身がどう考えていくか、どう向き合っていくか、その根本ってめちゃくちゃ大事ですね。
小山:多分、それが伝わるんでしょうね。そういう思いを持ってるから、クライアント側の人も「応えよう」とか「この人だったら」って思ってもらえる部分があるんじゃないかな。やる気がない人には、時間を使わないと思うので。ネガティブな雰囲気って、意外と伝わりますよね。
寺田:ネガティブの方がインフルエンスしやすいですからね。
小山:そう。「ブラックだ」といった話題は大好物です。
寺田:じゃあ、皆さんもポジティブに行きましょう!
この番組はSpotify、Apple Podcast、Amazon Musicで配信中です。
ポッドキャストへのフォローとレビューもぜひお願いいたします。
番組へのご質問やリクエストは、専用フォームか、各種SNSから受け付けております。気になることがありましたら、ぜひお寄せください。


