2025/05/22
インフラエンジニアのホントのところ #2|インフラトレンドの変遷を辿る
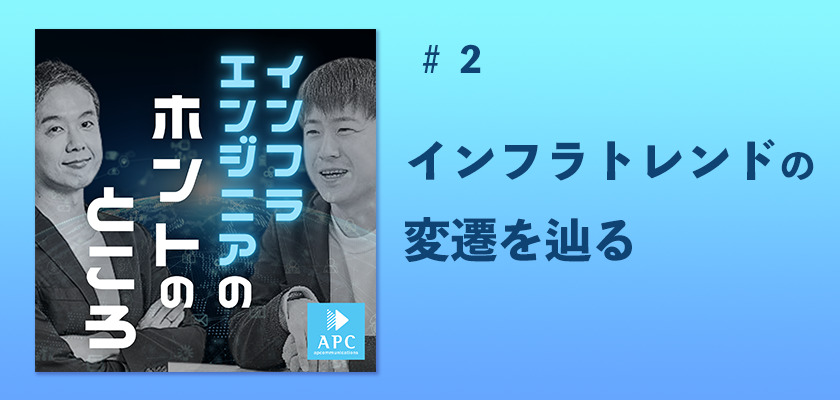
ITインフラって、「なんだか難しそう」「地味で大変そう」と思われがち。
でも実は、社会を支える根幹にある、とてもやりがいのある仕事なんです。
そんなリアルをお届けするPodcast 「インフラエンジニアのホントのところ」。
MCにはベンチャー女優の寺田有希さんを迎え、当社の副社長 永江耕治と採用責任者 小山清和が、現場・経営・採用の視点から語ります。
今回のテーマは「インフラトレンドの変遷を辿る」。
変化が激しいIT業界。合わせてITインフラは、これまでどのように変化してきたのでしょうか。
「トレンドの変遷」を二人が徹底解剖しながら、今はどんな時代なの? これからどうなっていくの? と、現在と未来についても考えます。
<目次>
1.オープニング
2.創業はインターネット黎明期。エーピーコミュニケーションズが見てきた景色
3.物理サーバーからクラウドへ。技術革新と社会の変化がもたらした「新しい働き方」
4.クラウドの次へ。AI時代を見据えたインフラエンジニアの新たな価値
5.クロージング
1. オープニング
寺田:さて、第2回目が始まりました。
永江:MCを務めます、エーピーコミュニケーションズ 取締役副社長の永江です。どうぞよろしくお願いいたします。
小山:エーピーコミュニケーションズ 採用部門 責任者の小山です。よろしくお願いいたします。
寺田:そして、同じくMCを務めます、ベンチャー女優の寺田有希です。この番組は、インフラエンジニアのキャリアのプロであるエーピーコミュニケーションズの永江さん、小山さんと共に、インフラエンジニアのキャリアについて徹底解剖する番組です。
早くも2回目ですが、お二人、いかがですか?
永江:そうですね。正直、まだ慣れていない感じはありますが、だんだん慣れていくかなと思います。
寺田:これからですよね。小山さんは前回、全く緊張していないとおっしゃっていましたが、今回はどうですか?
小山:緊張していません(笑)。話したい気持ちが先走っている感じで、変なことを言わないように気をつけたいです。この番組が何回続くかわかりませんが、どんどん続けていきたいという気持ちでいっぱいです。
寺田:素晴らしいですね。ぜひ続けていきましょう。では早速、本日もお二人に色々とお話を伺いたいと思います。
本日のテーマは「インフラトレンドの変遷」です。
2. 創業はインターネット黎明期。エーピーコミュニケーションズが見てきた景色
寺田:前回は、「そもそもITインフラとは何か」、そして「それを支えるインフラエンジニアとはどんな仕事なのか」について語っていただきました。現代社会におけるITインフラの重要性は理解できましたが、一口にITインフラといっても様々な変化を遂げてきたのではないかと思います。
そこで本日は、「ITインフラがどのように変化してきたのか」について、お話を伺っていきます。
その前に少し整理をすると、まずエーピーコミュニケーションズはITインフラをメイン事業とされているプロフェッショナル集団、という認識でよろしいでしょうか。
永江:その通りです。当社はまさにITインフラをメインに手掛けるプロフェッショナル集団です。ネットワークやサーバーといったITインフラ分野の設計・構築から運用までを、お客様にサービスとして提供しています。私たちは、IT基盤を支える「縁の下の力持ち」のような役割を担う会社です。
寺田:前回「影のヒーロー」だと感じましたが、まさにそういったご職業ですよね。
永江:そうですね。「下支えする」という言葉がイメージとして近いかもしれません。
寺田:創業は何年ですか?
永江:1995年の11月です。ですので、創業から30年近くになります。ちょうどインターネットの商用利用が始まり、Windows 95が発売されて話題になった時期です。まさにインターネット黎明期に会社がスタートしました。
寺田:Windows 95、懐かしいですね。
永江:そうですよね。だいぶ昔の話になりました。
寺田:永江さんご自身も使っていましたか?
永江:当時はMacも使っていましたが、Windows 95が登場してからは、そちらも使っていましたね。
寺田:小山さんはいかがですか?
小山:いえ、私は使っていませんでした。自宅にあったのはPC-98で、Windowsは入っていませんでしたね。ワープロソフトもWordではなく「一太郎」でした。
寺田:懐かしいですね。
小山:実家が田舎だったので、大学に入って初めて本格的に触れました。
寺田:当時はパソコンを持っている家庭も少なかったですよね。エーピーコミュニケーションズは、その時代からITインフラ事業をされていたのですか?
永江:設立当初はネットワークの保守から事業をスタートしました。その後、企業のネットワークやサーバーの設計・構築へと事業を拡大し、ITインフラの中でも領域を広げてきました。近年では、仮想化技術やクラウドの登場に伴い、そちらの分野へもシフトしています。
現在はクラウド事業はもちろん、ネットワークの自動化や、AIに関連するデータ基盤の設計・構築なども手掛けていますが、常にITインフラが事業の軸であり、私たちの根幹となっています。
3. 物理サーバーからクラウドへ。技術革新と社会の変化がもたらした「新しい働き方」
寺田:まさに「ITインフラの変遷」のすべてを見てこられてきたのですね。
永江:ええ、当社も時代の変化と共に事業内容を変化させてきました。
寺田:永江さんご自身はずっとITインフラ業界にいらっしゃるのですか?
永江:キャリアの最初はウェブサイト制作の会社でしたので、厳密にはITインフラではなく、インターネット関連の仕事でした。ITインフラの世界に入ったのは、エーピーコミュニケーションズに入社した23年前です。それから約四半世紀、ずっとこの業界にいます。
寺田:様々な変遷を見てこられたのですね。
永江:本当に、ずっと見てきたという感じです。
小山:私がインフラ分野に限定して関わるようになったのは、この会社に入社してからのことで、約1年半になります。
ただ、エンジニアの採用には2011年10月頃から関わっています。当時はまだオンプレが主流で、クラウドは登場していましたが、導入している企業は少なかったですね。開発エンジニアと並行してインフラエンジニアの採用も手掛ける中で、彼らの仕事内容を具体的に知るようになりました。
その後、一時期インフラエンジニアの採用から離れましたが、この十数年でインフラエンジニアを取り巻く環境が大きく変わってきたことは客観的に見て感じていました。そして、この会社に入社して、その変化の速さをより一層実感しています。
寺田:なるほど。ITインフラ業界に長く携わってこられた永江さんと、外側からその変化を感じてこられた小山さん、ぜひお二人の視点から色々なお話を聞かせてください。
では、インフラトレンドの変遷について、どこから語っていきましょうか。
永江:技術の変遷における最も大きな変化は、物理サーバーからの移行です。
寺田:昔はどのような感じだったのですか?
永江:今でこそクラウドという概念が当たり前ですが、以前はその技術がありませんでした。すべての企業が物理的なサーバーを、自社のデータセンターやサーバールームで運用していたんです。
そして物理的な作業をする際、ハードウェアを冷却するために、データセンター内は非常に寒く設定されていました。エンジニアは、その極端に寒い環境で長時間作業をするのが当たり前の時代でした。
寺田:それはいつ頃のお話ですか?
永江:日本でクラウドが本格的に普及し始めたのは、2000年代後半から2010年代前半にかけてです。象徴的な出来事としては、AmazonのAWSが日本に東京リージョンを開設したのが2011年で、この頃から大きな流れが生まれたと思います。
寺田:一方で、インターネットが一般に普及し始めたのが1995年頃ですね。
永江:ええ、Windows 95の登場で利用者が爆発的に増えました。
寺田:その頃からITインフラというものは存在しますよね。
永江:もちろんです。
寺田:1995年頃からクラウドが普及し始める2011年頃までは、主に物理サーバーで作業をされていた時代ということですね。ちなみに、その頃の働き方はどのようなものだったのでしょうか。
永江:クラウドが登場する前、特に2000年頃の話ですが、働き方の面では今に比べてかなり長時間労働だったと思います。当時は、社会的に「IT業界は激務で長時間労働」というイメージが定着していた時代でした。
寺田:実際に激務だったのですか?
永江:はい。IT業界の平均残業時間は、今よりもずっと長かったですね。
寺田:それほど業務量が多かったということでしょうか?
永江:そうですね。しかしその後、まず仮想化技術が登場し、クラウドが普及したことで、業務を効率化できる部分が非常に増えました。例えば、以前は現地に行く必要があった作業も、サーバー自体がデジタル化されたことで遠隔操作が可能になりました。また、プログラムで効率的にサーバーを動かすこともできるようになりました。
寺田:遠隔操作ができなかった時代は、インフラエンジニアの方々が現地で物理的に作業をされていたということですね。とても寒い部屋で。
永江:その通りです。
寺田:その頃、エーピーコミュニケーションズは、どのような事業をされていたのですか?
永江:先ほど申し上げた通り、ネットワークの保守からスタートしていて、創業から数年間は、いわゆる保守・監視業務が中心でした。24時間365日のシフト体制で、ネットワークやハードウェアに異常がないかを常に監視し、何かあれば対応するという業務が多かったですね。
寺田:現在とは大きく違うのですか?
永江:はい、現在ではそうした業務はほとんど行っていません。24時間365日体制の業務もゼロではありませんが、全従業員500名弱のうち、ごくわずかです。
寺田:オンプレのデータセンターからクラウドへは、一気に移り変わったわけではないと思いますが、その間の変遷はどのようになっているのでしょう?
永江:私たちの会社が新しいことに取り組み、技術レイヤーを上げてきていますが、それがイコールで、「業界全体の歩み方」というわけではありません。
業界全体で見れば、現在も運用・保守の仕事は多く存在する中で、私たちはその分野から、より上流の工程へとシフトしてきました。技術レイヤーの変化は会社によって異なりますが、私たちはこの30年で、監視・保守中心から設計・構築、さらには要件定義といったところに事業内容を変化させています。
寺田:お話を伺っていると、IT業界に対して「ブラック」なイメージを持つ方がいるとすれば、それは当時の名残なのかもしれませんね。
永江:もしIT業界にそのようなイメージをお持ちの方がいらっしゃるとすれば、それは当時の印象が残っているからかもしれません。
もちろん会社による差はあり、納期前には忙しくなることもありますが、当時と比べると業界全体で労働時間は減少し、労働環境は改善されている企業が非常に多いです。その理由の一つは、先ほどお話しした仮想化やクラウドといった「技術の進化による作業効率の向上」です。
これに加えて、2019年前後の「働き方改革関連法」の施行も大きな要因です。特に大手のお客様やIT企業がこの動きに敏感に反応し、就業環境を大きく改善しました。その影響が業界全体に波及し、過重労働は大幅に減少したと考えています。
寺田:技術革新だけでなく、社会的な働き方の変化もITインフラ業界に影響を与えているのですね。
永江:ITインフラに限らず、IT業界全体に言える話だと思います。さらに、新型コロナウイルスの影響も大きいですね。テレワークは技術的には以前から可能でしたが、社会の概念としてはそこまでマジョリティではありませんでした。
寺田:技術的にできていたのに、していなかったのですね。
永江:そうですね。それが2020年、ある意味、強制的に社会全体でテレワークへ移行しました。これが働き方を大きく変えました。
現在、オフィス回帰の動きも見られますが、IT業界に関しては、多くの企業でリモートワークやテレワークが定着しています。
まとめると「技術の進化」「社会的な働き方改革」、そして「コロナ禍によるテレワークの浸透」という三つの大きな波を経て、IT業界の労働環境は大きく変わりました。2000年頃の「長時間労働で大変」というイメージは、今や過去のものとなりつつあります。
寺田:なるほど。小山さん、ここまでの話を聞いていかがですか?
小山:知らなかった部分もあって、なるほど、と聞き入ってました。私も昔は同級生がSIerで働く様子などを見て、IT業界は労働時間が長いというイメージを持っていました。しかし、この10年で働き方は本当に変わりましたね。
変化の一つとして、これまで比較的少ないと言われてきた女性の活躍が目立つようになってきた点が挙げられます。開発エンジニアやデザイナーの分野では少し前から女性の活躍が広がっていましたが、インフラエンジニア、特に30代?40代の女性はまだ少ないのが現状です。しかし、働きやすさが向上したことで、若手の女性エンジニアは増えてきています。
かつて女性が少なかった理由の一つに、交替制勤務など体力的に厳しい側面があったことは事実ですが、今はそうした環境も改善されています。採用の視点から見ても、働き方の変化がエンジニアの構成比に変化をもたらしていると感じます。非常に良いことだと思います。
寺田:働き方に関しては、もっと色々とお聞きしたいので、ぜひ別の回で特集しましょう。
小山:ぜひ。昔のイメージで私たちの業界を見ている方は、きっとまだいらっしゃると思いますので。
4. クラウドの次へ。AI時代を見据えたインフラエンジニアの新たな価値
寺田:では、トレンドの変遷の話に戻りたいと思います。2011年頃からクラウドへの変遷が始まったとのことですが、そこから現在までのトレンドはどのようになっていますか?
永江:クラウドが世の中に受け入れられ始めてからも、特に日本では、すべてのシステムが一気にクラウドへ移行したわけではありません。日本の産業界は全体的にクラウド利用に慎重で、特に金融や官公庁などの業界では、時間をかけて段階的に導入が進められました。これらの分野でクラウド活用が本格化したのは、比較的最近のことです。
寺田:その中で、エーピーコミュニケーションズはどのように変化したのでしょうか。
永江:まず規模なところでいうと、この期間で従業員数は倍以上になりました。事業の幅もエンジニアの数も大幅に拡大した時期です。
事業内容に関しては、もともとネットワーク保守からスタートした経緯もあり、「ネットワーク分野に非常に強い」という特長があります。そこからサーバー、クラウドへとエンジニアの専門領域を広げてきました。現在はネットワーク単体の仕事は減少し、クラウドと組み合わせた案件が主流になっています。
寺田:求められる技術も変化していますね。小山さんの視点から見ると、エンジニアに求められるスキルはどのように変わってきていますか?
小山:昔は「どのツールを使えるか」が重要でしたが、今はより総合的なスキルが求められるようになりました。例えば、AWSの様々なサービスを組み合わせることで、一つの技術だけでは解決できない複雑な課題に対応する必要があります。
また、DXやAIの推進には、しっかりとしたインフラ基盤が不可欠であるため、採用で求められる要件も変化しています。以前は特定の専門職にしか求められなかった知識が、今ではより幅広い職種で必要とされています。ですから採用が難しくなってきている一方で、応募者側も努力が必要です。
これからは、企業の経営陣に技術的な説明をする機会も増えるため、技術だけでなくビジネスへの理解も不可欠です。技術職の仕事は、よりダイナミックで大規模になっており、求められる要件も高度化しています。
永江:もちろん高度な技術力は常に求められますが、それに加えて、「お客様の課題解決のために何ができるか」という視点が、社内で年々重要になっています。技術を追求するだけでなく、それをどう活用するかという独創性や発想力が問われるようになっていますね。
近年では特に、AIがクラウドを通じて業界に大きな変化をもたらしており、この傾向は顕著です。
時代の変遷を整理すると、まず2000年代後半から2010年代にかけて、オンプレから仮想化、そしてクラウドへと移行が進みました。2010年代後半になると、クラウドを使う前提で設計する「クラウドネイティブ」という考え方が広まり、DockerやKubernetesといった技術が標準的に使われるようになり、システム設計が大きく変わります。
さらに、マルチクラウドやハイブリッドクラウドが普及し、現在ではAI関連のインフラも非常に重要になっています。
寺田:小山さんは、このAIによる変化をどう感じていますか?
小山:採用でもAI関連人材の獲得を進めていますが、業界全体としては、まだ明確な成功パターンが確立されておらず、各社が模索している段階だと感じています。生成AIやデータ活用など、様々な文脈でAIが語られますが、それをいかにビジネス成長の手段として活用していくか。私たちも含め、多くの企業がその方法を模索している状況です。
寺田:そう考えると、非常に面白い時代ですよね。かつては「ITインフラだからこれをやる」と決まっていた部分がありましたが、今は「これからどうしていくか」を考えるところから始まっています。
小山:生成AIがコードを書いてくれるようになれば、エンジニアはより創造的な「考える」部分にリソースを割けるようになります。私は直接開発に携わるわけではありませんが、採用を通じて組織や業界がどう変わっていくかに関われるのは、非常に楽しいと感じています。
寺田:これから一緒に世界を作っていけるようで、ワクワクしますね。
5. クロージング
寺田:さて、第2回目となりましたが、永江さん、いかがでしたか?
永江:ITインフラの歴史を振り返る話もあったので、「あの頃はどうだったかな」と考えながら話すのは、少し懐かしい気分でした。
寺田:それだけ時代が変わったということですよね。小山さんはいかがでしたか?
小山:私自身が直接見ていなかった時代のピースが、今日のお話で埋まったような感覚です。業界への理解がより深まりました。変化の中に自分がいることを、これからも楽しんでいきたいと思います。
寺田:お話を聞いているだけで、これから時代が大きく変わる真っ只中にいるのだと実感でき、ワクワクしました。これからの時代を作っていくのは、まさにこれからこの業界に入ってくる方々だと思うと、本当に楽しみですね。
この番組はSpotify、Apple Podcast、Amazon Musicで配信中です。
ポッドキャストへのフォローとレビューもぜひお願いいたします。
番組へのご質問やリクエストは、専用フォームか、各種SNSから受け付けております。気になることがありましたら、ぜひお寄せください。


