2025/05/29
インフラエンジニアのホントのところ #3|ITインフラの重要性って?
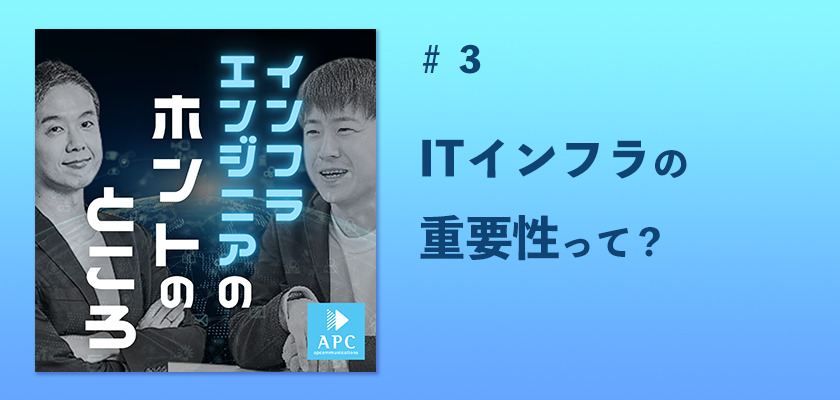
ITインフラって、「なんだか難しそう」「地味で大変そう」と思われがち。
でも実は、社会を支える根幹にある、とてもやりがいのある仕事なんです。
そんなリアルをお届けするPodcast 「インフラエンジニアのホントのところ」。
MCにはベンチャー女優の寺田有希さんを迎え、当社の副社長 永江耕治と採用責任者 小山清和が、現場・経営・採用の視点から語ります。
今回のテーマは「ITインフラの重要性って?」。
『ITインフラは重要だ!』と一口に言っても、その重要性も、時代によって変化を遂げてきているのではないでしょうか。
昔はどう重要だったのか。これからどう重要になっていくのか。
『ITインフラの重要性』について、徹底解剖していきます。
<目次>
1.オープニング
2. ITインフラとは、サービスの「土台」
3. 昔と今でどう違う?ITインフラの重要性の変化
4. インフラエンジニアの役割はどう変わったのか
5. 日常生活に深く関わるからこそ、高まる重要性
6. クロージング
1.オープニング
寺田:言葉は有名でも、何かと知らないことが多いインフラエンジニアの世界。キャリアや将来性、魅力など、ついつい隠れがちな「本当のところ」を、業界のプロであるエーピーコミュニケーションズの永江さん、小山さんと共にインフラエンジニアのキャリアを徹底解剖していきます。
永江:同じくMCを務めます、エーピーコミュニケーションズの永江です。取締役副社長をしております。どうぞよろしくお願いいたします。
小山:同じくMCを務めます、エーピーコミュニケーションズの小山です。採用責任者をしています。よろしくお願いいたします。
寺田:そして、同じくMCを務めます、ベンチャー女優の寺田有希です。早くも第3回目が始まりました。
永江:そうですね。まだあまり小山さんと掛け合いができていないので、もう少し絡んでいけるといいなと思っています。
寺田:ぜひ絡んでください。小山さん、いかがですか?
小山:絡んでもOKという許可が出たと解釈してよろしいでしょうか(笑)。少し猫をかぶっていたかもしれませんが、リスナーの皆さんに引かれない程度に頑張りたいと思います。
寺田:お二人は社内でもよくお話されるのですか?
永江:お互いにリモートワークが多いので、会議での会話が中心です。最近は会食でご一緒する機会もありましたね。
小山:そうですね、月に2回ほどありました。
寺田:でも、やはりリモートワークが多いんですね。
永江:うちはほとんどですね。とはいえ、誰かと会いに行くために出社することも週に1、2回ありますね。
寺田:では、今日もお二人でお話を盛り上げていただければと思います。さて、本日のテーマは「ITインフラの重要性」です。
ITインフラがどれほど現代社会において重要なのかについては、これまでの放送でも度々話題に上がってきました。ですが、一口に「重要」と言っても、その意味合いは時代の流れと共に変わってきたのではないでしょうか。
本日は「昔はどう重要だったのか」、そして「これからどう重要になっていくのか」、ITインフラの重要性について徹底解剖していきたいと思います。
2.ITインフラとは、サービスの「土台」
寺田:本編に入る前に、少し前提を整理させてください。そもそもITインフラとは、サービス開発においてどのような立ち位置の存在なのでしょうか?
永江:ITインフラは、アプリケーションやサービスを支える「土台」と捉えていただくと分かりやすいです。
例えるなら、建物を支える基礎や、街の道路、電気のようなものですね。インフラがしっかりしていないと、アプリの性能が出なかったり、セキュリティ上の問題が起きたりします。
寺田:家に例えると、基礎工事がしっかりしていないと地震で崩れてしまう、というようなことですね。
小山:そうですね、いくら立派な家が建っていても、基礎が弱かったり、水道や電気が通っていなかったりしたら住めません。それと同じで、ITインフラという土台がなければ、私たちが普段使っている便利なサービスも成り立たないわけです。
寺田:見た目が良い家でも基礎工事に欠陥があれば住めないのと同じなんですね。
小山:ITインフラが脆弱だとサービスが停止したり、システムが落ちたりしてしまいますからね。
3.昔と今でどう違う?ITインフラの重要性の変化
寺田:では、そのITインフラの重要性は、昔と今でどのように変わってきたのでしょうか?
永江:重要性に関して言うと、基本的には大きな変化はありません。
「通信が止まるとサービスが使えなくなる」という根本的な重要性は、昔も今も同じです。しかし、その「姿そのもの」は時代と共に大きく変化しました。一番大きな変化は、クラウドサービスの登場です。
寺田:クラウドが登場する前は、どのような状況だったのですか?
永江:以前は「オンプレ」といって、物理的なサーバーを自前で用意するのが当たり前でした。新しいサービスを始めるには、まずサーバー機器を発注して、設置する必要があったんです。インフラ担当者は、空調の効いたサーバールームで、物理的にハードウェアを並べ、ケーブルを配線するといった作業をしていました。
寺田:準備だけでも大変そうですね。
永江:ええ。物理的な準備に数週間から数ヶ月かかることも珍しくありませんでした。それがクラウドの登場によって、物理的なものがなくなり、自分たちでサーバー機器を買わなくても、AWSやAzureといったパブリッククラウドを利用することで、インフラ構築のスピードが速くなったという変化がありました。極端な話、数分でインフラを構築できるようになりました。
寺田:昔は「どの機材を選ぶか」「どうケーブルを配線するか」といった物理的な環境構築が重要だったわけですか?
永江:そうですね、やらないといけないことでした。
小山:クラウドの登場は、ビジネスの世界にも大きな影響を与えました。
インフラを自前で用意するハードルが劇的に下がったことで、ベンチャーやスタートアップが次々と新しいサービスを生み出せるようになったのです。メガベンチャーと呼ばれる企業も、この流れとともに成長してきた部分があると思います。
ITインフラの変化が、ビジネス界の勢力図まで変えたと言えるんじゃないでしょうか。
寺田:サービスを作るハードルが下がったのは大きな変化ですね。
小山:コストはかかるものの、クラウドを活用すればサーバーの購入・設置、運用といった悩みが減り、サービスを考えるところに注力できるようになったのは大きいですね。
4.インフラエンジニアの役割はどう変わったのか
永江:インフラ構築が楽になったと聞くと、「インフラエンジニアの仕事は簡単になったのでは?」という印象を持たれるかもしれません。しかし、実際はその逆で、役割はより複雑に、そして広がってきています。
寺田:具体的には、どのように変わったのでしょうか?
永江:例えば、クラウド上での設計やコスト管理といった、世界中のユーザーに高速でコンテンツを届ける仕組みづくりなどが求められるようになりました。また、開発と運用の橋渡し役を担うSRE(Site Reliability Engineer)という新しいポジションも登場しています。
より難しいことが求められるようになっているとも言えます。
寺田:物理的な技術力だけでなく、よりクリエイティブな能力が求められるようになった、というイメージでしょうか。
永江:そうですね。
寺田:それは、役割が枝分かれして、役割の数が増えてきているということなんでしょうか?
永江:幅は広がってきていますね。
永江:その中で企業で考えるのであれば、サービスの成長戦略の中核としてインフラも語られるようになってきています。
全員がそこに関わるわけではないですが、より重要なポジションの中にインフラエンジニアの役割の人が含まれてきた傾向があります。
寺田:昔はサーバー室にこもって作業するような、少し隔離されたイメージがあったかもしれませんが、現在はチームとして一緒に開発をしている。その中に重要なポジションとしてインフラも入っているという感じですか。
永江:企業としてサービスをどう設計するかについても、一部役割として担うようになってきている、と言えます。
寺田:大きな変化ですよね。
永江:もちろん、地道な作業が中心の役割もありますが、「インフラ=裏方で地味」というイメージだけではなくなりました。
寺田:関わり方次第では、昔とは全く違う働き方ができるというわけですね。
永江:ただ、それができるには、それなりの知識やスキル、経験が求められるので、簡単な道ではありません。しかし、キャリアの観点で考えると、そういう選択肢が増えたことは、良いことだと言えるかと思います。
5.日常生活に深く関わるからこそ、高まる重要性
寺田:今やインターネットのない生活は想像できません。特に若い世代にとっては、それが当たり前の世界ですよね。現代におけるITインフラの重要性について、改めてどうお考えですか?
永江:昔も今も、インフラなしにITサービスは成り立ちません。検索エンジンや動画配信、オンラインゲームといったサービスが当たり前に使えているのは、インフラが正常に機能しているからです。
もし大規模な障害が起きれば、人気サービスが一斉に停止し、ニュースになるほど影響は大きいですよね。
小山:できることが増え、新しいサービスが生まれた分、「サービスを絶対に止めてはならない」という緊張感は、より高まっています。事業的な損失やユーザーの離脱に直結しますからね。ただ、その重要性が世の中に十分に伝わっているかというと、少し疑問です。
多くの人は「エンジニア」と聞くと、アプリケーションを開発するエンジニアをイメージするのではないでしょうか。
寺田:確かに、意識しないほど当たり前の存在になっているのかもしれませんね。
小山:採用の現場でも変化を感じます。昔はインフラエンジニアから開発エンジニアへのキャリアチェンジが一般的でしたが、今は逆に、開発エンジニアからインフラ系のSREにキャリアチェンジする人も増えています。
そこに対して重要だと考えるからこそ、キャリアチェンジを考えるのだと思います。会社としても採用を強化したり、ポジションを作ったりする動きは、ITインフラの重要性が高まっていると言えるのではないでしょうか。
永江:役割としてはどんどん変化しています。
インフラの世界でも、クラウドの進化やインフラをコードで管理する「IaC(Infrastructure as Code)」など、新しい技術が次々と登場しています。地味なだけでなく、常に新しいことを学ばないといけないし、学べるエキサイティングな世界でもあると思います。
寺田:幅も変わり、求められることや描けるビジョンも変わっているんですね。
6. クロージング
寺田:さて、本日はITインフラの重要性についてお話しいただきましたが、お二人はいかがでしたか?
永江:改めて話してみると、ITインフラの重要性は、やはり「見えない存在」だからこそ認識されづらいのだと感じました。
ITではないですが、最近、水道管の老朽化がニュースになっていますが、インフラというのは、一度障害が起きると「何をやっているんだ」と非難されがちです。しかし、それだけ大事なものを支えている人たちがいる、ということを知っていただけたら嬉しいですね。
寺田:普段は感謝されることは少ないのに、問題が起きた時に大きく非難されるというのは、非常に悲しいことですね。小山さんはいかがでしたか?
小山:インフラエンジニアがもっと注目を浴びればいいというわけではないですが、もう少しリスペクトを受けてもいい存在だと感じます。彼らが様々な難しい課題にチャレンジしてきたからこそ、今の便利なサービスが生まれているわけですから。採用活動を通じて、その価値を伝えていきたいという気持ちが、より一層強まりました。
寺田:大きいサービスほど、止められない。安定運用が求められる。そう考えると、ITインフラの重要性というものは高まっています。
小山:目に見えない場所で、日々試行錯誤しながらサービスを支えてくれています。
寺田:私たちもそのことを想像しながら、日々のサービスを使っていきたいと感じました。お二人とも、本日もありがとうございました。
この番組はSpotify、Apple Podcast、Amazon Musicで配信中です。
ポッドキャストへのフォローとレビューもぜひお願いいたします。
番組へのご質問やリクエストは、専用フォームか、各種SNSから受け付けております。気になることがありましたら、ぜひお寄せください。


