2025/06/11
インフラエンジニアのホントのところ #5|インフラエンジニアはどんな仕事をしているの?
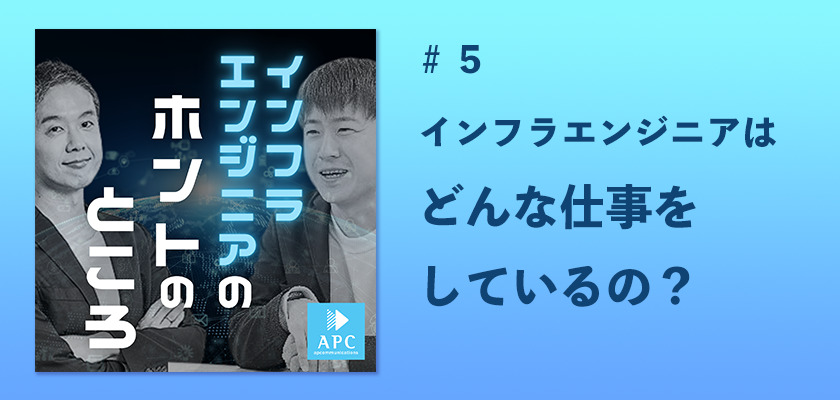
ITインフラって、「なんだか難しそう」「地味で大変そう」と思われがち。
でも実は、社会を支える根幹にある、とてもやりがいのある仕事なんです。
そんなリアルをお届けするPodcast 「インフラエンジニアのホントのところ」。
MCにはベンチャー女優の寺田有希さんを迎え、当社の副社長 永江耕治と採用責任者 小山清和が、現場・経営・採用の視点から語ります。
今回のテーマは「インフラエンジニアはどんな仕事をしているの?」。
「インフラエンジニア」にはどんな種類の仕事があり、普段はどんな仕事をしているのでしょうか?
なかなか知ることが難しい【仕事内容の実態】を、インフラエンジニアキャリアのプロである二人が、徹底解剖しました。
<目次>
1.オープニング
2.インフラエンジニアの仕事の種類:「環境」と「専門分野」それぞれの違い
3.エンジニアのキャリアパス:専門家か、ジェネラリストか
4.ITインフラ企業の事業変化
5.日々の業務内容とは?設計から運用・保守まで
6.クラウド時代における業務の変化
7.クロージング
1.オープニング
寺田:言葉は有名でも、何かと知らないことが多いインフラエンジニアの世界。キャリアや将来性、魅力など、ついつい隠れがちなインフラエンジニアの本当のところを、業界のプロであるエーピーコミュニケーションズの永江さん、小山さんと共に徹底解剖していくポッドキャストです。
永江:MCを務めます、エーピーコミュニケーションズ 取締役副社長の永江です。どうぞよろしくお願いいたします。
小山:同じくMCを務めます小山です。エーピーコミュニケーションズでは採用責任者の仕事をしています。よろしくお願いします。
寺田:そして同じくMCを務めます、ベンチャー女優の寺田有希です。 早くも第5回となりました。 そろそろお2人にも感想とか届き始めてますか?
永江:そうですね。つい最近、知り合いの経営者の方から「番組を聞きました。今度オフィスでお話を聞かせてください」と連絡をいただきました。こうしたきっかけが生まれているのは嬉しいですね。
寺田:素晴らしいですね!小山さんはいかがですか?
小山:友人が「フォローしたよ」と教えてくれたり、SNSでの反応の違いも感じています。特にLinkedInでの反応が良く、「いいね」がつきやすいと感じますね。
寺田:プラットフォームとの相性もありそうですね。我々も探りながら、番組を大きくしていきましょう。
さて、本日のテーマは「インフラエンジニアって、どんな仕事をしているの?」です。
これまで「ITインフラとは」「インフラエンジニアとはどのようなものなのか」について、いろいろな角度から徹底解剖をしてまいりました。全体像が見えてきたところで、やはり気になるのは実際の仕事内容ですよね。
なくてはならない重要なお仕事でありながら、「影のヒーロー」になりがちなインフラエンジニア。今日は「どんな種類の仕事があるのか」「普段はどんな仕事をしているのか」という2つのテーマで、お二人に詳しく語っていただきます。
2.インフラエンジニアの仕事の種類:「環境」と「専門分野」それぞれの違い
寺田:では早速ですが、インフラエンジニアにはどんな種類の仕事があるのでしょうか?
永江:一言でインフラエンジニアと言っても、業務内容はいくつか分かれています。まず大きく分けると、「オンプレ」と「クラウド」という2つの環境の違いがあります。
技術領域においてでいうと、大きく「ネットワーク」「サーバー」、その両方に関わる分野として「セキュリティ」という分け方ができます。
寺田:まずは、「オンプレ」と「クラウド」からお聞きしたいのですが、「オンプレ」は、物理的なサーバーを扱うお仕事ですよね。以前、涼しいサーバルームで作業するというお話もありました。
永江:その通りです。オンプレの場合、物理的な作業が伴います。例えば、「電源をどう確保するか」といった配線の知識や、サーバーというハードウェア自体の知識も必要になります。
寺田:物理的なモノに対する知識が必要なんですね。逆に、クラウドはいかがですか?
永江:クラウドの場合は、物理的なモノに触るのではなく、インターネット上でサーバーを作ったり、設定を行ったりします。
寺田:物理的な知識というよりは、どのクラウドサービスを使うか、といった専門的な知識が求められるんですね。
永江:とはいっても、共通のスキルが必要です。環境として物理なのか、デジタルなのかの違いがありますが、その上で動く技術の知識は共通化しています。
寺田:その共通している専門分野についても教えてください。
永江:大きく分けると「ネットワーク」「サーバー」という分け方ができます。また、その両方に関わる分野として「セキュリティ」があります。
寺田:それぞれの違いは何でしょうか?まず「ネットワーク」は、どんなお仕事ですか?
永江:ネットワークエンジニアは、文字通りネットワークの専門家です。扱うモノでいうと、ルーターやスイッチといったネットワーク機器です。それらを設定し、通信ができる環境を作るのが主な仕事です。
寺田:では、「サーバー」はいかがでしょう?
永江:サーバーエンジニアは、サーバーにOSをインストールしたり、その上で動くデータベースやWebサーバーといった「ミドルウェア」を構築したりします。技術的なところで言うと、「仮想化」というものもありますが、基本的にはOSのインストール、ミドルウェアの構築と理解してもらえればよいかと思います。
寺田:ネットワークという土台の上に、サービスが動くためのベースを載せていくイメージですね。そして「セキュリティ」は、どのような役割を担うのですか?
永江:セキュリティエンジニアは、サイバー攻撃や不正アクセスから情報を守る専門家です。例えば、ネットワークのセキュリティを強化する「ファイアウォール」といったツールや、IDS (不正侵入検知システム) と IPS (不正侵入防御システム) といったシステムがありますが、それらにおける脆弱性に対応します。
また、誰がどこまでアクセスできるかという権限を管理するなど、システムを安全に守るための知識と技術が求められます。これは常に新しい脅威が出てくるため、終わりなき戦いとも言えます。
寺田:ここまで一緒に説明を聞いていただきましたが、小山さんはいかがですか?私も想像以上にいろんな分野があるなと思っているんですけど。
小山:インフラエンジニアについて説明をするのはなかなか難しいと思っていたんですが、永江さんの話を聞いて、改めて理解が深まったところがあります。
私たちが普段何気なく使っているサービスが、いかに緻密に設計されているかがよく分かります。改めて、エンジニアの方々は本当にすごいなと感じます。
寺田:そうですね、基盤作りの中にもいくつも分野がわかれている時点で、すごく複雑なんだろうなということも想像できますし、それだけ専門知識も必要で、人手も必要ということですからね。
3.エンジニアのキャリアパス:専門家か、ジェネラリストか
寺田:いろんな専門知識が必要で、幅広く分かれているということは理解できたんですが、インフラエンジニアの方々は、全ての仕事を受け持つんですか?それとも、ご自身の専門分野を作っていくものなんでしょうか?
永江:分野が広いので、あらゆることに詳しくなっていくのは、情報をアップデートしていくことも含めて考えると、かなり難しくなってきていますね。なので、大規模システム・プロジェクトになると、分業化を進めていく必要があります。
ただ、分業によって、関わるメンバー同士がお互いの業務をまったく理解できない状態になると、プロジェクトの進行や品質チェックが難しくなります。
そのため、ある程度幅広く全体を俯瞰し、概要レベルで管理できる存在が必要になります。
もちろん、ひとりで全体を深く理解できるのが理想ではありますが、人間が認知・習得できる範囲には限界があります。だからこそ、チーム全体で補い合いながら全体像を見渡す体制づくりが重要になってきます。
寺田:なるほど。
永江:そんな中でエンジニアのキャリアがどうあるべきかと言うと、正しい姿が一つとは言えないと思っています。
何かを深く突き詰めることで、市場価値を高めることができるかもしれない。一方で、例えばAとBとC、この三つの分野にそれなりに詳しい人というのが市場にそう多くなければ、付加価値が高くなります。
ある一つのスキルをものすごく突き詰めて、日本、あるいは世界でトップレベルになったとしても、その技術が世の中であまり使われなくなれば、市場価値は下がってしまう可能性があります。
ですので、「どうあるべきか」という問いに対しては、本人がどういう志向を持つかという点に加えて、世の中が、そして技術がどう変わっていくかによって、「どの職種のスキルを持っていた方がいいか」という答えも変わってしまうため、予測するのは難しいと思います。
寺田:技術の進化が早いということも相まって、今必要とされているものが3年後には、新しい技術が出てきてなくなってしまう、みたいなことも簡単に起こってしまいますもんね。
永江:ITの世界では、次々と新しい技術が登場します。もちろん、昔からある技術の基本や基礎には共通点もありますが、たとえば伝統芸能のように、1000年以上受け継がれてきた変わらない技術とは性質が異なります。伝統芸能のような分野であれば、一つの技を極めていくという選択肢もありますが、ITの場合は技術の移り変わりが早いため、同じような考え方は通用しづらい。だからこそ、常に新しい技術に柔軟に向き合う姿勢が求められると感じています。
寺田:小山さん、採用の観点ではいかがですか?広い知識が必要だったりする一方で、専門知識を極めたりと、自分の力でキャリアを作っていくことについて、幅広い考え方ができるのかなとも思ったのですが。
小山:例えば開発の領域ではフレームワークが色々出てくるんですけど、「これがデファクトスタンダードだ」みたいなのがでてきて、それ以外が廃れていくというのはやっぱりあります。「これがいい」と思ってやっているものが、いつのまにか淘汰されていく。
でも、世の中の流れに合わせていかないと、仕事を探すというときにキャリアが広がらなくなってしまいます。だから、中には「好きなのはこの技術だけど、仕事上はこっちをやっています」という人もいるんですよね。
流れに身を任せ過ぎても駄目だし、でも任せなきゃいけないときもあるし…そこを乗り越えるのが本当に難しい仕事だと、客観的に見ていて感じますね。
寺田:キャリア構築の話は奥が深そうなので、今後お二人に詳しく語る回も作らせていただきたいなと思います。
4.ITインフラ企業の事業変化
寺田:個人の話については理解が深まったんですが、これを会社に置き換えると、どうなのでしょうか。会社も専門分野を持つものなのか、それとも幅広くやるのか。いかがですか?
永江:もちろん会社ごとに違うと思います。なので、エーピーコミュニケーションズを例としてお話ししますね。私たちはITインフラ中心の会社で、ソフトウェア開発の割合はすごく小さいです。
設立して30年ほどが経ちますが、最初はネットワーク領域がほぼ100%でした。そこからサーバーに広がり、技術の変遷もあって、仮想化技術が出てきて、クラウドが出てきて、という流れです。
現在はだんだんと事業内容が変化し、セキュリティやデータ基盤の構築という仕事も増えています。
データ基盤の構築とは、ガバナンスが効いた状態でデータを収集、蓄積、分析など使いやすくする仕組みの構築です。例えば「AI」とか「ビッグデータ」といったキーワードをよく耳にするかと思います。AIを使うにしても大量のデータが必要で、そのデータはどこかに入れているんですよね。つまり、AIで活用するための「データを入れる箱」が必要になってくる。そういうものを作っていく仕事が増えてきています。
皆さんもAIを使うことが増えていると思いますが、そこに関わるインフラの仕事が最近は増えてきているんです。ネットワークやクラウドの仕事がなくなっていくわけではありませんが、割合の変化はどんどん起きていますね。
寺田:そうなんですね。第2回でITインフラの変遷についてお伺いしたときも、AIが出てきて大きな波が来ているっていうお話もありましたけど、まさに今、変化の過渡期。インフラを整備する概念が変わってきてるんですね。
永江:そうですね。AIを使うにしてもインターネットを介することがほとんどだと思います。そうなると、ネットワークやサーバー、クラウドが必要になる。インターネットを使ったシステムが新しくなったり増えたりする限りは、そこに関わるITインフラの仕事は増え続けます。
「安定」という観点で言うと、インターネットがなくならない限りは、何かしらの仕事は残り続ける分野だと思います。
寺田:なくならない。だけど、細分化し、複雑化する分野だと。奥が深いですね。
永江:そうですね。変化していくので、そこにはついていかなければいけない。だからこそ面白いのだと思います。
5.日々の業務内容とは?設計から運用・保守まで
寺田:続いては、「普段の仕事」についてです。どういった分野があって、どういった知識が必要なのかについては理解ができたのですが、実際どんな仕事をしているのかを聞いていけたらと思います。
永江:インフラエンジニアの仕事は、工程で分かれてきます。
まずはシステムを「設計」するフェーズがあって、次に「構築」があります。試験をする「テスト」という工程を経て、システムが出来上がったら今度は使い続けていく上での「運用」があります。運用が始まった後は、修正や改善があるのでそこにもエンジニアが関わってきます。
それぞれのフェーズによって、どういうスキルが求められるか、どんな仕事をするかが変わってきますね。
寺田:一つずつの工程において、どのような業務をしているのかを聞いていきたいと思います。まずは「設計」についてです。
永江:ものすごく簡単に言うと、お客様がどのようなシステムを必要としているのかを理解して、それに合ったシステムを形にするのが設計の仕事ですね。
寺田:設計スキルもですが、コミュニケーションスキルも重要になる業務ですか?
永江:そうなんです。単に技術に詳しいだけでは、良いシステムは作れません。
お客様の要望を実現するためには、ヒアリングや要件定義といった工程がとても重要で、そこが設計の難しさでもあります。
たとえば、お客様が「素敵な家を作りたい」と漠然とした希望を持っているとします。でも、家づくりに詳しいわけではないので、具体的な仕様までは見えていません。
その要望から「つまりこういう家を作りたいんですね。では、予算はこのくらい、耐震構造が必要で…」と、背景や制約条件を整理していく必要があります。
さらに、予算やスケジュールといった制限もあるため、丁寧にやり取りしながら、お客様の意図をくみ取り、より明確な形に落とし込んでいく。
そうした技術的な知識を土台にした提案こそが、設計の役割です。
寺田:続いて、「構築」はいかがですか?
永江:要件として設計されたものから、具体的にそのシステムを作っていく部分が「構築」です。
寺田:システムを作る人ですね。
永江:ですから「設計」に比べて、さらに技術寄りです。具体的にその技術をどう扱えるかが分かっていないとできない役割です。
寺田:サービスができた後の「運用」はどうですか?
永江:運用も幅が広く、技術的に高いレベルを求められるケースもあります。
例えば24時間365日、システムがちゃんと動いているという確認も含まれますし、場合によっては、モニタリングした上で何かあったら自分で解決する。もし自力で解決できない場合には、迅速に適切な担当者へエスカレーションし、できるだけ早く復旧させるための体制構築や対応プロセスの整備も、運用の重要な役割の一つです。
さらに、高度な運用を考えるうえでは、日々の改善活動も欠かせません。システム運用の目的は、単に動かすことではなく、ビジネスの価値を継続的に高めていくことにあります。「このシステムは本当に価値を提供できているのか?」「もしそうでないなら、もっと良い方法はないか?」といった視点で、システムを動かしながら継続的に見直し・改善していくことも、運用の重要な役割です。
こうした取り組みも含まれることから、運用という仕事の幅は非常に広いのです。
寺田:続いて「保守」はいかがですか?
永江:「保守」は、モニタリングに近いです。例えば、監視や障害対応、定期的なバックアップ、アップデートの実施などが含まれてきます。
寺田:「障害対応」についてはいかがですか?
永江:モニタリングしている中で、おかしい挙動やうまくサービスが動いていないなど異常が検知された場合は、適切な関係者に素早く伝えていくことが求められます。
その後に、問題がどこにあったのかを切り分けし、それが特定の技術分野であれば対応できる人が障害対応にあたる、というのが基本的な流れですね。
寺田:突然呼び出されることもありますか?
永江:場合によってはあり得ます。
寺田:「セキュリティ対策」はどうですか?
永江:これは本当に幅が広いんです。例えば情報漏洩が起きないか、外部からの侵入はないか、アクセス権限をどうやって狭めておくべきか、といったことへの対応です。
制限をかければかけるほどセキュリティは高くなりますが、システムを使う上では不便になってしまう。「セキュリティは確かに高いんだけど、システムとして使いづらいよね」となっても駄目なんです。
いろんな技術分野にまたがる話ではありますが、使いやすさとともに安全な状況をどうやって作るのか、を考えるのがセキュリティの仕事です。
寺田:少しでも使いづらいと文句も増えてしまうでしょうし、バランス感覚も重要そうです。
永江:そういうバランス感覚を持たなければいけない役割の人もいますね。
寺田:最後に「監視」はいかがですか?
永江:先ほどお話しした「保守」にもつながりますが、いわゆるモニタリングです。サービスやネットワークが正しく動いているかどうかを、ずっと見守るシステムを作ります。
異変を自動的に検知してアラートを出すだけの場合もありますし、アラートが出たら人間がすぐに対応できる体制にしていることもあります。24時間365日、必ず人間が対応する体制もあれば、夜間はシステムだけにしている場合もあります。
これは、対象のシステムに異変が起きたときにどれぐらい社会的なインパクトがあるか、コストをどれぐらいかけられるか、によって変わってきます。
寺田:本当に幅広いですね、こうやって改めてお聞きすると。小山さんいかがですか?
小山:知っていた部分はありますけど、改めて体系立てて、全体的に話を聞く機会はあまりなかったので、自分の理解も深まりました。
寺田:我々はサービスを使っているだけですが、その裏でこんなにも専門分野があって、こんなにも業務が多岐にわたっていることを知りました。想像できていなかった部分もあって、だからこそ、すごさとありがたさを感じます。
小山:本当にそうですね。なので、X(旧Twitter)とかでも、大規模な障害が起きたとき、「中の人、大変ですね。頑張ってください」って、逆に応援のコメントがあったりしますよね。理解している方だと、その大変さが分かっていらっしゃるのだと思います。
6.クラウド時代における業務の変化
寺田:クラウドの時代になって、エンジニアの日々の業務に変化はありますか?
永江:クラウド時代の前後で、業務はだいぶ変わったと思います。大きな変化の一つは、インターネットを介して作業できるようになったことです。それによって、どこかの場所に行って作業する必要がなくなり、自由度が生まれました。
クラウドの登場によって、従来は物理的に扱っていたサーバーがデジタル化され、プログラミングで制御できるようになりました。たとえばプログラムで「この処理を実行して」「こういう事象が起こったら、次にこの設定を行う」といった命令を記述できます。サーバーやネットワークの構成をコードで記述して、自動で構築したり、自動で変更できたりするような仕組みを作ることができるようになったんです。それが「自動化」になってくるんですけれども、効率化に繋がります。
システムの大きさに比例して、昔は多くのエンジニアを配置しなければならなかったのですが、こうした技術の変化によって配置されるエンジニアの数はだいぶ減っています。もちろん、技術的には高度になる部分もありますが、こういうところは働き方にも影響を与えてきていますよね。
寺田:インフラエンジニアも「コードを書く」っていうことですか?
永江:昔はインフラエンジニアがコードを書くことは、あまりありませんでした。求められることがゼロではないけれど、少なかった。それが、最近はコードを扱う技術が増えてきているので、キャリアを考えていく観点で見ると、やはりプログラミングのようなスキルもインフラエンジニアに必要になってくる、ということなんですよね。
寺田:これは大きな変化ですよね。エーピーコミュニケーションズではどんな変化が起きていますか?
永江:私たちの例で言いますと、「ネットワークの自動化」が大きな強みになりました。なぜなら、元々はネットワークの会社だったからです。
寺田:そうでした、事業内容の100%でしたもんね。
永江:デジタル化によって、ネットワーク機器もプログラミングで取り扱えるようになるのですが、ネットワークの分野はサーバーより、デジタル化しづらい傾向にあります。
寺田:そうなんですね。
永江:コンピューターネットワークには「OSI参照モデル」という7階層のモデルがあり、第1層は「物理層」、一番上の第7層は「アプリケーション層」と言います。その間には5つの層がありますが、ネットワークは主に物理層に近い、第3層ぐらいまでを扱うことが多いんです。
階層で言うと下の階層に近ければ近いほどデジタル化しづらいので、ネットワークの自動化は難易度が高くなるんです。
ですから、ネットワークに詳しくなかったり、プログラミングだけしかできなかったりすると、ネットワークの自動化は難しい。
ですが私たちには、ネットワークのスペシャリストとしての長い歴史と新しいことにも取り組む風土があります。結果、「ネットワークの自動化」というニッチな市場ではありますが、日本でトップクラスです!
寺田:物理的に構築する知識や経験があるからこそ、デジタル化によるネットワークの自動化を実現できるってことですね。歴史を感じますね。
永江:この歴史のおかげもあり、この分野の優秀なエンジニアが集まっています。たとえば自動化の分野では、Red Hat社の「Ansible」という製品がよく知られていますが、エーピーコミュニケーションズにはそのAnsibleに関する技術書の執筆に関わったり、技術雑誌にチームで連載を持ったりと、業界内でも名前の知られたエンジニアが在籍しています。
寺田:先ほど専門分野を持った方がいいのか、広く知っていた方がいいのか、それでキャリアがだいぶ変わるというお話もありましたけど、エーピーコミュニケーションズだからこそ身につけられる専門分野と強みがあるんですね。
色々なスキルが必要で、時代とともに対応していかなければいけないということは理解できました。インフラエンジニアといっても、様々な仕事が選べたり、キャリアが選べたり、ということですね。
小山:そうですね、昔と比べると選択肢は確実に広がったと思います。
なので「選べる」というのは間違ってはいないと思いますが、選べるようになるための必要なスキルも増えました。技術力はもちろんのこと、インフラがより一層事業に食い込んできているので、そもそものビジネスの理解が必要です。今までは担当者レベルの方とやり取りすればよかったところが、場合によっては経営陣と対話をしていかなければならないこともあります。
また、チームで連携する上で必要となるスキル、いわゆるポータブルスキルも同時に必要になってくると思います。
選ぶためには技術だけではない部分も磨かなければいけない、というのが今のインフラエンジニアを取り巻くキャリアの環境なのではないでしょうか。
寺田:職人気質なイメージがありましたが、職人だけではないという感じなんですかね。
小山:その観点も必要だとは思うんですけど、それ一辺倒で乗り切れるような規模感やビジネスへの影響度ではなくなってきた、ということだと思うんですよね。
寺田:キャリアに関しては、今後もぜひ詳しくお話を聞いていきたいと思います。
7.クロージング
寺田:本日は超大作になりましたが、かなり深いところまで掘り下げてお聞きできたと思うんですけれど、どうでしょうか?
永江:そうですね。ちょっと長くなりましたが、まだまだ詳細があるんだけどな、と思いながらお話ししていました(笑)。
寺田:そうですよね。でも、ここまで詳しく語っていただけてるものもなかなかないと思うので、かなり解像度が高くなったのではないかと思います。
小山:我々がやっていることを理解していただく上で、非常に重要な回になったんじゃないかなと思いました。
この番組はSpotify、Apple Podcast、Amazon Musicで配信中です。
ポッドキャストへのフォローとレビューもぜひお願いいたします。
番組へのご質問やリクエストは、専用フォームか、各種SNSから受け付けております。気になることがありましたら、ぜひお寄せください。


