2025/06/18
インフラエンジニアのホントのところ #6|インフラエンジニアがブラックって本当!?
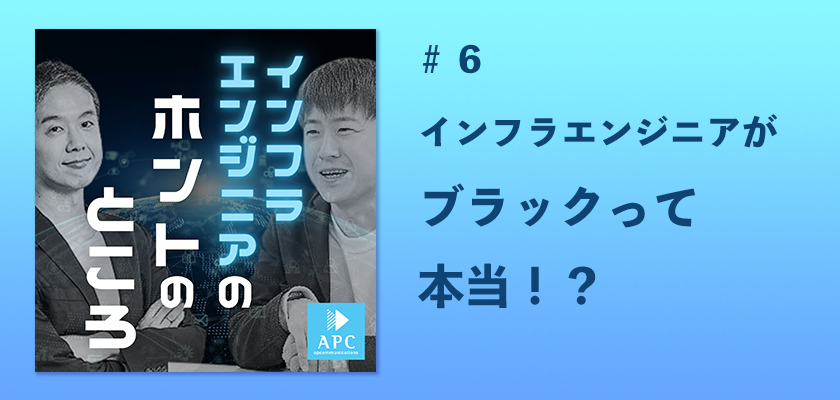
ITインフラって、「なんだか難しそう」「地味で大変そう」と思われがち。
でも実は、社会を支える根幹にある、とてもやりがいのある仕事なんです。
そんなリアルをお届けするPodcast 「インフラエンジニアのホントのところ」。
MCにはベンチャー女優の寺田有希さんを迎え、当社の副社長 永江耕治と採用責任者 小山清和が、現場・経営・採用の視点から語ります。
今回のテーマは「インフラエンジニアがブラックって本当!?」。
この噂は本当なのでしょうか? インフラエンジニアキャリアのプロである二人に、ズバリ聞いてみました。
「インフラエンジニア」や「SIer」と検索するとよく遭遇する、「ブラック」というワード。ここに隠れている「ホントのところ」を徹底解剖します。
すると、意外な真実が見えてきました。
<目次>
1.オープニング
2.「インフラエンジニアはブラック」は過去の話?/a>
3.データで見る、現代インフラエンジニアのリアルな働き方
4.意外?インフラエンジニアも「リモートワーク8割」が当たり前に
5.働きやすい、でも「ぬるま湯」じゃない。会社と個人の新しい関係
6.クロージング
1.オープニング
寺田:言葉は有名でも、何かと知らないことが多いインフラエンジニアの世界。キャリアや将来性、魅力など、ついつい隠れがちな「本当のところ」を、業界のプロであるエーピーコミュニケーションズの永江さん、小山さんと共にインフラエンジニアのキャリアを徹底解剖していきます。
永江:同じくMCを務めます、エーピーコミュニケーションズの永江です。取締役副社長をしております。どうぞよろしくお願いいたします。
小山:同じくMCを務めます、エーピーコミュニケーションズの小山です。採用責任者をしています。よろしくお願いいたします。
寺田:そして、同じくMCを務めます、ベンチャー女優の寺田有希です。さてさて、もう6回目となりました。そろそろポッドキャストに慣れてきましたか?
永江:そうですね、慣れてきたんじゃないかなと思っています。テーマによっては、話しやすいこともあれば、もしかしたら言葉に詰まることもあるかもしれませんが、だいぶ慣れてきたかなと思います。
寺田:小山さんどうですか?未だ緊張はせずですか?
小山:はい。緊張はしないんですけど、内容によっては若干空気になる時があるなと思ったりもします(笑)。個人的には、専門的な知識をもっと磨く必要があるなと反省しながら、この回を迎えています。
寺田:とんでもないです。これからキャリアの話をもっと深く語っていくと思うので、小山さんの知識がすごく重要になります。逆に、私はお二人のキャリアと専門知識のコントラストが素晴らしいなと思っています。
小山:そう言っていただけて安心しました。良かったです。
寺田:本日もよろしくお願いいたします。
さて、本日のテーマは「インフラエンジニアがブラックって本当?」です。「インフラエンジニア」とウェブ検索すると、正直「ブラック」という言葉とよく遭遇しますよね。この噂は果たして本当なのでしょうか?本日は業界のプロであるお二人にずばりお答えいただきたいと思います。
2.「インフラエンジニアはブラック」は過去の話?
寺田:今回のテーマは「インフラエンジニアがブラックって本当?」ですが、永江さん、ぶっちゃけ…どうですか?
永江:昔はどうだったか、という話はありますが、今はそうではありません。
あくまでエーピーコミュニケーションズでの話で、会社や仕事のプロジェクトによってはそういった状況もあるかもしれませんが、今、多くの会社が良い意味で変わってきていると思います。20年ぐらい前に比べると、だいぶ変わったと感じますね。
寺田:それで言うと、以前はブラックだったというのは本当ということですかね?
永江:はい、当時は「ブラック」という言葉はありませんでしたが、長時間労働はIT業界全般に共通していました。私が若い頃は、本当にそういう時代でした。
寺田:それは、いわゆる「オンプレ」と呼ばれる、データベースを物理的に置いていた時代に当たりますか?
永江:オンプレの時代と重なりますし、物理的な作業が多いため、労働時間に影響があったのは事実です。しかし、それ以上に日本社会全体の労働観の影響が大きかったと考えています。
寺田:とにかく時間があるだけ働け、といった風潮でしたよね。
永江:そうですね。バブルの頃ほどひどくはなかったと思いますが、それこそ昔はCMで「24時間戦えますか?」というフレーズが普通に流れていました。そんな大昔の価値観が社会の中にありましたよね。
寺田:今、あのCMが流れたらどうなってしまうんでしょうね。
永江:流せないですよね。
小山:永江さんや私ぐらいの世代だと、まだ「半ドン」という言葉を知っていると思うのですが、土曜日も普通に出勤でした。週休二日制そのものがありませんでした。
寺田:「半ドン」って何ですか?
小山:土曜日は午前中だけ仕事をして、午後は休みといった働き方です。学校もそうでした。土曜日は午前中だけ授業を受けて、午後からは部活とか。多分、私ぐらいまでの世代は知っていると思うのですが、30代になると、すでに完全週休二日になっていた時代なので、分からないという人が出てくるんでしょうね。
寺田:確かに私も小学生の頃、土曜日に学校に行っていました。そう考えると、インフラエンジニアやIT業界がブラックだったというよりは、社会全体がブラックだったからそのように言われていただけで、この分野特有の問題ではないのですね。
永江:どれくらい昔の話をするかによって、話は大きく変わってくると思いますけど、大企業で週休二日制が始まったのが80年代後半ぐらいで、1992年から国家公務員が完全週休二日制になったんですよね。
30数年前から日本で一般的になったという、それぐらいの歴史なんです。その後、2000年代にかけて広く定着していったという流れですね。昔といえば昔ですけど、大昔からそうだったかというと、そうではありません。
寺田:時代も変化してますからね。では、どうして未だにブラックと思われているかというと、そのイメージがこびりついてしまっているという感じなんですかね?
永江:もしかしたらそうかもしれないですね。
あとは、企業によって差があると思うので、きちんとコントロールが効いていない企業では、そのような状況があるのかもしれないです。
寺田:でも、それはどの分野でも同じですよね。
永江:そうですね。
3.データで見る、現代インフラエンジニアのリアルな働き方
寺田:現在はどのような働き方が主流なのでしょうか?
永江:まず残業時間についてお話しします。これはエーピーコミュニケーションズの事例になりますが、2024年の平均残業時間は「19.32時間」でした。例えば月20日働くと考えると、1日あたり平均1時間弱程度ですね。
もちろん、これより少ない人もいれば多い人もいますが、全社平均にするとそのくらいになります。
寺田:かなり少ない気がしていますが、どうですか?
永江:そうですね。平均的か、それともやや少ないか、といったところでしょうか。しかも、当社の勤務時間は1日7.5時間なんです。
寺田:8時間じゃないんですね。
永江:そうなんです。
月間標準労働時間でみると、当社は1日7.5時間なので、月20日間の勤務で計算すると150時間です。法律上は8時間と定めても問題ありませんので、多くの企業はこちらを採用していて月間労働時間は160時間です。
当社の場合、月間標準労働時間の150時間に約20時間の平均残業時間を足すと、月の総労働時間は約170時間になります。一方、月間標準労働時間が160時間の会社だと、仮に10時間の残業をすると、月の総労働時間は170時間になります。
つまり、総労働時間で見ると、当社の月20時間の残業は、他社で月10時間残業するのとほぼ同じということになります。
一般的な企業(1日8時間勤務)の場合
月間標準労働時間:8時間 × 20日 = 160時間
仮に残業が10時間だと、総労働時間は170時間
エーピーコミュニケーションズ(1日7.5時間勤務)の場合
月間標準労働時間:7.5時間 × 20日 = 150時間
昨年の平均残業時間19.32時間を足すと、総労働時間は約170時間
寺田:これ、かなり重要なポイントですね。
永江:そうですね、実はその点があまり知られないまま、語られることが多いんです。
寺田:残業時間だけで見ると、そのデータしか出てこないですもんね。
永江:そう考えると、エーピーコミュニケーションズは比較的少ない部類に入るのではないかと思います。
小山:「総労働時間」で見るか、「残業時間」で見るかという違いですね。
ただ、一般の人はそこまで見ないと思います。メーカーなど伝統的な会社だと、標準労働時間が「7時間45分」「7時間半」という場合もありますが、多くの会社は8時間勤務なので、それが普通だと思っている方がほとんどだと思います。
寺田:正直、私も「1日8時間勤務」が当たり前だと思っていました。残業時間が減った要因は何なのでしょうか?
永江:減少傾向の理由の一つには、技術的な側面もあります。クラウドの登場によって業界全体で業務が効率化されましたが、改めてどういう時代だったのかを調べてみると…「働き方改革」という言葉が盛んに言われていた時期と重なります。
法律化されていったのは2018年頃だったと思いますが、世間では、働き方について大きな関心が寄せられるようになっていきました。
これはエーピーコミュニケーションズだけで変わるわけではなく、業界全体の取引先や関係会社なども含め、全体で協力して労働時間を減らしていかないとなかなか難しい話なんです。ですから、当時と比べると、業界全体としても労働時間が減少しているはずです。
4. 意外?インフラエンジニアも「リモートワーク8割」が当たり前に
寺田:時代と共に、この業界もどんどんクリーンになっているということですね。具体的な働き方で言うと、エーピーコミュニケーションズさんではどのような働き方を推奨されているのでしょうか?
永江:これも社会の大きな出来事ですが、2020年に新型コロナウイルスが流行し始めました。そこから、現在に至るまでリモートワークが中心です。全く出社しないわけではなく、週に1回・2回ほど出社するケースもありますが、ほとんどがリモートワークという社員の割合が8割を占めています。
あとは半分ぐらい出社する社員が1割、プロジェクトや業務の都合で毎日出社する社員が1割です。2020年以降、急激に変わりました。
寺田:インフラエンジニアでもリモートワークが可能なのですね。あまりそんなイメージはありませんでした。
永江:ネットワークの物理的な作業があるときは、出社して対応することになりますが、リモートでも可能な業務は結構多いんです。
寺田:小山さん、こんなにもリモートワークが普及しているのですね。8割というのはかなり多いように感じますが…。
小山:世間のトレンドでは、一部の大企業や有名な会社が「出社回帰」を打ち出し、原則週5日出社を義務付けるといった話題が多く聞かれます。私の周りでも、SIerや、営業、カスタマーサクセスといった職種では出社が必須とよく耳にしますね。そういった中で、この割合でリモートワークを維持できているのはすごいことだと思いますし、働きやすさという点でも魅力の一つだと感じますね。
寺田:働き方とかキャリアを選択する上で、リモートワークが可能かどうかは、今や大きな判断基準だと思います。そう考えると、リモートワークを希望する方にとっても、インフラエンジニアというキャリアが選択肢に入ってくることになりますね。
小山:そうですね。新卒の方々にも、そう考えてもらえると嬉しいですね。
一方で、逆説的なデータも一つあります。「新卒の約3割が3年以内に退職する」という話は以前から言われていますが、働き方改革が進み、労働時間が減ったにもかかわらず、「3年で3割が退職」という傾向は、実はあまり変わっていないんです。
一見すると「ホワイトな業界」になってきているのかもしれませんが、少しグレーな側面もある、といったところでしょうか。
5. 働きやすい、でも「ぬるま湯」じゃない。会社と個人の新しい関係
寺田:最後に、これからの働き方についてです。エーピーコミュニケーションズが目指す働き方はどのようなものになりますか?
永江:働き方の柔軟性は、働く人の可能性を引き出しやすいと考えています。
どういうことかと言うと、人生を長く見据えると、様々なライフステージがあると思うんです。例えば、小さなお子様が成長していくタイミングであったり、あるいは、親が年を重ねて体調を崩し、介護の問題などで大変になる時であったり。あとは、自分自身が病気などを抱えた時に、仕事も大事だが、家庭やプライベートとうまく両立させていかなければならないといった状況において、働く時間と場所の柔軟性が高い方が、様々な状況に対応できる人の割合が増える、と思っています。
能力も意欲もある人が、環境が対応できずにその能力や意欲を活かせない、という状況を防ぐことができると考えています。IT業界は他の業界よりも柔軟な対応がしやすいはずだと思っていますし、私たちは、そういった人々のポテンシャルを十分に引き出せるような環境づくりを推進していきたいと考えています。
寺田:素晴らしいですね。会社としても柔軟性を考慮したいということですね。
永江:一方で、必ず付け加えていることがあります。それは「ぬるま湯のような職場を作るつもりはない」ということです。「楽そうだからこの会社で働こう」という考え方は、少し違うと思っています。
成果を出す意欲があり学習して成長していこうとする人が、何らかの事情でその機会を持てずにいるのであれば、我々がそれをきちんと作っていくということです。経営者として、その両方を同時に語っていく必要があると考えています。
寺田:もし甘い考えを持っている方がいらっしゃれば、ぜひ前回の話を聞いてみてください。ぬるま湯ではないことがお分かりになるはずです(笑)。
小山:私も身が引き締まる思いで、永江さんの話を聞いていました。
これは「定数」と「変数」の関係に似ています。定数の部分、つまり本人の責任では変えられない制度面やハード面を整備するのは会社側の役割です。本人がどうしようもできない部分は会社が整備しつつ、残りの変数の部分は、個人の領域として自分で変えていく必要があります。そのために会社をうまく活用して、自ら成長していく姿勢を持つ人が活躍していくのだろうと思います。
先ほど「ぬるま湯ではない」というのは、言葉を選ばずに言えば、会社を利用するくらいの気持ちで臨んだ方が良いのではないかと考えています。「自分は変わりません、会社が合わせてください」ということではない、ということです。
寺田:それを公言してしまって良いのですね。「会社を利用する」くらいの気持ちで、と。
小山:ええ、今「人的資本経営」という言葉が盛んに言われています。いわゆる昔は会社が主役で、従業員は裏方という考え方でしたが、そうではありません。これからは従業員に「この会社にいたい、残った方がメリットがある」と思ってもらうために、会社が投資をしていかなければならない、という考え方なんです。
人的資本開示と言って、企業はIRでも開示義務があり、それを見て投資家が投資を判断するという形が進んでいます。我々もその視点をもって、きちんと経営を行っていく必要がある時代です。
寺田:今のお二人の言葉から、そういったことをきちんと考えてらっしゃる会社なのだということがひしひしと伝わってきました。
小山:私もそれが入社を決めた理由の一つです。
寺田:そうだったんですね!今後は、そのお話もぜひ!
小山:そうですね。ぜひ語っていきたいです。
6. クロージング
寺田:本日は「インフラエンジニアはブラックって本当?」という、皆さんが気になっているけれどもなかなか聞けないことについて言及してきました。永江さん、いかがでしたか?
永江:この話題は多くの方に興味を持っていただけると思うので、別の機会でもっと深掘りして、お話ししても良いのではないかと思います。
寺田:なるほど。ぜひやりましょう!小山さんはいかがですか?
小山:私個人としては、言葉だけを捉えるのではなく、その裏側、つまりもっと深いところまで見てほしいと思います。「あの会社はブラックだね」という、その「ブラック」という言葉だけに囚われず、中身をきちんと見極める、ということが重要です。
価値観はそれぞれなので、その人にとっては実はそうではないというケースも存在します。残業に関しても、10時間でも長いと感じる方もいれば、それ以上でも問題ない方もいるなど、多様な価値観が存在します。キャリア選択において、表面的な部分だけで判断するのは非常にもったいないことだと感じています。
この番組はSpotify、Apple Podcast、Amazon Musicで配信中です。
ポッドキャストへのフォローとレビューもぜひお願いいたします。
番組へのご質問やリクエストは、専用フォームか、各種SNSから受け付けております。気になることがありましたら、ぜひお寄せください。


