2025/06/25
インフラエンジニアのホントのところ #7|『インフラエンジニアはやめとけ』は本当か?
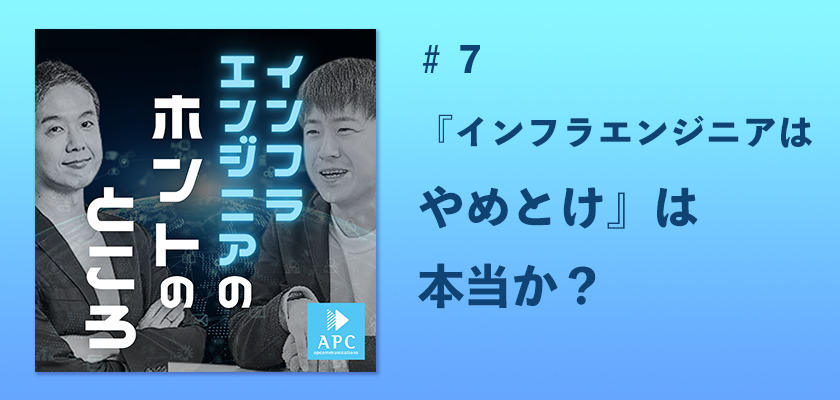
ITインフラって、「なんだか難しそう」「地味で大変そう」と思われがち。
でも実は、社会を支える根幹にある、とてもやりがいのある仕事なんです。
そんなリアルをお届けするPodcast 「インフラエンジニアのホントのところ」。
MCにはベンチャー女優の寺田有希さんを迎え、当社の副社長 永江耕治と採用責任者 小山清和が、現場・経営・採用の視点から語ります。
今回のテーマは「『インフラエンジニアはやめとけ』は本当か?」。
「インフラエンジニア」や「SIer」とウェブ検索すると、『やめとけ』という4文字をよく見かけます。この噂は本当なのでしょうか?
将来性に不安を抱える人も多いのではないか?ということで、どうして「やめとけ」と言われてしまうのかなど、インフラエンジニアキャリアの将来性について、業界のプロである二人がズバリ言語化しました。
<目次>
1.オープニング
2.スピーカーのバックグラウンド紹介
3.「インフラエンジニアはやめとけ」と言われる理由
4.インフラエンジニアの多様なキャリアパスと市場価値
5.インフラエンジニアに向いている人・向いていない人
6. クロージング
1.オープニング
寺田:言葉は有名でも、何かと知らないことが多いインフラエンジニアの世界。キャリアや将来性、魅力など、ついつい隠れがちな「本当のところ」を、業界のプロであるエーピーコミュニケーションズの永江さん、小山さんと共にインフラエンジニアのキャリアを徹底解剖していきます。
永江: MCを務めます、エーピーコミュニケーションズ取締役副社長の永江です。よろしくお願いいたします。
小山: 同じくMCを務めます、エーピーコミュニケーションズで採用責任者をしております小山です。よろしくお願いいたします。
寺田: そして、同じくMCのベンチャー女優、寺田有希です。さて、第7回となりましたが、お二人は最近何かありましたか?
永江: 最近、ネットワークスペシャリストの資格取得をテーマにした『100万円の選択』という映画に、少しだけ出演させていただき、先日撮影をしてきました。
寺田: おめでとうございます!
小山:セリフはあったのですか?
永江: はい、ありました。プロの俳優さんやタレントの方々が出演される中、素人の私がNGを出すわけにはいかないと、かなり緊張して臨みました。
寺田: NGの結果は…?
永江: NGは出さずに、無事終えることができました。ITインフラがテーマの映画なので、とても良い経験になりました。
寺田: 素晴らしい!小山さんは、映画出演に興味はありますか?
小山: 人生経験として一度は出てみたいですね。小学生の時にNHKのインタビューを受けたことくらいしかないので。
寺田: 永江さんは、どのような経緯で映画に出演されることになったのですか?
永江: 私が5年以上続けている『エンジニアBooks』というYouTubeチャンネルがきっかけです。
このチャンネルでは、ITインフラ系の技術書の著者をお招きして本を紹介しているのですが、そこにご出演いただいた左門さんという方がいらっしゃいます。彼はネットワークスペシャリストの資格取得界隈では非常に有名な方で、その左門さんを原作とした映画が制作されることになり、ご本人からお声がけいただきました。
寺田: それはもう、出演オファーですね!素晴らしいです。映画をきっかけにインフラエンジニアの世界が広がっていくのは、とても良いことですね。
永江: はい。他にはないと思うので、業界に興味がある多くの方に見ていただけると嬉しいです。
寺田: 映画の公開、楽しみにしています。
小山: 社員一同、楽しみにしています。
永江: 『X』で『100万円の選択』の公式アカウントがありますので、ぜひフォローして最新情報をチェックしてください。
2.スピーカーのバックグラウンド紹介
寺田: それでは、本日のテーマに移りましょう。今回のテーマは「インフラエンジニアはやめとけって本当?」です。Webで「インフラエンジニア」と検索すると、よく「やめとけ」という4文字を目にします。
これは、この職種の将来性に不安を感じる人が多いことの表れかもしれません。そこで本日は、この噂が本当なのか、なぜそう言われるのかを、業界のプロであるお二人に解き明かしていただきます。
その前に、お二人がいかにインフラエンジニアキャリアのプロであるかをご紹介させてください。エーピーコミュニケーションズは、ITインフラをメイン事業とするプロ集団ですよね?
永江: 従業員約500名という規模で、ITインフラを主軸にしている企業は珍しいと思います。ソフトウェア開発をメインにインフラも手掛ける会社は多いですが、弊社のようにITインフラ事業が中心の会社は限られてきます。
寺田: 日本でも有数の存在ということですね。
永江:この分野ではそう言えると思います。
創業は1995年、今年で約30周年を迎えられる歴史ある企業です。創業当初はネットワークの保守から始まり、サーバー、仮想化、クラウド、そして現在はAI基盤へと事業領域を広げてきました。
寺田: お二人の業界歴はどれくらいですか?
永江: 私はITインフラの分野で23年になります。新卒で入った会社でWebサイト制作を6年経験した後、エーピーコミュニケーションズにネットワークエンジニアとして入社しました。
小山: 私はIT業界全体で10数年です。インフラに特化していた期間は3年ほどですが、業界の変遷は常に見てきましたので、年数以上に多くの情報に触れてきました。現在は採用責任者として、新卒・中途採用を担当しています。
寺田: エンジニア出身の経営者である永江さんと、採用のプロである小山さん。異なる視点から深く掘り下げていきましょう。
3. 「インフラエンジニアはやめとけ」と言われる理由
寺田: それでは本題です。「インフラエンジニアはやめとけ」という噂は本当なのでしょうか?
永江: もちろん、そんなことはありません。ITインフラエンジニアは非常に魅力的な職種です。まず、「インフラ」という名の通り、技術に汎用性があり、安定しているという側面があります。その一方で、常に新しい技術が生まれ、それらを学び続ける面白さも兼ね備えています。安定と変化、両方の魅力がある良い業界だと考えています。
寺田: 「安定」と聞くと、変化がなくて退屈なイメージを持つ人もいるかもしれませんが、実際は新しいことにも挑戦できるのですね。
永江: 「やめとけ」という意見は、おそらく業界の一部分だけを切り取ったものだと思います。インフラの業務は多岐にわたり、中には「オペレーション」と呼ばれる定型的な業務も存在します。
年々減ってきてはいますがゼロではありませんので、そこに長く携わっている人は、あまり技術の発展が見込めないと感じ、「別のキャリアを追求したほうがよいのではないか?」と言われるのかもしれません。その点を大きく取り上げると、「インフラエンジニアはやめとけ」という意見が出てくる可能性はあるかもしれません。
寺田: 「オペレーション」とは、具体的にどのような業務ですか?
永江: 例えば、システムの「監視」業務です。24時間365日、モニターでシステムの状況を確認し、異常があれば担当部署に報告(エスカレーション)する役割です。自ら技術的な対応をするというよりは、まさに運用・監視を担う仕事ですね。
寺田:以前の回でも、業務が多岐にわたるというお話がありましたよね。業務が多岐にわたるからこそ、そういったオペレーション業務も中には含まれるということですね。
永江:はい、中には存在します。
小山: 採用の現場にいると、「やめとけ」という言葉はインフラに限らず、どの業界でも耳にします。
永江さんがおっしゃる通り、一部分だけを切り取って評価したり、個人の価値観と合わなかったりする場合に、そうした意見が出やすいのだと思います。リモートワークの有無や働き方一つとっても、人によって価値観は様々です。
もちろん、総合的に見てやめておいた方が良いというケースもあるかもしれませんが、一部分だけを見て、全てが「ブラックだ」「やばい」と決めつけるのではなく、多角的に業界を見て判断することが大切だと思います。
キャリア相談で「この会社は辞めた方がいいですか?」「この業界はどうですかね?」といった質問を受けることがありますが、まずはその方の価値観と、業界を多角的に見ることが大切だと考えています。
寺田:業務が多岐にわたること、働き方が多様であること、そして時代の変化といった要素が、どうしても部分的に切り取られ過ぎていると感じます。それはどの業界でも同じかもしれませんね。
小山:BtoBであるインフラ業界は、普段の生活で目に触れにくいため、誤解されやすいと思います。だからこそ、私たち自身がもっと情報発信をしていく必要があると感じています。
永江: 「単純作業の繰り返し」「24時間365日のシフト勤務」といったイメージが強いのかもしれません。事実として、そうした業務を中心に行っている会社も存在します。エーピーコミュニケーションズの設立当初はそうした業務の割合が高かったのですが、自動化技術の進歩により、現在では監視業務のような定型業務の割合は全体の2%前後まで減少しました。
寺田:かなり少ないですね。
永江:企業によっては0%のところもあります。このように企業ごとに割合は大きく異なるため、部分的に切り取れば間違ってはいない、という状況が生まれているのだと思います。
4. インフラエンジニアの多様なキャリアパスと市場価値
寺田: では、現代のインフラエンジニアは、どのようなキャリアプランを描けるのでしょうか?
永江: 私たちの会社でいうと、設計・構築はもちろん、そこからセキュリティ分野へ進む道もあります。
現在では、ネットワークだけを扱う業務は本当に少なくなってきており、ネットワーク技術と並行してクラウド技術も習得していく必要があります。
また、私たちはネットワークの自動化を一つの得意分野としていますから、そういった道もありますし、ネットワークの経験があまりなくても、クラウドエンジニアとして活躍するキャリアパスもあります。
現在では、インフラエンジニアでありながら、やはりコードが書ける方が良いとされています。先ほど述べた自動化や、さらに効率化を図るためには、プログラミングスキルが役立つからです。このように、インフラエンジニアの業務範囲は徐々に広がっています。
寺田: 前回は、AI技術の発展にも関わっているという話もありました。
永江: 私たちは、AIの基盤となる「データ基盤」を構築する支援も行っています。Databricksという世界的な企業の技術を活用し、AIが利用する「データの入れ物」を整備する仕事です。これもAI時代におけるインフラの新しい形であり、今後ますます需要が増えると考えています。
寺田:時代の進化で、本当に幅が広がっていますね。 採用の観点から見て、キャリアの可能性はいかがですか?
小山: インフラエンジニアに対するニーズは確実に高まっています。特に中途採用マーケットでは、人材獲得競争が激化していると感じますね。
また、新卒採用の領域でも大きな変化があります。今の若い世代は、高校生の頃からプログラミングに触れているんですよね。さらにインフラもコードで管理する時代になり、Pythonのような開発言語が書ければ、インフラの世界でも活躍できる道が開かれました。
ですから、「コードが書けるのなら、開発だけじゃなくインフラの道もあるよ」と提示できるようになった。これは、学生にとってはキャリアの選択肢が広がり、私たち採用側にとっても人材獲得の間口が広がるという、大きな変化です。
以前は専門学校でインフラやネットワークを学んだ学生が主な対象でしたが、今ではそうした学校に行っていなくてもコードが書ける人材も対象になり得る、ということです。
永江: ネットワーク分野は、これまでコードとは縁遠い領域でした。しかし、デジタル化が進むと、あらゆる操作がコードで完結できるようになり、学ぶべき新しい技術が次々と出てきています。プログラミングやコードと無縁ではいられなくなります。
ですから、以前はインフラエンジニアのキャリアは限定的な部分がありましたが、今は新しい技術をどんどん吸収できる、むしろ学んでいかなければならない状況です。これはキャリアの発展という点で、非常にポジティブな状況だと言えます。
寺田:小山さんのお話では、市場価値も高まっているんですよね?
小山: ただ、業界全体がこの変化に気づいているわけではありません。中には当事者自身がその変化に気づいていないケースもあります。
今、まさに大きなうねりが起き始めている段階です。これから業界全体に浸透していくのだと思いますが、それはもう少し先のことではないでしょうか。チャンスに気づいて行動している人はすでにいますが、皆が気づき始めると競争が激しくなるでしょう。
寺田: ある意味、今が「狙い目」とも言えますね。
小山: はい。DXやAIといった成長分野には、必ずインフラが必要です。成長市場であることはほぼ間違いないですし、人やお金も集まってくる。もちろん競争はありますが、良い要素の方が多いのではないでしょうか。
5. インフラエンジニアに向いている人・向いていない人
寺田: 最後に、「こういう人におすすめ」「こういう人には向いていない」という点を明確にしていただけますか。
永江: インフラエンジニアはチームで動く仕事です。一人でコードを書くだけでおしまいではなく、様々な部署や担当者と連携するため、技術力だけでなくコミュニケーション力を磨きたい、やり取りしながら仕事を進めたい方には非常に向いています。
小山: 基本的には、目の前のことにコツコツと向き合い、安定運用を非常に重視するという資質は当然必要です。しかし、成長産業に関わっていく人材像は変化してきており、より上流工程、例えばDXのような経営や事業に紐づく大きなプロジェクトに関わる機会が増えています。
そういった場においては、関係者と向き合えるコミュニケーション能力が求められます。業界や市場を深く理解し、技術を「わかる人」に伝えるだけでなく、「わからない人」に対しても「それを導入すれば、確かにメリットがある」と納得させられる説明能力も必要です。
そういった能力を磨いていける人は、今後非常に求められ、ダイナミックに仕事ができる人材になるのではないでしょうか。
寺田:インフラエンジニアは技術のイメージが強いので、「技術力を高めれば良い」と考えがちな職種かと思っていましたが、それだけではないのですね。
小山:エンジニアが使うツールも、この10年で大きく進化しました。GitHubのようなバージョン管理ツール、Slackのようなコミュニケーションツールなど、チームで何かをすることを前提としたツールが多いと感じます。
昔は技術のトップがいて、その下に多くの人が集まるという構図でしたが、今はどちらかというと一人のスペシャリストではなく、優れたチームで仕事を進めていくという流れが強まっています。インフラ業界も、ちょうどそうした変化のタイミングに来ているのではないでしょうか。
寺田:変化のタイミングなのですね。では逆に、「お勧めできない」という人も言語化していただきたいのですが、いかがでしょうか?
永江:インフラは全てのシステムの基礎となる部分です。そのため、システムのトラブルを極力なくすことが求められます。つまり、一定レベル以上の周到さや確実性が求められる分野です。そうした業務を我慢強く、粘り強く行うことが非常に苦手だという方は、少し向いていないかもしれません。
小山:表現が難しいのですが、あまりにも即効性のある結果を求める方、例えば「何かをしたらすぐに世の中が変わる」といった影響を期待する方には、あまり向いていないかもしれません。いわゆるサービス開発とはやや異なり、時間がかかる領域だと考えています。じっくりと腰を据えて取り組み、花開く性質の仕事です。
ですから、「3ヶ月で成果が出ますか?」といった短期的な結果を求める方には、なかなか難しいかもしれません。まずはじっくりと着実に足元を固め、一定の時間がかかることに対しても向き合い続けられる人が向いているでしょう。
寺田: 働き方の面ではいかがですか?
永江:働き方については、担当するクライアントや業務内容によって勤務形態が変わるので、一部で夜間作業が発生することもあります。そのため、どうしても夜間作業ができないという方にとっては、その業務の配属先が合わない可能性はあります。
一方で、安定的なシステム運用が実現できている場合、逆に不規則な勤務が少なくなります。これも企業やシステムの状況によって大きく異なりますが、比較的安定的に働けている方もたくさんいらっしゃると思います。
寺田:そう考えると、例えば働くママや子育て中の方にとって、全く不向きな職種ではないのですね。
永江:はい。例えば現在、当社のオフィスは東京にしかありませんが、約80名近くの従業員が、北海道から沖縄まで、関東圏以外の地域に住んでいます。
ITインフラエンジニアはそういう働き方ができないのではないかというのは、昔のイメージとしてありましたが、ITインフラメインのエンジニアは基本的にリモートワークです。働き方、特に場所の自由度はかなり高いと思います。
6. クロージング
寺田: 私たちが抱いていたインフラエンジニアのイメージと、現在の姿には良い意味でギャップがあることがよく分かりました。「やめとけ」と言われる背景について、お二人はどうお考えですか?
永江: 昔のイメージを引きずっている方が、それなりにいるのだと思います。業界は大きく変化しているので、その全体像を広く捉えていただけると、より正確な理解につながると感じました。
小山: 「やめとけなんて、言わないでほしい」と改めて思いました。ただ、キャリアのロールモデルが分かりにくいなど、情報が不足しているのも事実です。この番組も含め、業界全体で積極的に情報発信を行い、「やめとけ」という声を一つでも減らしていきたいです。
寺田: このポッドキャストでその一助を担っていきましょう。本日はありがとうございました。
この番組はSpotify、Apple Podcast、Amazon Musicで配信中です。
ポッドキャストへのフォローとレビューもぜひお願いいたします。
番組へのご質問やリクエストは、専用フォームか、各種SNSから受け付けております。気になることがありましたら、ぜひお寄せください。


