2025/07/02
インフラエンジニアのホントのところ #8|インフラエンジニアに求められる素質って?
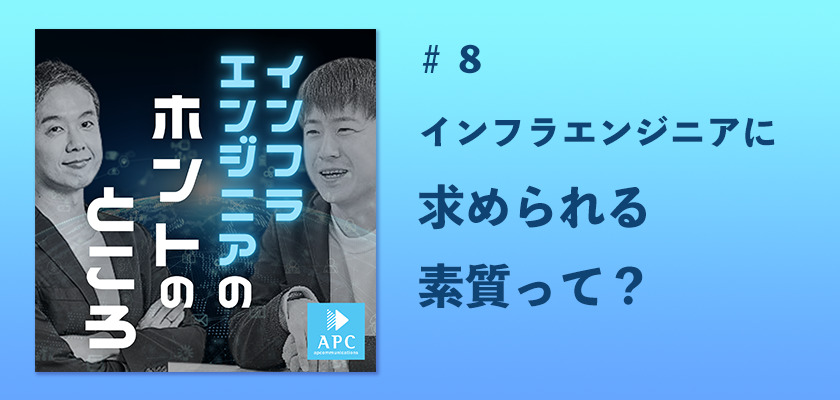
ITインフラって、「なんだか難しそう」「地味で大変そう」と思われがち。
でも実は、社会を支える根幹にある、とてもやりがいのある仕事なんです。
そんなリアルをお届けするPodcast 「インフラエンジニアのホントのところ」。
MCにはベンチャー女優の寺田有希さんを迎え、当社の副社長 永江耕治と採用責任者 小山清和が、現場・経営・採用の視点から語ります。
今回のテーマは「インフラエンジニアに求められる素質とは」。
必要な技術や流行りなど、とにかく変化と進化が激しく、業務内容も多岐に渡るという、『インフラエンジニア』。
一体どんな人が、インフラエンジニアに向いているのでしょうか?
求められる「素質」について徹底解剖し、「向いている人」と「向いていない人」を明らかにしていきたいと思います。
<目次>
1.オープニング
2.ITインフラ業界の現状と今後の変化
3.採用目線で語る、インフラエンジニアに必要な素質
4.エンジニア目線で語る、インフラエンジニアに必要な素質
5.インフラエンジニアに向いている人・いない人
6.クロージング
1.オープニング
寺田:言葉は有名でも、何かと知らないことが多いインフラエンジニアの世界。キャリアや将来性、魅力など、ついつい隠れがちな「本当のところ」を、業界のプロであるエーピーコミュニケーションズの永江さん、小山さんと共にインフラエンジニアのキャリアを徹底解剖していきます。
永江:同じくMCを務めます、エーピーコミュニケーションズの永江です。取締役副社長をしております。どうぞよろしくお願いいたします。
小山:同じくMCを務めます、エーピーコミュニケーションズの小山です。採用責任者をしています。よろしくお願いいたします。
寺田:そして、同じくMCを務めます、ベンチャー女優の寺田有希です。さて、前回は永江さんの映画初出演のお話を伺いましたが、小山さんは最近何かございましたか?
小山: 昨日、丸の内南口の三菱一号館美術館で開催されている「ルノワール×セザンヌ ―モダンを拓いた2人の巨匠」という展覧会に行ってきました。
もう完全に感性が磨かれたというか、普段はスマートフォンばかり見てしまいますから、いい意味で「デジタルデトックス」になりました。もちろん、見たことのある絵も展示されていましたが、やはり実物が目の前にあると違います。
私は、絵画の背景にある作者の心情や、描かれた当時の時代背景を掘り下げて見るのが好きなんですよね。評論家でもない私が言うのも何ですが、時代や心境によって使う色や絵柄が変わっていくのが面白いんです。
ルノワールやセザンヌ、そして後に続くピカソといった巨匠たちに影響を与えた人々の作品も展示されていました。実際にピカソの絵なども見ていたら、1時間少々の時間でしたが、「ルノワールやセザンヌの作品をもっと調べてみようかな」という気持ちになったんです。
私にしては非常に珍しいことで、普段なら「走ってました」という話が出てくるので。
寺田: 普段は、走っていらっしゃるんですね。
小山: はい。その前日は、皇居を5周、合計25kmを2時間10分くらいで走っていました。練習の一環として、少しゆっくりめに走ってはいるのですが。
寺田: 25kmを2時間10分ですか!マラソンだと、サブ4(4時間切り)くらいでしょうか?
小山: ベストタイムは3時間11秒なので、ほぼサブ3(3時間切り)に近い記録は持っています。
寺田: 大変失礼いたしました。サブ4などと言ってしまい。サブ3ランナーでいらっしゃるんですね。
小山: ですから、私のような人間が美術館に行ったと言うと、「ええ!?」と驚かれるわけです。
2. ITインフラ業界の現状と今後の変化
寺田: 本日のテーマは「インフラエンジニアに求められる素質とは」です。
以前の配信では、インフラエンジニアがどのような仕事をしているのかを徹底解剖しました。まだお聞きになっていないという方は、ぜひそちらも合わせてお聞きください。その回で、必要な技術やトレンドなど、変化と進化が激しく、業務内容も多岐にわたるというインフラエンジニアの実態が明らかになりました。
では、そんなインフラエンジニアに向いているのは、どのような人なのでしょうか。本日は「求められる素質」について徹底解剖していきたいと思います。
まず、前提として「今はどのような時代なのか」「ITインフラ業界はどのような状況なのか」をお伝えした方が分かりやすいかと思います。永江さん、現在のITインフラ業界は、どのような時代と言えるでしょうか?
永江: 私がこの業界に身を置いて20年以上になりますが、やはり20数年前と今とでは、全く状況が変わってきていますね。特にクラウド技術が浸透し始めた頃から、大きく変化しました。
ネットワークの世界などでもデジタル化が進み、デジタル化されるということは、コードやプログラムで扱えるようになるということです。そこから「自動化」が大きく進展しました。プログラムを使ってコードを書き、システムを自動で構築したり拡張したりすることが可能になったのが、まず一つの大きな変化です。
そして最近はさらにAI技術の導入が進んでおり、これによりさらなる変化が次々と起こっていくかなと思います。
寺田: さらなる変化というと、具体的にはどのようなことでしょうか?
永江: これまでは人がシステムコードを書いて自動化していましたが、今後はAIが自動で状況を判断してシステムに変更を加えたり、異常箇所を人を介さずにAI自ら検知・対応したりする部分が、さらに増えていくと思います。
寺田: 人力で行うというよりは、インフラの整備にもAI技術が導入されていくのですね。それによって業務内容も、求められる技術も変化していくということでしょうか。
永江: そうですね。人がプログラムを設計し記述していた領域に、AIによる状況判断や異常検知といった機能が加わり、その領域がどんどん広がっていく。おそらく、そういった世界になっていくのだろうと思います。
寺田: なるほど。では、この時代の変化を踏まえた上で、求められる素質についてお二人にお聞きします。
まず永江さんには、エンジニアとして20数年この業界にいらっしゃるエンジニアとしての目線で。そして小山さんには、採用責任者としての目線でお聞きしたいと思います。
3. 採用目線で語る、インフラエンジニアに必要な素質
寺田:まずは小山さんにお聞きします。採用責任者目線で「求められる素質」とは何でしょうか?
小山: そうですね、いくつかありますが、「素質」という点でお話しするならば、まずは「きっちりとやりきる力」です。これは少しスキル寄りの話かもしれませんが、非常に重要です。仕事のクオリティに良し悪しはありますが、まずは与えられたタスクを最後までやりきる。この「やり切れる」という素質は、非常に優れていると思います。
これは業界による差があると思います。例えばスタートアップやベンチャー企業では、事業を創出しなければ会社が存続できないため、スピード感が重視され、まずはやってみて、失敗したら次へ、といったドラスティックな変化が求められます。
しかし、我々の業界はそうではなく、むしろ中途半端にすることが一番良くありません。きちんと完遂させることが求められます。むしろ、やりきってからが本番、という仕事でもありますので。そういったことにきちんと向き合えるかどうかが重要です。新しいことが好きだという気持ちも大事ですが、それに取り組む前に、まず目の前のことをしっかりとやりきる。この素質は非常に大切だと感じますね。
逆に、すぐに大きなことを成し遂げたい、失敗してもいいからまずやってみたい、という短期的な視点が強すぎると、この業界では少し危険な場合があります。もちろん、失敗を恐れないチャレンジ精神も大事ですが、それだけではうまくいかないと思います。
寺田: チャレンジ精神が旺盛すぎると、仕事にそれを求めすぎた場合に、少しミスマッチが起きるということでしょうか。
小山: そうですね。「成果を残したい」「爪痕を残したい」という短期的な視点が強すぎると、合わない部分があるかもしれません。インフラの仕事は規模が非常に大きいため、個人の力だけでは変えられない定数的な部分が多い。つまり、個人の変数がそこまで大きく影響しない職種でもあると思います。
寺田: なるほど。
寺田: そう考えると、「個人で成果を上げたい」という志向とは少し結びつきにくいかもしれません。
小山:そうですね、それであれば、おそらく違う業界の方が活躍できる可能性は高まるのではないかと思います。もちろん、絶対に活躍できないとは言い切れませんが。
4. エンジニア目線で語る、インフラエンジニアに必要な素質
寺田: 永江さん、エンジニア目線ではいかがですか?
永江: 現場目線で考えると、何よりもまず「ITが好きである」ということが一番必要な素質だと感じます。これは、学校の勉強ができるかどうかよりも重要で、ITが好きで、人から言われなくても自ら情報を取りに行ったり勉強したりする人の方が、圧倒的にエンジニアとしてのスキルの身につき方が速いんです。
これまでの経験から言うと、どんなに勉強が得意な人でも、ITに興味が持てなかったり、好きではなかったりすると、エンジニアとしては伸び悩む傾向にあります。
ですので、そこは非常に大切なポイントになります。
寺田: 一つの技術を磨き続けるというよりは、新しい技術をどんどんキャッチアップして成長していく、というイメージでしょうか。
永江:そうですね。自分で「面白い」「好きだな」と思えることは、大きな才能の一つではないでしょうか。
寺田:他に、チームワークが重要というお話もありましたよね。
永江: はい、コミュニケーション能力やチームの協調性は重要です。インフラの構築はチーム作業であることが多いため、連携できる人の方が成果を出しやすいと感じますね。
寺田: 一人で淡々と作業できる人の方が向いているのかと思っていました。
永江: もちろん、チームの中にそういったタイプの人がいても良いとは思います。しかし、共に働く仲間たちがいる中で、キャリアとして大きな成果を出すという点においては、一人でコツコツ作業するだけでなく、人と連携しながら仕事ができる人の方が、より大きな成果につながりやすいと思います。
寺田: 小山さん、このあたりも納得ですか?
小山: そうですね。チームでの仕事は、規模が大きくなるにつれて本当に「掛け算」になっていくと感じます。掛け合わせる要素がプラス同士であれば良い結果が生まれますが、マイナスがあると駄目です。この場合、マイナス同士を掛けてもプラスにはなりませんから。
技術力だけでは不十分で、チームで連携する力、物事を考える力、そしてコツコツと着実に作業を進める力、それらが掛け算として大きな成果につながるのだと思います。
ですから昔に比べて、掛け合わせる要素が増えたのではないでしょうか。昔は技術力の比重が大きかったと思いますが、今は技術も複雑化し、案件の難易度も上がり、より経営に近い部分と向き合わなければならなくなりました。その結果、掛け算の要素がより強くなり、ある一部分だけでは突破できない状況になってきているのだと思います。
寺田: 変数が大きくなっているんですね。業務が多岐にわたる印象ですが、専門分野ごとに求められる素質は変わるものですか?
永江: これはITインフラエンジニアに限った話ではないと思いますが、根本的な素質としては、ITエンジニア全体で共通して必要な部分があると思います。よく言われるのは、「論理的思考」「協調性」そして「学習意欲」ですね。
これらは必須です。特にインフラエンジニアは、システム障害が起きた時に冷静に状況を判断し、論理的に物事を切り分けていく場面が多くあります。そのため、冷静さと論理的思考力は、特に求められる素質です。
そして、これはエンジニア全般に言えることですが、常に新しいことを学んでいく姿勢や、それを実行する行動力は、広範囲にわたって共通して求められる部分になると思います。
寺田: なるほど。専門分野で違いはあっても、ベースとして求められることがあるんですね。
永江:そうですね。論理的に物事を解決する力が重要になってくる、ということですね。
5. インフラエンジニアに向いている人・いない人
寺田: 最後に、お二方に「どのような人がインフラエンジニアに向いているか」をまとめていただきたいと思います。まず、論理的思考ができる方、でしょうか。
永江: そうですね。そこはベースとして非常に重要です。
寺田: あとは、学習意欲がある方。
永江: 学習意欲が強い人である必要がありますね。
そして、特にインフラに関しては、「縁の下の力持ち」になることが多い。裏方としてシステムを支えることに、やりがいや誇りを持てる方が向いていると思います。
寺田: それは、先ほど小山さんもおっしゃっていたことに通じますね。
小山: はい、そうですね。 それから最近、現場から「こういう人が欲しい」と聞く声は、コミュニケーションに関する能力です。例えば、相手に共感する力。クライアントがなぜその状況に陥ったのか、どう考えているのかを思いやること。また、技術的な話を、難しい話のまま伝えても伝わらないので、相手の視点に立ってどうすれば伝わるかを考える「言語化能力」も重要です。
さらに、物事を抽象的な段階から具体化していく力も求められます。これは、お客様自身が気づいていない課題を特定する、といった課題設定の側面にもつながります。上流工程に行けば行くほど、業務の抽象度は上がっていきますから、そういった「物事を構造化して考える力」が必要になってきていると感じます。
寺田: ありがとうございます。では逆に、向いていない人はいかがでしょうか?
永江: 「継続的に学ぶ」ことが好きではない人、現状の知識だけで業務を進めたいと思っている人は向いていないでしょう。また、先ほどの裏返しになりますが、地道な作業を退屈に感じたり、そこにやりがいを感じられなかったりする場合も、あまり向かないかもしれません。
寺田: 小山さんはいかがですか?
小山: 永江さんがおっしゃったことは、本当にその通りだと思います。我々の業界の特性を理解した上で言うならば、やはり目の前のことにきちんと向き合うことが大切です。何事においても「現状維持は退化」ですから、そういった視点で物事に向き合える方は年齢に関係なく活躍できるのではないでしょうか。
寺田: お話を伺っていて、インフラエンジニアという仕事が、想像していたよりも特殊なわけではないのかもしれない、と思いました。
小山: 職人的なイメージがあるのかもしれないですね。
寺田:「特別な素質がなければいけない」と思ってしまったところがありましたが、いい意味でそうじゃないと思えたことが大きな気づきでした。
小山:こだわることは大事にしつつも、あくまで相手が存在する仕事ですので、自分たちが作りたいものを作るだけでは駄目ですからね。
永江:「インフラ」というと、変わらないものというイメージが強いかもしれませんが、ITインフラである以上、変化する部分もかなりあります。普遍的な技術と、変化し続ける技術、その両方が一定の割合を占めているのが、ITインフラの特殊性かもしれません。
6. クロージング
寺田: 「向いている素質」「そうではない素質」を言語化していただきましたが、いかがでしたか?
永江: こうして言語化してみると、やはり「支える基盤」という目に見えづらい部分に誇りややりがいを持てるかどうかは、その人の価値観や性格によって異なるので、何が正しいというわけではなく、向き不向きが出る分野なのだと改めて思いました。
小山: そうですね。ただ、これはあくまで現時点での話だと考えています。素質は時間の経過と共に変化することもあります。やっていく中で「自分はインフラに向いているかもしれない」と気づくこともあれば、その逆もある。ですから、これを聞いて「自分には素質がない」と結論づけるのではなく、一つの考え方として捉えていただけると嬉しいですね。
寺田: 他の業界と比べて特殊かと言われれば、良い意味でそうではないのだなと強く感じました。ぜひ皆さん、これを参考にしてキャリアを考えてみていただけたらと思います。
この番組はSpotify、Apple Podcast、Amazon Musicで配信中です。
ポッドキャストへのフォローとレビューもぜひお願いいたします。
番組へのご質問やリクエストは、専用フォームか、各種SNSから受け付けております。気になることがありましたら、ぜひお寄せください。


