2025/07/16
インフラエンジニアのホントのところ #10|インフラエンジニアのキャリアパスを考えよう【給料・待遇編】
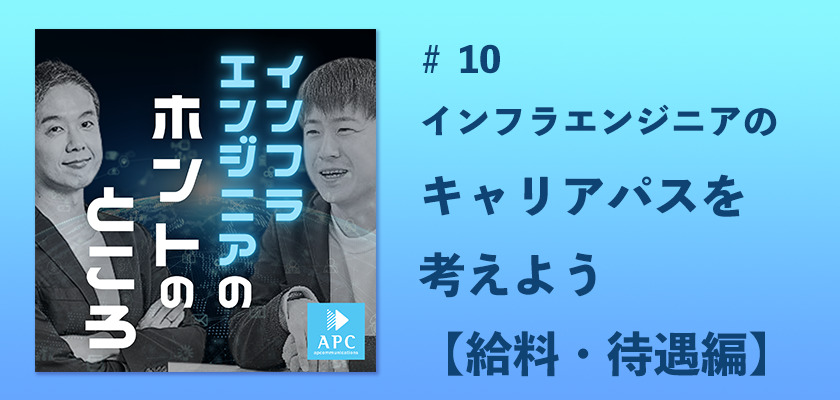
ITインフラって、「なんだか難しそう」「地味で大変そう」と思われがち。
でも実は、社会を支える根幹にある、とてもやりがいのある仕事なんです。
そんなリアルをお届けするPodcast 「インフラエンジニアのホントのところ」。
MCにはベンチャー女優の寺田有希さんを迎え、当社の副社長 永江耕治と採用責任者 小山清和が、現場・経営・採用の視点から語ります。
今回のテーマは「インフラエンジニアのキャリアパスを考えよう【給料・待遇編】」。
キャリアパスを考える上で、給料や待遇面は重要なポイントですよね。業務内容が多岐に渡るインフラエンジニア。
給料アップは目指せるのか?そのためにはどう考え、何をすべきなのか。徹底解剖していきます。
<目次>
1.オープニング
2.インフラエンジニアの給与は昔と比べてどう変わった?
3.給与レンジの拡大と求められるキャリア戦略
4.給与アップの鍵は「成長産業」を選ぶこと
5.自社で給与を上げるには「事業計画」を読む
6.クロージング
1.オープニング
寺田:言葉は有名でも、何かと知らないことが多いインフラエンジニアの世界。キャリアや将来性、魅力など、ついつい隠れがちな「本当のところ」を、業界のプロであるエーピーコミュニケーションズの永江さん、小山さんと共にインフラエンジニアのキャリアを徹底解剖していきます。
永江: エーピーコミュニケーションズの永江です。私は2002年からITインフラ業界に携わっており、もう20年以上の経験があります。最初はエンジニアでしたが、今は経営者をしております。どうぞよろしくお願いいたします。
小山: エーピーコミュニケーションズの小山です。私はIT業界で10年以上、採用を中心に関わってきました。また、7回の転職を通してキャリアを築いてきた人間です。当社では採用責任者をしております。よろしくお願いします。
寺田: MCを務めます、ベンチャー女優の寺田有希です。さてさて、日本はもう夏ですね。
小山: だいぶ暑いですね。梅雨前線はもう完全に太平洋側にあって、日本には存在していない気圧配置になっていますね。
寺田: じゃあ、もう夏ということですね。
永江: 東京近辺では6月で35℃を超えたりもしたので、夏が早いなという感じです。
寺田: お二人は何か夏のご予定はあるんですか?「ここに行こう」とか「これをしよう」と思っていることなど。
小山: 夏だからやる、ということはあまりないんですけど、「富士登山競走」という、日本で最も過酷と言われる山岳レースがありまして。0合目から山頂まで一気に登る過酷な競争があるのですが、それが7月の末に参加する予定です。
寺田: うわぁ!私は5合目から登っただけでも、もうお腹いっぱいという感じでした。
小山: それが普通です。はい。こっちがおかしいんです(笑)。
寺田: 永江さんは何か夏のプランはありますか?
永江: 夏は家族で旅行に行ったりするんですけど、今年は子供が受験生なので、あまり遠出はしないかなという感じです。家の近くで少しゆっくりリフレッシュするぐらいの夏になりそうです。
寺田: それはそれでいいですね。
さて、それでは本日のテーマに移りたいと思います。本日のテーマは「インフラエンジニアのキャリアパスを考えよう?給料編?」です。
先日、番組宛に「インフラのエキスパートになるのか、PMなどに転身することもできるのか、どんなキャリアがありますか?」というリクエストをいただきました。一言でキャリアパスと言っても様々な切り口から考えられるということで、職種編、給料・待遇編、働き方編の3回にわたって、インフラエンジニアのキャリアパスについて考えていきます。
今回は第2回目の「給料・待遇編」です。キャリアパスを考えていく上で、給料面、待遇面は重要なポイントですよね。給料アップを目指していくことはできるのか、そのために何を考えていかなければいけないのか、お二人と共に詳しく見ていきましょう。
2. インフラエンジニアの給与は昔と比べてどう変わった?
寺田: インフラエンジニアはどのくらいの給料を目指せるのか、そのためには何をして、何を知っておくべきなのか徹底解剖していきましょう。
それではまず、小山さんと一緒に現在の市場を見ていきたいと思うのですが、IT業界の採用で10年以上の経歴を持つ小山さん、インフラエンジニアのお給料事情はいかがでしょうか。
小山: 当然、スキルや会社によっても変わってはくるのですが、求人ベースや実際に働いている方たちの現職の給与を聞くと、大体年収400万円台の中盤ぐらいから700万円ぐらいの範囲に収まるのが、一般的なところですね。
スキルが高ければ年収も高くなる傾向がありますし、まだスキルがあまりない方だと若干低くなる傾向はあるかと思いますが、平均的に言うとそういった感じかなと思います。
寺田: これは過去と比べて変化していますか?
小山: していますね。これはあくまで私の経験上なので、そういう人ばかりではないという前提での話ですが、例えばインフラエンジニアになって1、2年目の方で年収200万円台、月給で言うと20万円ちょっとぐらいの人とか、300万円台の人というのは普通にいました。
私が初めてインフラエンジニアの採用に携わった2010年頃だと、やはり300万円台ぐらいが下限で、上が600万円台とか。開発エンジニアよりは若干低かったという印象です。2010年代の中盤ぐらいまでは、そういった条件で応募があり、採用となっていたので、業務量や内容からすると年収が少し低かったかもしれません。ですから、今は非常に上がってきていると言えるんじゃないかなと思います。
寺田: ということは、単純に市場価値も上がっているということとイコールですか?
小山: そうですね。そういう側面はあると思います。
昔に比べると、特にIT業界のサービスが大規模になってきて、その分、安定稼働が大事になってきています。昔はベンチャーやスタートアップが「新しいサービスを作る」ということが多かったのですが、今は新しいものを作るというよりも、いかに安定運用をしていくかというフェーズになっています。プラットフォームも大きくなりましたからね。そうなってくると運用に関わる人を増やしていかないと収益が担保できません。
つまり、その人たちにちゃんと投資をしないと、会社が成り立たないということです。会社側もしっかりとした給与を渡して、残ってもらわないといけないわけです。
我々はクライアントワークとして業務を依頼される側ですが、依頼する側もちゃんとした対価を払わないと、仕事を受けてくれる会社がなくなってしまいます。その結果、給料も上がっていくという形でしょうかね。
3. 給与レンジの拡大と求められるキャリア戦略
寺田: 永江さんは、どうでしょうか?この業界に20年以上いらっしゃると思いますが、体感する変化はありますか?
永江: はい、変化はありますね。昔と比べると、やはり給与水準は上がってきていると感じます。特に2000年代、2010年頃までの時期と今とでは、良い意味で大きく変わってきているかなと思います。
寺田: かなり上がってきていると。
永江: そうですね。それこそ2000年代ぐらいだと、300万円台ぐらいの求人も普通に結構あったと思いますし、550万円ぐらいでも「まあまあ高いな」という感覚があったと記憶しています。
もちろん幅はありますが、今はそのレンジが上の方まで大きく広がっています。それこそ年収1000万円近い、あるいは超えているような求人も出てきました。下限から上限までの幅がだいぶ大きくなっているのが、ここ最近の傾向だと思います。
これは何を意味するかというと、いわゆる「上位層」と言われる人たちが存在するようになってきたということです。例えば、難しい領域で非常に付加価値の高い仕事をしている人もそうですし、昔はそんなにたくさん求人を出すことがなかったいわゆる外資系企業も。もちろん波はありますが、それにしても、昔はそういう上位層の求人はそんなになかったなという感じはしますね。
寺田: そう思うと、小山さんもおっしゃっていた通り、市場価値も給料面も上がっている一方で、レンジが広がる中で自分が下の方にならないように、どうやって上に上がっていくかを考えていかないといけないんですね。
小山: そうですね。流れに任せるというよりは、ある意味、昔よりも「自分の意思を持ってキャリアを築いていかないと難しい時代になってきた」と感じます。市場が盛り上がっているから自分もそれに乗っかれる、という感じでもないな、と。
4. 給与アップの鍵は「成長産業」を選ぶこと
寺田: では実際に小山さん、どうすればこの給与や役職、待遇を上げていくことができるのでしょうか?
小山: ここからお話しするのは、これが正解ということではなく、あくまで一つの要素として捉えていただきたいと思います。
まず前提として、自分が属している分野が「成長産業」かどうかは、かなり重要だと思うんですね。その反対を「斜陽産業」なんて言ったりもしますが、成長産業には、人、モノ、金、情報といったものがものすごく集まってきます。
私もIT業界に長くいますが、成長産業であるIT業界の中でも、特に盛り上がっている分野にいたことがあります。最初はソーシャルゲーム業界。その後、EdTechのような教育関連だったり、SaaS系のベンチャーやスタートアップだったり。そういった盛り上がっている市場を複数見てきましたが、本当にすごい人材が集まってくるんです。例えばコンサルティングファームにいるような方や、日本で誰もが知るような会社にいる人が転職してくる。そして、そこに投資家がすごい額を投資するわけです。設備面で言っても、最新のPCだけでなく、良い周辺機器なども含めて投資されますし、情報もたくさん集まってきます。
やはり、そういったところには人が集まってきて、事業が伸びていきます。なので、当然、そこにいる人自身の市場価値が上がったり、給与が上がる確率も高まったりします。ですから、成長産業に行くというのは、まず外してはいけないポイントだと思います。
逆に、成長していない市場は、市場自体が伸びないので、会社の売上も上がっていきません。給与の原資となる売上や利益が増えないわけですから、思ったように給料が上がらない。いきなり従業員数が減るわけではないので、給与を上げることが難しくなったり、賞与が出なくなったり、ポジションが増えなかったりということも当然あるわけです。
ですから、自分がいる業界が成長しているのかどうかという視点は、絶対に外しちゃいけないポイントだと思います。頑張り続けても報われないとか、思った通りに行かないということが普通にあるので。
寺田: そっか。頑張ったからといって給料が上がるわけではないんですね。
小山: そうですね。やはり、売上や利益が上がるから、それを社員に還元するというのがベースですから。そう考えると、成長している市場であれば、その可能性が非常に高いということです。もちろん全部がうまくいくわけではないですけど。
寺田: こういうことを考えている方は、やはり少ないんですか?
小山: そうですね。そういう形で議論されたり、話をしたりする機会が少ないからかもしれません。
例えば、私が中学生、高校生、大学生だった頃のキャリア教育って、やはり「一社で長く頑張って働いた方がいいよ」という教育を受けてきた世代なんです。それがすり込まれた上で社会に出たら、「あれ、なんか違くない?」と感じる。
特に40代の私ぐらいの世代が、ちょうどその狭間にいるんですよ。「一社で長く頑張りなさい」と言われてキャリアの円熟期に入ろうという時に、「いや、一社で長く働くよりも、自分で変化させていった方がいいよ」と言われる、みたいな。「え、どうすればいいの?」ってなりますよね。
私は転職回数が多いので、「君みたいに転職回数が多い人は…」と言われてきたんですけど、今では逆に「転職回数が少ない人の方が、変化への対応力に不安を感じる」ということが普通にあったりします。
寺田: ええ!?それで不採用もあり得るんですね。
小山: あり得るんですよ。「変化への対応に不安を感じます」とか。これは当社の話ではないのですが、そういう話をよく聞きます。私は「時代が追いついてきたな」と勝手にポジティブに捉えているんですけど(笑)。
寺田: 待遇や給与を上げていくには、まず「市場価値が上がっていく場所を選ぶ」ということが最初に来るんですね。
小山: そうです。以前よりも戦略的に自分のキャリアを考えるということが、非常に大事になっているかなと思います。
自分の得意なことを考えた上で、どの市場でどう戦うべきかを考える。100%その戦略通りにいくことはないとは思いますが、ある程度、軸を持ってキャリアを作っていく必要があります。会社にいれば成長できるとか、成長産業に行ったから成長できるというわけでもありません。会社の成長と個人の成長は別の話です。
寺田:確かにそうですね。
小山:逆に、伸びていない市場でも活躍される方はいらっしゃいますし。あくまで可能性を上げる、待遇を変えていく可能性を高めるという前提であれば、成長産業の方が絶対にいい、ということです。
寺田: そう思うと、インフラエンジニア業界は、市場としていかがですか?
小山: 伸びています。とある統計でも、2027年頃には約8兆円規模の市場になると言われていて、年々右肩上がりで伸びています。
特にインフラの中でも、物理的なハードの市場は少し下がっていますが、私たちがやっているようなクラウド分野や、そのクラウドに関わるソフトウェアの分野はどんどん伸びています。
そこに関わり続ける以上は、少なくともその統計が出ている2027年までは、市場がいきなり急落することはないと思います。この傾向はしばらく続くと見ています。市場が伸びているので、自分たちのキャリアや待遇がまだまだ上がっていく可能性は高い分野なんじゃないかなと思います。もちろん、保証はできませんけれど。
5. 自社で給与を上げるには「事業計画」を読む
寺田: インフラエンジニアが給与面、待遇面を上げていける可能性を秘めていることが分かったところで、永江さん、どうやって上げていけばいいのか?どんな準備をすればいいのかというお話をお聞きしたいです。
永江: 給料の上げ方はいろいろあると思っています。
一つは、業界の中での市場価値を上げる、ということです。例えば、今、旬の技術は何か、これから伸びそうな領域はどこかを見極めて、それを選択していくというのも一つの手です。
業界内で転職をして給与を上げるという方法もあると思いますが、私が今日お話ししたいのは、同じ会社に属しながら考える、という方法です。
これには、会社の事業計画にヒントがあると思っています。多くの会社は、短期的な1年だけでなく、3年後ぐらいの事業計画を持って事業を運営しています。あまり遠すぎると参考になりづらいですが、「数年後に、我が社はこの領域をこうやって伸ばしていこう」という計画があるはずです。
それは何かと言うと、「すでにできている」ことではなく、「まだできていないけど、こうしたい」という目標です。
寺田: なるほど。
永江: なぜなら、そこには良い市場があると考えているし、自分たちが過去に培ってきた資産や強みを考えると、そちらに進むことが会社としての成長につながるだろう、と思っているからです。
まだできていないという前提で考えると、会社としては、そこで活躍してくれる人が増えると嬉しいわけですよね。
寺田: ああー!
永江: そして、その目標は一つだけではなく、いくつかある場合が多いと思います。
その時に、自身がやりたい方向性や「これは向いてそうだな」「得意だな」と思えることと、100%ぴったり重なることはないかもしれませんが、「これだったら重ねやすいな」「重ねると面白そうだな」と思えるものを探す。これは、事業計画を持っている会社の中にいるのであれば可能です。
寺田: 面白い!事業計画を読むんですね。
永江: それは、評価される可能性を高める、大きなヒントになると思います。
寺田: 会社が将来を見据えて、市場を分析した結果が事業計画ですもんね。キャリアを探していく上での指針になりそうですね。例えば、資格を取るというのはどうなんでしょうか。
永江: それもやり方としてはあります。これも同じで、業界の中で求められている資格というのがあるんです。
会社によって少し違ってくるのですが、例えばAWSやAzureといったクラウドベンダーは、資格の取得をすごく推奨しています。
中でもAWSはITインフラの世界で最も有名で、新しい分野で技術を大きく広めたいと考えている企業は「日本のIT業界に自社の資格取得者がたくさんいる」という状況を作りたいと思うことが多いんです。
自分が所属している会社が、まさにその方向性で競争力を高めたいと考えている状況であれば、資格がいわゆる給与Upにつながる確率は上がるんじゃないかなと思います。
資格なら何でもいいというわけではなく、会社ごとに何に力を入れていくかは変わってきますし、トレンドも変化していくので、その辺りを見極めていくといいと思います。
寺田: 考えることは多そうですが、指針になるものを得られた気がします。指針を持って考えることが大事ですね。
6. クロージング
寺田: ありがとうございました。キャリアパス第2回目、語っていただきましたが、まず永江さん、いかがでしたか?
永江: 今回もリクエストをいただいた内容でお話をしましたが、やはり「こういうことを知りたいんだな」ということが分かると、すごくありがたいですね。もっとたくさんリクエストをいただけると嬉しいなと思います。
寺田: 本当ですね。ぜひ皆さん、聞きたい話、気になっている話をお寄せいただけたら嬉しいです。小山さん、いかがでしたか?
小山:キャリアパスの話って意外と少ないなと思っていて、特定の個人に当てたモデルケースの話や、一般的な話はあると思うんですけど、今回みたいに割と踏み込んで、細かいところも含めて話す機会はなかなかないと思います。
私自身も若い頃にこういうことを知っていたかというと、知らなかったので、この機会がインフラエンジニアの方だけでなく、それ以外の方々にも何か良いヒントになるような回になればなと思ってお話ししました。
寺田: 本当に、考え方がすごく参考になりました。まず前提として市場価値を考えなければいけないことや、単純に給料の数字だけを見てはいけないんだなと。どうしても数字は気になってしまいますけど、それだけを追いかけちゃダメなんですね。
小山: そうですね。キャリア形成というもの自体が、変わってきているんでしょうね。
寺田: ぜひ皆さん参考にしていただけたらと思います。
この番組はSpotify、Apple Podcast、Amazon Musicで配信中です。
ポッドキャストへのフォローとレビューもぜひお願いいたします。
番組へのご質問やリクエストは、専用フォームか、各種SNSから受け付けております。気になることがありましたら、ぜひお寄せください。


