2025/07/23
インフラエンジニアのホントのところ #11|インフラエンジニアのキャリアパスを考えよう【働き方編】
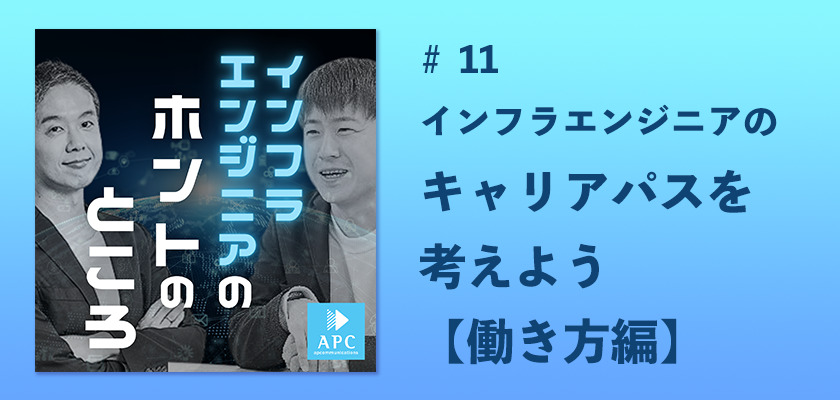
ITインフラって、「なんだか難しそう」「地味で大変そう」と思われがち。
でも実は、社会を支える根幹にある、とてもやりがいのある仕事なんです。
そんなリアルをお届けするPodcast 「インフラエンジニアのホントのところ」。
MCにはベンチャー女優の寺田有希さんを迎え、当社の副社長 永江耕治と採用責任者 小山清和が、現場・経営・採用の視点から語ります。
今回のテーマは「インフラエンジニアのキャリアパスを考えよう【働き方編】」。
インフラエンジニアはどんな働き方が叶うのでしょうか。理想の『働き方』を叶えるために考えるべきこと、するべきことについて徹底解剖していきます。
<目次>
1.オープニング
2.質問:エンジニアの情報キャッチアップ術とは?
3.インフラエンジニアのリモートワーク事情
4.採用市場で高まる「ワークライフバランス」への意識
5.ワークライフバランス実現の鍵は「信頼」と「セルフコントロール」
6.採用面接で希望を伝える際のポイント
7.クロージング
1.オープニング
寺田:言葉は有名でも、何かと知らないことが多いインフラエンジニアの世界。キャリアや将来性、魅力など、ついつい隠れがちな「本当のところ」を、業界のプロであるエーピーコミュニケーションズの永江さん、小山さんと共にインフラエンジニアのキャリアを徹底解剖していきます。
永江:エーピーコミュニケーションズの永江です。現在は副社長をしておりますが、ITインフラエンジニア業界では23年の経歴を持っております。どうぞよろしくお願いいたします。
小山:エーピーコミュニケーションズの小山です。私はIT業界で10年以上の採用経験を持ち、7回にわたる転職でキャリアを形成してきました。当社では人事として採用責任者を務めています。
寺田:MCを務めますベンチャー女優の寺田有希です。
さて、先日は視聴者の方からいただいたリクエストにお答えしましたが、なんと本日は質問もいただいております。そちらにまずお答えいただいてから本編に移っていきたいなと思っております。
2. 質問:エンジニアの情報キャッチアップ術とは?
寺田:本日いただいた質問です。「近年インフラエンジニアのカバーする領域が増えたと話されていましたが、どうやってキャッチアップされていますか?」というご質問です。
ご質問ありがとうございます。これは永江さんにお聞きしたいですね。いかがですか?
永江:昔に比べると、キャッチアップの仕方はだいぶ変わってきたなと感じますね。ご質問者さんが書かれている通り、領域がかなり増えているという背景もありますが、学習環境や知識の習得環境もだいぶ変わったと思っています。
昔は書籍や雑誌といった媒体が中心でした。今ももちろんありますが、それだけだとスピード感としては追いつかない部分があります。ブログはもちろん、YouTubeなどの動画で情報を集めている人も多くいます。また、オンライン学習サイトで言うと、『Udemy』は多くの方が使われていると思いますが、そういった場所では研修が作られるよりもかなり早いスピードで新しい知識が出てきたりします。
あとはエンジニア同士の勉強会も頻繁に行われていて、そういった場に参加することが、生の情報のキャッチアップとしては一番早いのではないかと思います。
寺田:ありがとうございます。コミュニティの情報は早いんですね。
永江:はい、一番早いのではないでしょうか。
寺田:では、コミュニティに所属したり、そういう場所に出向いたりしながら、SNSなどでもキャッチアップしていく。そして、動画サイトや『Udemy』のようなものを効果的に使いながら、というのが一番いいのかもしれませんね。
永江:そうですね。
寺田:これまでも何度も、時代の変化が激しいとおっしゃっていました。そういった変化に対応する力や、利用する技術を身につけていかなければいけないのですね。
永江:そこはすごく重要なことになるかなと思います。
寺田:ありがとうございます。ぜひ参考にしていただけたらと思います。
3. インフラエンジニアのリモートワーク事情
寺田:本日のテーマは「インフラエンジニアのキャリアパスを考えよう ~働き方編~ 」です。
先日、リクエストをいただきました。「インフラエンジニアのキャリアパスについて話してほしいです。インフラのエキスパートになるのか、PMやEMなどに転身することもできるのか、どんなキャリアがありますか?」。
一言でキャリアパスと言っても様々な切り口から考えられるということで、職種編、給料・待遇編、働き方編と3回にわたってインフラエンジニアのキャリアパスについて徹底的に考えていきます。今回は最後の3回目、働き方編です。
お給料ももちろん大事ですが、リモートワークは叶うのか、子育てはできるのかなど、働き方もかなり重要ですよね。インフラ業界に興味がある方はもちろん、業界内でキャリアアップを目指す方、そして業界を問わずキャリアに困っている方、特に必聴な内容です。
まず永江さんと共に、現状を整理していきたいと思います。この業界に23年以上いらっしゃる永江さん、現状の働き方はどのような感じでしょうか?
永江:働き方には色々な意味があると思いますが、多くの方がきっと関心があるだろうなという点で言うと、「リモートワークはできるのか、できないのか」というテーマかなと思っています。
ITインフラというと、ネットワークやサーバーといった物理的な機器を扱うので、リモートワークはしづらいのではないかというイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。しかし結論から言いますと、インフラエンジニアもかなりリモートワークができる状況になっていますね。
寺田:以前、この話をお聞きした時、すごく意外でした。現場に張り付いているイメージがどうしてもありました。
永江:もちろん、現場に出て物理的な作業をすることがゼロになったわけではありません。ですが、当社のケースで言いますと、社員の8割がほとんどリモートワークです。とはいえ、週に1回チームで集まったり、お客様先でミーティングをしたりすることもありますが、基本はリモートワークという社員が8割です。
残りの2割のうち1割は、ほぼ毎日出社しています。そしてもう1割は、半分くらい出社という感じですね。ITインフラだけを専門にやっている当社でも、このような環境です。
もちろん会社さんによって、どういうお仕事をされているかで変わってくるので、これが業界全体とは言いませんが、一つの事例としては言えるかなと思います。
寺田:自分で会社を選べば、リモートワークも叶うという感じですか?
永江:そうですね。決してできないわけではなく、むしろ選択肢としてあるということですね。
寺田:「どこに住むか」という話ではどうでしょうか?例えば東京に住まなければいけないのか、地方に住んでも大丈夫なのか?
永江:正確な統計情報を持っているわけではないので、あくまで当社の事例でお話をすると…今、私たちのオフィスは東京にしかなく、社員数は500名弱なのですが、80名ほどの社員が関東圏以外の場所に住んで働いています。場所は、北海道から沖縄までさまざまです。
寺田:かなり多い気がしました。
永江:だんだん増えていって、今でも増え続けています。当社は多い方なのかもしれないですね。
寺田:そう思うと、かなり働きやすい環境も作れますし、働き方も選べるようになっているということですよね。
永江:以前に比べると、働き方の柔軟性は出てきていると思います。
4. 採用市場で高まる「ワークライフバランス」への意識
寺田:続いて、小山さんと一緒に現在の市場について見ていきたいと思います。採用のプロ、小山さん。まず「ワークライフバランスを整えたい」という希望は、採用市場でも大きくなっているのでしょうか?
小山:そうですね。私が採用の仕事をするようになってから17年、この業界に関わってからは14年ほど経ちますが、関わり始めた当初は当然そういった話は出てくるはずもなく、基本的には「ワーク、ワーク、ワーク」といった感じでした。
ただ、この1~2年で顕著に変化が出てきています。例えば、当社の場合、選考段階でエントリーシートを書いていただくのですが、その中の優先したい事項にそういったことを書かれる方もいます。他社さんの話を聞いてもそうですし、もっと言えばSNSのような場所でも、ワークライフバランスを大事にしたいとおっしゃる方や、それを体感しているという投稿も多く見かけます。
明らかに流れが変わり、そういうことを求める方が増えているのは間違いない状況だと思います。
寺田:でも、ここ1~2年なんですね。結構最近ですね。
小山:おそらく、そう思っていた人は以前からいたんだと思うんです。ただ、なかなか声を大にしては言えなかったのが、最近では普通のことになってきて、普通に言えるようになったのではないか、と。
あとは、「ワークライフバランス」という言葉自体を知らなかった方もいたと思うんです。「今、自分がやりたいことを言語化して一言で言うと何だろう?」となった時に、「ワークライフバランス」という言葉がぴったりだ、と認知が広がって、皆が使うようになったのではないかと個人的には考えています。
寺田:確かに、この言葉自体を聞くようになったのは最近かもしれません。
小山:そうですね。「生活を安定させたい」とか「仕事を充実させたい」といった表現は普通にあったと思うんですけどね。
寺田:確かに。
小山:「充実させたい」といったことを一言でまとめて言うと「ワークライフバランス」ということなのかもしれませんね。
寺田:そう思うと、このワード自体がマジョリティになってきたからこそ、皆さんも考えやすくなったし、考えていく人ももちろん増えていくでしょうし、考えないといけなくなりますよね、きっと。
小山:あとは、主張ができるようになったということでもあると思うんですよね。
これまでは言わなかった理由として、例えば選考でネガティブに捉えられるとか、「コミットしてくれないんじゃないか」と思われてしまうとか、そういったこともあったんじゃないかと思います。
しかし、今は転職もポピュラーになってきているので、会社側が従業員に報いたり、良い環境を提供したりしないと辞めてしまう状況になっています。だからこそ、会社もその点を考慮しなければならなくなったという背景もあると思います。
そこも変化だと思います。いわゆる人的資本経営的な考え方です。人を資本だと考えて、企業側は従業員に対してしっかりと投資していかなければいけない。上場企業ですと人的資本の情報を開示しなければならなかったりもします。それを見て投資家が投資をするという時代でもありますから、その変化というのもあるのではないでしょうか。
5. ワークライフバランス実現の鍵は「信頼」と「セルフコントロール」
寺田:では、具体的にどうすればワークライフバランスを整えられるのでしょうか?
小山:これはインフラエンジニアだけの話ではないと思います。あくまで私が当社の採用責任者として、また他社の人事の方と交流する中で聞いた話をまとめると、ワークライフバランスを整えるためには、会社の中や市場の中で一定の評価をされたり、認められたりすることが必要なのではないかと感じています。
言葉を選ばずに言えば、「この人なら大丈夫だよね」という信頼をまず得ているから、ライフの部分で何かがあった時や「こうしたい」と言った時に、「大丈夫だよ、あの人なら」という関係が成り立つんだと思うんです。
これは、それまで目の前のことにしっかりと向き合ってきて、社内や上司、もっと言えば市場の中で認知され、信頼された結果だと考えています。実際にライフを充実させている方々は、その過程でワークのアクセルをしっかり踏んでいた時期があった人が多いと思うんです。もちろん絶対とは言えませんが、そこがあってこそのワークライフバランスではないでしょうか。
寺田:前回の給料・待遇編でもお話ししましたが、「まずは成長産業に入ることは大事。でも入ったからといって勝手に給料は上がらない」という話と似ていますね。ただ会社にいるだけでバランスを整えられるわけではなく、そのためには相応の価値を提供し、信頼関係を築かなければいけない、と。
小山:そうですね。トレードオフというか、会社に貢献するからこそ、会社も従業員に対して何かしらで応えなければいけない、という順番にはなってきます。
寺田:その会社が何を提供しているのかという嗅覚を働かせて選んでいくことも大事ですが、その中で自分ができることも探していかなければいけないですね。
小山:組織貢献や事業成長への貢献というところはセットだと思います。全部が自分の思った通りにいくことはなかなか難しいと思うので。
自分が思う満足度を高めていくためには、社内や市場の中でどういう立ち位置を築いていくかということも、重要になってきます。
寺田:では「ワークライフバランスを叶え、自分の価値も上げていきたい」となったとき、具体的に何をすべきか整理していきたいのですが、永江さん、いかがでしょうか。
永江:これはインフラエンジニアに限った話ではないと思いますが、私は二つの側面が必要だと考えています。
一つは、まず「柔軟な働き方ができる環境を選択する」ということです。場所や時間といった柔軟な働き方ができる制度がそもそもないと、ワークライフバランスを整えるのは難しくなると思います。
もう一つの側面ですが、そういった環境に入ったら、今度は「セルフコントロールをしっかりできる人」になる必要があると思います。
寺田:セルフコントロール…?
永江:私たちの会社は柔軟な働き方ができるのですが、採用の場面などでは誤解を与えないように、「決してぬるま湯の職場というわけではありません」とお伝えするように気をつけています。
どういうことかと言いますと、成果は求めないのではなく、しっかりと求めていきます、ということです。リモートワークで近くに同僚や上司がいない場合は、自律的に仕事を進め、分からないことがあれば自分から聞いて解決していく必要があります。周囲の目がないから「ちょっとサボっちゃおう」というような人だと成り立たないんですよね。
ですから、自律的に一人称で仕事ができるという前提と、組織に貢献する意欲と実行力がセットでなければ、この働き方は成り立たないと思います。
寺田:チームがやってくれるからいいやとか、他の人がやってくれるからいいや、という考えではそもそも叶わないということですね。
永江:そう思います。
寺田:なるほど。そう思うと、どうすればワークライフバランスを叶えられるのかというのは、もちろん組織や会社を選ぶこともそうですが、貢献しようという意欲が大事なんですね。
永江:そうですね。向上していく意欲や、実際に成長し続けるという姿勢がないと、なかなかうまくは成り立っていかないんじゃないかなと思います。
寺田:では、自分をどう成長させていくかという点で、何かできることはありますか?やはり新しい技術のキャッチアップなどでしょうか?
永江:技術もそうですが、ビジネスにおいて必要なのは技術だけではありません。例えば、広い意味でのコミュニケーションスキルも必要ですし、その事業に対する理解、提供しているお客様に対する理解など、学ぶべきことはたくさんあります。そういったところに目を向けられると良いと思いますね。
寺田:なるほど。そうして自分の価値も上げて、信頼関係も築いていく。
永江:はい、その通りです。
6. 採用面接で希望を伝える際のポイント
寺田:小山さん、採用責任者をされていて、「ワークライフバランスを叶えたいんです」という感じで希望を伝える方は、転職者や新卒の方でも結構いますか?
小山:いらっしゃいますね。面接で、一番ではないけれど、いくつかの希望のうちの一つとして挙げる方はいらっしゃいます。
寺田:その時、どう対応されるのですか?
小山:伝え方には気をつけなければいけませんが、実現できることとできないことは、割とはっきり伝えています。「これはうちだと叶えられる可能性はあるけれど、これは難しい」というように。
一番良くないのは、本当はできないのに「うちは検討しますよ」といったようにはぐらかしたり、嘘をついてしまったりすることです。実際にあるんですよ、新卒で入社したら聞いていた話と全然違った、ということが。リモートができると聞いていたのにできなかった、そもそもそんな規則はなかった、といった恐ろしい話もあります。
会社としては学生の方々と真摯に向き合うべきですし、結局は入社してからが大事ですから、そのあたりははっきりとお伝えした上で、最終的にご本人に判断していただくようにしています。これは中途採用の方に対しても同じですね。
寺田:受ける側も、自分が提供できる価値などをはっきりさせておかないと、そういった希望を伝えてもなかなか通りにくい、といったことはあるのでしょうか?
小山:そうですね。面接はお互いフラットな関係だと思いますので、自分の希望はあまりオブラートに包まず、できる限り具体的に伝えた方がいいと思います。
細かすぎても少し困りますが、ワークライフバランスの中でも、例えばライフ面で「どうしてもこういう事情があるので考慮してもらえませんか」とか、「何か対応はできませんか」といったように伝えた方がいいですね。
寺田:家族のことなども、言っていいんですね。
小山:はい、全然問題ないと思います。むしろその方が良くて、私たちがそれを知っておくことで対応できることもあります。
入社してから何かあった時に「どうしたんだろう?」となるよりも、最初に伝えていただいた方が、「それならうちの制度で対応できますね」とか「こういう形でフォローアップできますよ」という話ができると思います。
お互いのことを考えても伝えておいた方がいいですし、私たちとしても、逆にしっかりと話をしていただいた方が、相互理解が深まると考えています。
寺田:では、面接ではフラットな関係で条件を伝え合い、環境を選んだ上で、あとは自分の価値を高めていく、というのがワークライフバランスを整えるための大事なステップということですね。
小山:そうですね。スキルが上がれば全てが良いということでもありません。能力を発揮するためには、心の安心・安定が絶対必要だと思います。それがライフの部分や条件面だったりするわけですが、ある程度納得感がないと不安なままでは力を発揮できませんしね。
7. クロージング
寺田:さて、お二人ありがとうございました。永江さんは、ワークライフバランスを意識されていますか?
永江:そうですね。私たちの会社は、場所の柔軟性という点では、もう6年目になります。それでもビジネスは十分に拡大していっているので、できないのではなく、できるんだなと思っています。
一方で、やはり提供価値がとても重要だと思うので、働き方がどうこうよりも、働く側も会社としても、いかに高い価値を提供できるかにこだわることが、とても重要なことかなと思っています。
寺田:提供価値ですね。小山さんはいかがですか?
小山:永江さんの話にもあった通り、お客様に提供できる付加価値を上げていくために、従業員のワークライフバランスを考えた方が良い、と私たちとしては判断し、そこに対して積極的な投資をしています。逆を言えば、今のやり方が事業成長に影響を及ぼすとなると、また状況が変わってくる可能性もあります。
ですから私たちのような管理系の人間は、しっかりと機会を作っていくことも含めて、従業員の皆さんが良い状態でパフォーマンスを維持できるよう、うまく間に入って調整していかなければいけないと思っています。
寺田:ありがとうございます。皆さん、参考にして考えてみていただけたらと思います。
キャリアパスについては前の2本でもかなり深く語っておりますので、ぜひそちらも合わせてお聞きください。
この番組はSpotify、Apple Podcast、Amazon Musicで配信中です。
ポッドキャストへのフォローとレビューもぜひお願いいたします。
番組へのご質問やリクエストは、専用フォームか、各種SNSから受け付けております。気になることがありましたら、ぜひお寄せください。


