2025/07/30
インフラエンジニアのホントのところ #12|インフラエンジニアが持っておくべき資格とは?
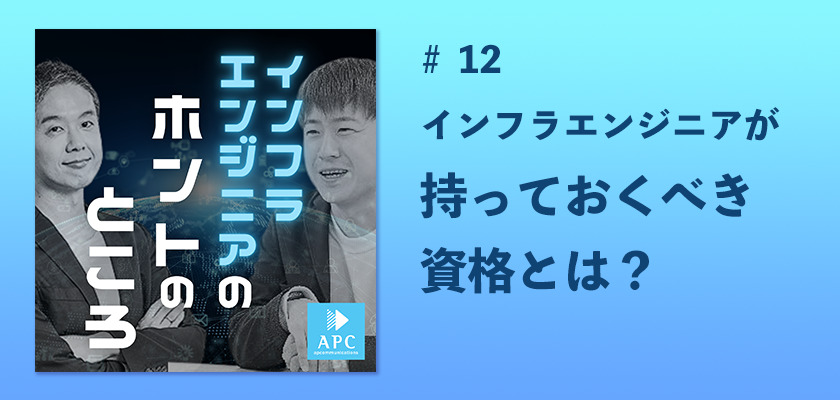
ITインフラって、「なんだか難しそう」「地味で大変そう」と思われがち。
でも実は、社会を支える根幹にある、とてもやりがいのある仕事なんです。
そんなリアルをお届けするPodcast 「インフラエンジニアのホントのところ」。
MCにはベンチャー女優の寺田有希さんを迎え、当社の副社長 永江耕治と採用責任者 小山清和が、現場・経営・採用の視点から語ります。
今回のテーマは「インフラエンジニアが持っておくべき資格とは?」。
インフラエンジニアとして成長するうえで、資格は必要?どう考え、何を選ぶべきなのか。
新卒・未経験、転職、キャリアアップ、それぞれの段階に合った『資格』の考え方を深掘りします。
<目次>
1.オープニング
2.インフラエンジニアに資格は必要か?
3.キャリアパス別:おすすめの資格と取得の考え方
4.キャリアの考え方、T字型キャリアの重要性
5.クロージング
1.オープニング
寺田:言葉は有名でも、何かと知らないことが多いインフラエンジニアの世界。キャリアや将来性、魅力など、ついつい隠れがちな「本当のところ」を、業界のプロであるエーピーコミュニケーションズの永江さん、小山さんと共にインフラエンジニアのキャリアを徹底解剖していきます。
永江:エーピーコミュニケーションズの永江です。ITインフラエンジニア業界には23年以上います。どうぞよろしくお願いいたします。
小山: エーピーコミュニケーションズの小山です。私は10年以上のIT業界での採用経験と、7回にわたる転職でキャリアを形成してきた、人事の小山です。よろしくお願いいたします。
寺田:そして、同じくMCを務めます、ベンチャー女優の寺田有希です。さてさて、すごくざっくりお聞きしますが、最近何かありましたか?
小山: 公式でも告知しているのですが、当社の部活動支援として、桜美林大学の女子バレーボール部をスポンサードさせていただき、先日調印式も執り行いました。
1年ぶりくらいにスーツを着て、先方の顧問の先生と選手の方々と少しお話をさせていただきました。新卒採用という文脈と、IT業界やインフラ分野ではやはり女性エンジニアが非常に少ないという現状から、エンジニアを増やしていきたいという活動の一環としてやらせていただいています。
実は永江さんが主導で進めている取り組みで、こういった形での支援は少し珍しいかもしれませんね。
寺田: 大学の部活動を支援する、ということですか?
小山: そうです。活動費として協賛をさせていただき、私たちのロゴなどを練習着に掲載していただきます。試合観戦にも行かせてもらっています。
永江: 桜美林大学の女子バレー部はかなり強いんですよ。関東に複数あるリーグの中で一番上のリーグで、今、優勝を目指して頑張っています。
寺田: すごいですね。
永江: 強豪校から集まったメンバーが多くて、次のリーグ戦が始まったら、また応援に行きたいなと思っています。私たちにとってもすごく貴重な体験でした。
寺田: そのような支援もされているんですね。
小山: たまたま、テレビ東京の『ワールドビジネスサテライト』で放送されていたんです。中小企業が新卒採用の一環として部活動の支援をするという内容で、有名な部活動には既に大きな会社やOBがついていることが多い、という話でした。それを私が見かけて、「これは面白そうだ」と思ったところから始まったんです。
寺田: いいですね。そういう新しいことも「やっちゃおう!」というのが、エーピーコミュニケーションズさんの良いところですね。
永江: 実はバレー部には「アナリスト」という役割の方もいるんですよ。データを分析するということをやられているんです。
なので、ITに関わっていますよね。私たちもデータ基盤のお仕事をさせていただくことがありますが、ある意味、分野的には少し近いところも実はあるんです。
寺田: スポーツの世界もそうなんですね。 強くなればなるほど、データ分析をしているイメージは確かにあります。
小山: アナリストの推薦枠があるらしいですよ。アナリストが推薦で大学に入ってくるという話を監督から聞きました。
寺田: そんなことがあるんですか!
小山: それくらい「データバレー」なんだと思います、強豪校は。高校でも普通にやっているみたいですから。
寺田: データスポーツですね。そう思うと、ITの分野もまた広がりますね。
永江: それはありがたい限りです。
2. インフラエンジニアに資格は必要か?
寺田: それでは本日のテーマに移ってまいりましょう。本日のテーマは『インフラエンジニアが持っておくべき資格とは』です。
ここまで3回にわたってインフラエンジニアのキャリアパスについて考えてきました。考え方の方向性が見えたところで気になるのは、具体的にどう自分の価値を高めていけるかですよね。
そのために資格を取るべきか悩んでいる人も多いのではないでしょうか。そこで、インフラエンジニアが資格を取ることは本当に有益なのか、そしてどの資格がおすすめなのか。新卒や未経験の方、転職したい方、キャリアアップしたい方、それぞれの目線で徹底的に解剖していこうと思います。
それではまず、エンジニア目線で永江さんにお聞きしたいのですが、インフラエンジニアも資格は取った方がいいのでしょうか?
永江: これは、その人の経験とスキルによるというのが答えになります。
既に実績があり、実力もある方は必ずしも資格が必要というわけではありません。ただ、まだそれほど経験がない方や、これからエンジニアを目指す方にとっては、有効な手段の一つだと思います。
寺田: なるほど。ちなみに永江さんも資格を取得されたことはありますか?
永江: はい。エンジニアとして活動していたのはかなり昔になるので、だいぶ前の話ですが、Cisco Systems社の「CCNP」というプロフェッショナル向けの資格を勉強して取得しましたね。
あとは、会社全体での取り組みとして、Pythonという言語の資格を社員100人くらいと一緒に取得したこともあります。最近ですと、2年くらい前にAIの概要が学べる「G検定」というものを少し勉強して取得しました。ですが、最近はそれほど多くは取得していません。
寺田: 資格を取得した時の気持ちとしては、新しい分野を勉強したい、あるいは価値を高めたい、という感じでしたか?
永江: そうですね。エンジニアとしてやっていた時は、市場価値が上がる感覚はありました。特にその時々の旬な技術はそうですね。
あとは、会社によって力を入れている分野も異なるはずなので、何が本当に良いかは、所属している会社や自分がどういう分野で活躍していきたいかによっても変わってくるかと思います。
寺田: 採用責任者を務められている小山さんにお聞きします。やはり採用を決める際も資格の有無は見ますか?
小山: その点で言うと、あった方が良いと言いたい気持ちと、一概にそうとは言えない側面もあり、少し複雑な回答になります。
あるかないかで言うと、持っていた方が良いとは思います。なぜかと言うと、例えば新卒の方や経験の浅い方の場合、「エンジニアとして頑張りたいです」「勉強しています」と言うのは簡単ですが、その努力を証明する手段の一つが資格だと思うんです。
「エンジニアとして勉強して頑張っています」という言葉の根拠を聞かれた時に、資格を持っていると「この人はちゃんと勉強してきているんだな」ということが、まず分かります。加えて資格には難易度もありますから、持っている資格の難易度が高ければ高いほど、学習時間も必要になるはずです。そこは評価すべきポイントだと思います。
ただ、気をつけなければいけないのは、資格は「頑張っています」というアピールにはなりますが、それがイコール「優秀なエンジニアになれるか」「活躍できるか」というわけではありません。これはITインフラの資格に限らずです。例えばTOEICで満点を持っているからといって英語が完璧かというと、全くそうではないケースもあります。
ポテンシャルのある人材かどうかの指標にはなるので、それに加えて面接でのコミュニケーションや、会社・部署が求める人物像との相性も見ていきます。
もちろんあった方が良いですが、資格があるからといって全てが決まるわけではない、ということです。会社によっては資格手当で給料が上がることもありますのでメリットはありますが、それが全てを保証するわけではない、ということですね。
たまに資格を取ること自体が目的になってしまっている方もいらっしゃるなと感じます。
寺田:資格を取ったら終わりではない、という意識改革は必要ですね。
小山: そうです。やりたい仕事に就くために、どうしてもその資格がないとチャンスがない、あるいはそもそも関われないというのであれば、取るべきです。例えば弁護士になりたいなら、弁護士資格がなければ話になりません。資格にはそういった側面もあると思います。
たくさんの資格を持っていることで、クライアントからの信頼を得て、より上流の仕事を任されることもありますしね。私たちも、資格保持者がいるということがクライアントからの信頼につながり、「安心して任せられるね」という話になったこともありました。
寺田:そう考えると、やはり新卒の方や未経験で業界に入りたい方にとっては、「私はこのくらいできますよ」というアピールになる良い指針かもしれません。
小山:採用側としては「この人ならポテンシャルがある」という判断の一つの軸になると思います。
3. キャリアパス別:おすすめの資格と取得の考え方
寺田: ここからは、どのような資格が必要なのかについて、永江さんと共に深掘りしていきたいと思います。まず、インフラエンジニア全員に必要な資格というのはあるのでしょうか?
永江: その点で言えば、必ずしも資格がないと仕事ができないわけではないので、「全員が持っていなければいけないものはない」と言えます。ただし、知識が不要かというとそんなことはなく、資格は特定の分野・範囲について体系的にまとめられているので、学習においてはすごく効率的ですし、どれくらい学習が進んでいるかを測る指標にもなります。
寺田: なるほど。
永江: そういう意味で「意味がない」ということは全くありません。
寺田: 自分の能力値を測るために資格を受ける、という側面もあるのですね。
永江: それもありますし、経験豊富な方でも、新しい分野が出てきた時に「その知識は既に吸収できていますよ」というアピールにも使えます。
寺田: 普遍的に必要な技術というよりは、新しいシステムが出てきたから、その知識を深めるためにこの資格を取ろう、というような使い方もあるんですね。
永江: 他の分野の学問と違い、IT技術は常に変わり続けるものがかなりの割合を占める、という性質があります。ただ、変化はしつつも比較的基礎的で、ITに携わる人として知っておいた方が良いものはあります。
良い例として「基本情報技術者試験」です。決して簡単ではありませんが、とはいっても難しすぎるわけでもないので、特に若い方であれば勉強しておくと良いものの一つと言えると思います。
寺田: なるほど。他にはありますか?
永江: それ以外ですと、どの分野で仕事をしていくのかによります。インフラと言っても様々ですので。例えばクラウドの分野であれば、AWSの仕事をしていくならAWSの資格、Microsoft Azureであればそちらの資格を取っておいた方が良いでしょう。
最近当社ではオラクルのOCI(Oracle Cloud Infrastructure)に力を入れていまして、この数ヶ月の短い間に100人くらいが新たにその資格を取得しました。このように、時代の流れや、会社として注力していく分野によっても変わってきます。
寺田: ありがとうございます。次に、新卒でインフラエンジニアを目指す方や未経験で転職されたい方が「何を取ったらいいんだ」と考えた場合、いかがでしょうか?
永江: いくつかのパターンが存在していると思います。昔は、ネットワークなら「CCNA」、サーバーならLinux関連の「LinuC」などを取るパターンが非常に多かったですね。
今もその流れはありますが、最初にAWSの認定資格を取るという方がすごく増えていますし、Azureを選ぶ方もいます。そこは結構変化があるところですね。
寺田: そのパターンはどう選べばいいのでしょうか?
永江: まずはその方が何をやりたいのか、そして、どこの会社で働きたいのか。その二つを重ねていくことが必要になると思います。
本人がその分野をやりたいという気持ちと、会社によって力を入れている分野は少しずつ違うので、そこのすり合わせが重要になります。所属している会社が力を入れているものと、自分がやりたいものを重ねていくことが、キャリア形成の上で非常に重要なポイントです。
寺田: 自分で調べたりして感度を高く保ち、資格も取ってその業界を目指す、というステップが必要なんですね。
では、次に経験者で転職する場合はいかがでしょうか?
永江: 転職においても、より多くの求人がある市場の大きい分野を狙うという戦略も一つですし、逆に、範囲は狭いけれど自分が競争力を持てるニッチなところを狙っていくパターンもあると思います。
寺田: なるほど。
永江: それによって、個人の転職戦略も変わってきます。トレンドになっている分野、例えば今だとクラウドの中で市場規模が一番大きいAWSは、学習環境も豊富で資格を持っている人もたくさんいます。その中で全ての種類の資格をちゃんと持っている、というのは一つのステータスになっています。それを目指すのも良いですが、そこには既に多くの競合がいると考えて、別の領域で勝負するという選択肢もあるでしょう。
あとは好みもあると思います。市場価値を戦略的に考えて取得する方法もありますが、単純に自分がそれに興味があってやりたいから、という動機も当然あるかと思います。何を大事にするか、ですね。
価値を求めるという視点で考えるなら、市場価値や将来性についてきちんと調べ、その中で自分の競争力はどこにありそうか、どこであれば勝負ができそうか、という観点で考えていくと良いのではないでしょうか。
寺田: そう思うと、自分のパーソナリティを深く知っておくことも大事ですね。「自分はこういうことが得意だから」といった自己分析がないと、舵を切れませんよね。
永江: はい。これは企業の事業戦略と考え方が似ていると思うんです。それぞれの会社は、市場のトレンドを読みながら、過去に築いてきた資産を活かして事業を拡大していきます。市場が大きいから仕事も多いだろうと、競合がたくさんいる中に飛び込んでいく場合もあれば、そこではトップになれないから、トップになれそうなところを狙うという考え方もあります。ただ、まだ勝負がついていない領域は、市場が本当に大きくなるか分からないというリスクもあります。
資格のトレンドの話も同様で、正確な未来予測は難しいんです。
寺田: 資格一つ取るにしても、感度を高く保ち、未来を予測する力を磨き続けること。そして自分は何がしたいのか、どういう人間なのか、ということに常に向き合い続けるのが大事なんですね。
永江: はい。この質問は、おそらく経験がない方やこれから業界に入りたい方が抱くものだと思います。
それはすごく自然なことで、それに対してスクールや人材紹介エージェント、ブログなどの情報源が「これがいいんじゃないですか」と提示するのは、今トレンドになっていることが多いんです。それはそれで間違ってはいません。
ただ、それは「今」の状況を伝えているだけなので、それに乗っかるのも一つの手ですが、先を読んでいくことが、キャリアをより良くする上での重要な分かれ道になる可能性があります。深く考えるのであれば、そういった先のことも考えていく方が、本来は良いと思います。
寺田: 深いですね…。「どの資格を取ればいいですか?」「はい、分かりました。受けます」という単純な話ではないですね。
では、キャリアアップをしたいと思った方にとっては、いかがでしょうか?
永江: キャリアアップを目指すのであれば、シンプルに市場価値が高く、難易度が高い資格が重要になります。難易度が高く、かつ市場からの需要が今も将来もある、というものが一番です。
ものすごく難しいけれど取得しても仕事があまりない、というものよりは、その難しい資格を取得すれば確実に市場価値の高い仕事が存在している、というものが、「キャリアアップのための資格」としては適切な答えになると思います。
寺田: キャリアアップとなると、やはり難易度が高いものや希少性のあるものが良いのですね。
永江: どちらかというと、そうなってきますね。
寺田: 考え方がものすごく参考になりました。
4. キャリアの考え方、T字型キャリアの重要性
寺田: 最後に、採用担当者の目線も含めてお聞きしたいのですが、自分が取るべき資格をどうやって見つければいいのでしょうか?小山さん、お願いします。
小山: これも恐らくITの資格に限りませんが、まず自分がどういった仕事をやりたいか、というところから始まると思うんです。良くない例として、漠然と「エンジニアになりたい」と思い、とりあえず片っ端から資格を取るような方も時々いらっしゃいますが、あまり良い結果にはなりません。
キャリアの考え方として、「T字型キャリア」というものがあります。T字の縦の支柱、つまりコアになるスキルをまずしっかりと根付かせ、そこから上の横棒を広げていくという考え方で、個人的には良いキャリアの築き方だと、思っています。
まず尖った強みがあるからこそ、それを活かして幅を広げることで仕事の幅が広がるわけです。
例えば今、開発エンジニアの方もインフラの知見を持たなければいけない、というのもT字型の考え方です。今は、開発エンジニアのスキルだけだと厳しくなってくる時代です。昔はJavaだけでなくPHPやDBもできます、というように開発言語の幅が広ければ良かったのですが、今はそこだけでなく、ビジネススキルやインフラの理解にまで広がってきています。
でも、それができるのは、ちゃんと開発者としてのベースがあるからこそ生きてくるわけです。
寺田: なるほど。
小山: ベースができずに横にだけ広げても、支えがないので崩れてしまいます。ですから私としては、まず「今伸ばしたいこと」「やりたいこと」を絞った方が良いと思っています。
その上で、それを実現するためにはどの資格が良いのかを考える。まずは自分で軸を決めて、そこをしっかりと伸ばす。そしてそれが自分だけでなく周りからも評価され、「あなたはこれができる人ですね」と言われるようになったら、今度はまた別の資格を取って幅を広げていくのが、キャリアとしては良いのではないでしょうか。
一番良くないのは器用貧乏だと思います。どれもこれも何となくできる、というのは強みに見えて、実は結構苦しいんですよね。
寺田: H型ではダメでしょうか。軸が2本あるような。
小山: いや、支柱が2本あるなら、それはそれで素晴らしいですよ。軸と軸をつなげる能力があれば、それは活きてきます。「何かと何かを掛け合わせる」という感じですね。
寺田: 確かに。
小山: でも、それはすごく難しいと思います。ブリッジできる人材はあまりいません。ビジネスにおいても、一見すると関係ないものをつなげることでイノベーションが生まれたりしますが、それはとても難しいことです。
寺田: 「Connecting the dots」とは言いますが、それが難しい。
小山:それだけたくさん行動しているからこそ点が線になるわけで、そこに至るまでに多くの失敗も経験しているはずです。多くの人は、つながる前に心が折れてしまうんだと思います。
寺田: なるほど。H型は最高峰として、まずはT型を目指しましょう、ということですね。
小山: そうですね。自分の軸を定めた上で、それに合う資格を取得していく。これはエンジニアに限らず、活躍されている方々に共通する点だと思います。
私も人事としての経験の幅は広くありませんが、「採用」という尖った専門分野があったおかげで、そこから横に派生できていると感じます。
5. クロージング
寺田: 資格の話からかなり深い話になりましたね。まさかこういう展開になるとはという感じでしたが、いかがでしたか、永江さん。
永江: 資格の話は色々なところで語られていますが、分かりやすさを優先するなら「具体的にはこの資格です」とお話しする方が良いのかもしれません。しかし実際には、何を目指し、その人自身がどういう状況にいるのかがすごく重要です。
ですので今日は、どちらかというと「考え方」、戦略的にキャリアを考えるのであれば、こういう視点を持った方が良いのではないでしょうか、ということをお話しさせていただきました。
寺田: そのキャリアの考え方については、既にキャリアパスに関するPodcastが3本上がっておりますので、そちらも合わせて聞いていただけると、より理解が深まりそうですね。小山さんはいかがでしたか?
小山: そうですね。資格については、私が人事の仕事を始めて10数年経ちますが、業界も大きく変わり、資格に対する考え方も変化してきました。キャリアを考える上で、これはずっと出続けるテーマだと思います。
それでもやはり、自分がまず何を伸ばしたいのか、という軸に合わせて資格を考えていくのが良い、という本質的な部分は10数年前と変わっていないと感じます。この話を通じて、改めてその原点に立ち返ることができました。
寺田: ぜひ皆さんも、単に資格を取るということだけでなく、その「考え方」について参考にしてみてください。
この番組はSpotify、Apple Podcast、Amazon Musicで配信中です。
ポッドキャストへのフォローとレビューもぜひお願いいたします。
番組へのご質問やリクエストは、専用フォームか、各種SNSから受け付けております。気になることがありましたら、ぜひお寄せください。


