2025/08/06
インフラエンジニアのホントのところ #13|未経験でもIT業界に転職できるって、ホント?
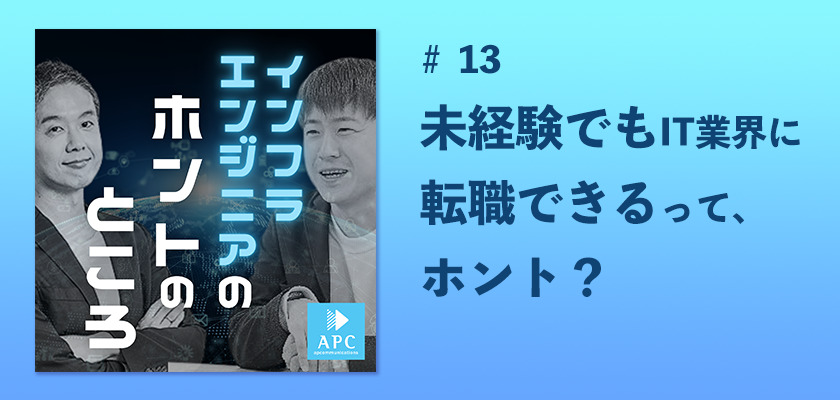
ITインフラって、「なんだか難しそう」「地味で大変そう」と思われがち。
でも実は、社会を支える根幹にある、とてもやりがいのある仕事なんです。
そんなリアルをお届けするPodcast 「インフラエンジニアのホントのところ」。
MCにはベンチャー女優の寺田有希さんを迎え、当社の副社長 永江耕治と採用責任者 小山清和が、現場・経営・採用の視点から語ります。
今回のテーマは「未経験でもIT業界に転職できるって、ホント?」。
「未経験でもIT業界に入れるの?」そんな不安や疑問に、元エンジニア経営者と採用責任者が本音で回答します。
未経験転職の可能性や今の市場、成功のコツまで、現場のリアルを語ります。
<目次>
1.オープニング
2.未経験でもIT業界への転職は可能か?
3.採用担当者が語る!未経験でIT業界を目指すメリット
4.知っておくべきデメリットと「見極め」の重要性
5.自分に合う分野の見つけ方と適性
6.クロージング
1.オープニング
寺田:言葉は有名でも、何かと知らないことが多いインフラエンジニアの世界。キャリアや将来性、魅力など、ついつい隠れがちな「本当のところ」、インフラエンジニアのキャリアの真実を、業界のプロであるエーピーコミュニケーションズの永江さん、小山さんと共に徹底解剖していきます。
永江:エーピーコミュニケーションズの永江です。私はインフラエンジニア業界に23年以上います。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
小山: エーピーコミュニケーションズの小山です。私は10年以上のIT業界での採用経験と、7回にわたる転職でキャリアを形成してきた人事です。よろしくお願いします。
寺田:そして、同じくMCを務めます、ベンチャー女優の寺田有希です。さて、そろそろお盆に差しかかる時期かなと思うのですが、インフラエンジニアはお盆など長期休みは取れるんですか?
永江: 当社の場合になりますが、お盆に取る人もいれば、夏休みとして6月から10月頃にかけて取る人もいて、かなり自由です。期間も長期で取る人もいれば、分割して取る人もいます。比較的しっかり長期休みを取る人が多いかなと思います。
寺田: 長期というと、7日間くらい取れたりするのですか?
永江: 土日を含めて9日間、という人が多いですね。
寺田: 9日間も取れるんですね!そしたら海外旅行とかも行けちゃいますね。
永江: そうですね、海外に行っている人もいますし、実家に帰省するなど、皆さん様々な休みの過ごし方をしているようです。
寺田: 永江さんと小山さんはお休みを取るんですか?
永江: 私はお盆に休もうかと思います。みんなが一番休む時期なので、私も休みやすいんです。いろんな連絡が来ない時期がいいなと。
寺田: やはり経営者だと、周りと休みを合わせるとご自身も休みやすくなりますよね。小山さんはいかがですか?
小山: 私は「山の日」の祝日から休みに入って、今回は実家に帰る予定です。
当社は夏季休暇として、有給休暇とは別に5日間が特別休暇として付与されるのですが、今回は1日余るので、その分は9月の連休に合わせて月曜日に休みを取って、4連休にしようかなと思っています。
寺田: お盆とは別に休暇が取れるんですね。
小山: はい、夏季休暇という形で会社から5日間付与され、それを先ほど永江さんが言ったように6月から決められた期日までに使ってください、と。使わなかったら消滅してしまうので。
寺田: それは使った方がいいですね!
さて、本日のテーマは「IT業界って未経験でも転職できるの?」です。転職を繰り返しキャリアを形成していくことが推奨され始めたこの時代、どの業界を選ぶべきか悩む方も多いのではないでしょうか。IT業界は成長産業として真っ先に思いつきますが、果たして未経験からでも転職は可能なのでしょうか。
そしてIT業界を選ぶメリット、実現する方法を徹底的に解剖していきます。転職にお悩みの方は必聴です。
2. 未経験でもIT業界への転職は可能か?
寺田:本日のテーマは「IT業界って未経験でも転職できるの?」です。それでは早速、インフラエンジニア業界23年以上の経歴を持つ永江さんにズバリお聞きしたいのですが、未経験でもIT業界に入ることはできるのでしょうか?
永江: はい、実際に未経験からIT業界に入ってこられる方は、それなりの数いらっしゃいます。ですので、そのご質問に対しては「可能です」ということが回答になります。
寺田: 異業種からIT業界に転職する人も多いということですね。
永江: そうですね。特にその方の年齢が若ければ若いほど、その可能性は高いかなという感じです。IT業界だけではないと思いますが、年を重ねていくと、だんだん異業種への転職のハードルが上がっていくと思います。
若い方は結構いらっしゃいますね。
寺田: そこから、業界の第一線で活躍できるような人材になることも可能なのでしょうか?
永江: はい、今ものすごく活躍されている方も本当にたくさんいらっしゃいます。
寺田: では、やはり回答としては「可能」ということですね。
永江: 可能です。
寺田: 採用責任者の小山さんと一緒に、採用の観点から業界の市場についてお聞きしていきたいのですが、現状、IT業界への転職を目指す方は多いのでしょうか?
小山: そうですね、「何をもって多いか」という点はありますが、労働人口自体が減少している中でも、他の業界と比べて目指す人は多いと思います。特にIT業界における「エンジニア」という職業の社会的地位が上がってきていて、例えば、小学生がなりたい職業ランキングのトップ10にエンジニアが入ってきたりするわけです。
これはおそらく、親の世代に実際にエンジニアとして働く人がいて、その姿に憧れたり、あるいは少し前の話になりますが、マーク・ザッカーバーグのようなエンジニア出身者が大きな事業を成し遂げたことで、「夢がある仕事だ」というイメージが定着したことも影響していると思います。
寺田: なるほど。
小山: そういうこともあり、イメージがしやすくなった、という方が正しいかもしれません。身近に働いている人がいたり、業界が盛り上がっていたり、過去にはテレビドラマになったりもしました。
そういった背景から、私たちが把握できない部分も含め、目指す人は多くなっているのではないでしょうか。「市民権を得た」というところが大きいと思いますね。
寺田: 「市民権を得た」という点では、YouTuberと文脈が近いかもしれませんね。
小山: そうですね。子供がなりたい職業にYouTuberと書いたりしますし、私の甥っ子も「なりたいものは、YouTuber」と言っています。私たちの世代だと、プロスポーツ選手やパイロットでしたけどね。
寺田:エンジニアの方も、昔は「何をやっているか分からない仕事」というイメージがあったのかな、とお話を聞いて思いました。
小山: そうですね。「外に出ないでパソコンで何をやっているんだ」とか、地方だと「外に出て働くのが仕事」という価値観で言われたこともありました。でも今は、事業を成長させるために不可欠な人材であり職種である、ということが認知され、これも市民権を得たということだと思います。
ITが当たり前の時代になり、売る人だけが増えても、売るものや売るための基盤を作る人がいないと事業が成長できない、という世の中の変化も影響しているでしょうね。
寺田: 総合的に見て、過去と比べても目指す方は増えていますか?
小山: 明確に「何人増えました」と言うのは難しいですが、私がこの業界で10数年採用をやってきた経験から言うと、求人数は間違いなく年々増え続けていると思います。求人が増えるということは、それだけ人材を求める会社が多いということです。広告費や人材紹介会社への手数料を考えても、企業が「投資するべきだ」と判断しているからこそ、求人が増えているのだと思います。
永江: あと、昔に比べてイメージがだいぶ良くなったというのもある気がしますね。かつてはITエンジニアというと「過酷で忙しすぎる」というイメージが強かった時期がありましたが、今は労働環境が本当に良くなっているところが多いです。
もちろん納期直前は忙しくなりますが、昔に比べて全体的に労働環境はすごく良くなっていると思います。
寺田: 実際にお二人も、環境は変わっているとよくおっしゃっていますよね。
永江: はい、そこは大きいと思います。
3. 採用担当者が語る!未経験でIT業界を目指すメリット
寺田: ではここからは、実際に目指す上での質問です。小山さん、採用責任者として、未経験から今IT業界を目指すメリットはどこにあると思いますか?
小山: まず、これまでもお話ししてきた通り「成長産業である」ということが大きいと思います。市場が伸びていることに加え、経済産業省の予測では、IT人材は今後さらに不足すると言われています。2025年時点での不足数は約45万人で、5年後の2030年には約79万人にまで拡大すると予測されています。
寺田:すごいですね。
小山: これは、それだけ市場が伸びる可能性がある一方で、人材が追いつかないということです。
企業側としては経験者を採用したいのが本音ですが、例えばAIのように市場が大きくなってから日が浅い分野では、熟練した人材は非常に少ないんです。そうなると、自社で人材を育成する必要が出てきます。そのため、経験の浅い人でも積極的に採用したいという会社は実際多いんです。
ある大手ITエンジニア専門の人材紹介会社の統計によると、取引先企業の約4割が「未経験者を採用したい」、約3割が「今後検討したい」と回答しており、合計7割が未経験者採用にポジティブです。
需給バランスが崩れているからこそ、未経験からでも飛び込めるチャンスがある。成長産業に、現時点では経験がなくても関われるチャンスがあるというのは、非常に大きなメリットだと思います。成長している産業には人、モノ、金、情報が集中するので、大きなキャリアチェンジを実現できる可能性があります。
寺田: それはつまり、未経験からでもIT業界を目指しやすくなった、ということですよね。
小山: 目指しやすくなったと言える一方で、企業の本音を言えば、どの会社も即戦力となる経験者が欲しいはずです。
寺田: まあ、そうですよね。
小山: ただ、先ほど言ったように労働人口が減っていること、そして新しい技術分野では熟練者が市場にほとんどいないことを考えると、「1年に1人採れるか分からない人材を待ち続ける」より、「ポテンシャルのある人材を採用して自社で育てる」という選択肢の方が現実的になります。
ですから、未経験者にとってはチャンスがある、ということです。
寺田: 他の業界と比べてもかなり増えている方ですか?
小山: どの分野にも人手不足の問題は一定数あると思います。例えば、販売やサービス業の慢性的な人手不足はよくニュースになりますよね。ただIT業界の場合、市場の成長スピードに人材の数が追いついていないという乖離が他業界よりも非常に大きいため、特に注目されているのだと思います。
4. 知っておくべきデメリットと「見極め」の重要性
寺田: 逆にデメリットはありますか?
小山: 未経験者が入りやすい職種というものが存在します。例えば、監視・運用の仕事や、ヘルプデスク、ユーザーサポート、テストエンジニアといった職種です。
募集している会社はたくさんありますが、求職者側での「見極め」が非常に重要です。「とりあえずIT業界に入ればなんとかなる」という時代ではなくなってきているので、どういう仕事に就くか、その会社がどういうビジネスモデルで事業を行っているかを理解しないと、「入ってみたけど、なんか違った」ということになりかねません。
寺田: 門戸は開かれているけれど、無知のまま飛び込んではいけない、ということですね。
小山: はい。「流れに身を任せる」のではなく、何でも良いわけではない、ということです。たくさんの求人があるからこそ、良いものもあればそうでないものも混在しています。伸びている業界だから全部大丈夫、というわけではなく、自分自身でしっかりと見極めるという難しさがあります。
寺田: その見極めの先に、きちんと成長やスキルアップにつながる場所に入ることも可能だ、ということですよね?
小山: もちろんです。ですから、ポジティブな情報だけに踊らされない、ということが大切です。人間は自分の考えに都合のいい情報ばかり集めてしまうバイアスがありますが、そうではなくフラットに物事を考え、メリットとデメリットを理解した上で、自分がどこでキャリアを築いていくべきか判断する必要があります。
ITインフラの中でも、セキュリティやクラウド、自動化といった分野は伸びていますから、そういった領域に関わった方がキャリアの幅が広がる可能性は高いでしょう。そういった見極めが必要だと思います。
複雑だからこそ、市場の中で戦っていくための知識をインプットするのはすごく大事なことだと思います。
5. 自分に合う分野の見つけ方と適性
寺田: 最後に、具体的な方法について伺います。永江さん、ご自身もエンジニアをされていたと思いますが、どの分野が良いか、どれが自分に合うか、というのはどうやって探せばいいのでしょうか?
永江: これは、頭で考えるより「やってみないと分からない」という部分が、かなり大きい割合を占めていると思います。
寺田: そうなんですね。
永江: じゃあ未経験からどうやって試すのか、という話になりますが、まずは実際に勉強してみるのが第一歩です。テキストを読んでみたり、資格の勉強にトライしてみたりして、そもそもそれに興味を持てるか、面白いと思えるか、というのも参考になります。
一番いいのは、実際に手を動かしてみて、それを楽しいと思えるかどうかです。特にインフラ分野であれば、クラウドはそれほど高額なお金をかけずに実際に触れることができます。自分で環境を構築してみる、簡単なアプリケーションを作ってみるといったように、やりたいと思ったことを実現する方法を調べて、極力自分で手を動かしてみるといいと思います。
寺田: そうすれば、IT業界の中でも何が自分に向いているか見えてきますか?
永江: そうですね。それに対して自分が本当にワクワクできるか、楽しいと思えるかは人それぞれです。できるだけ実務に近い形で試せるといいですね。
寺田: ITインフラは、何かプロダクトがないと試せないのでは、と思っていましたが、違うんですね。
永江:クラウドであればパソコンとインターネットさえあれば自分で疑似的な環境を作れます。ただ、そこまでやれる人が多いかというと、そうではないかもしれません。
寺田:逆に言えば、それができる人は強いですね。
永江:未経験だけれども、それくらい自分でどんどん進められる人は、この業界や分野に向いている可能性がかなり高いと思います。
寺田: 以前、永江さんは「自分で勉強し続けられる人が向いている」ともおっしゃっていましたね。
寺田: 最後に小山さんにもお聞きしたいのですが、適齢や元々こういう業界にいた人が向いている、といった傾向はご自身の経験からありますか?
小山: まず適齢で言うと、絶対ではありませんが、チャレンジするのであれば遅いよりは早い方がいいと思います。違う業界の商習慣ややり方が長く身についていると、それを変えるのは難しいですよね。習慣を変えるには最低でも半年くらいはかかるので、なるべく変な癖がついていないうちに飛び込んできた方が順応はしやすいと思います。
もちろん、私が知っている人の中には、40歳近くで未経験からチャレンジして活躍している人もいますし、還暦を越えても現役でコードを書いている人もいるので、一概には言えませんが、早いに越したことはないかなと。
そして、どういう業界にいた人が向いている、というよりは、最近のエンジニアに求められるスキルセットの変化がポイントです。以前のようなスペシャリストとして黙々とコードを書くだけでなく、チームで協力しながら仕事を進めることが増えていますから、コミュニケーション能力が求められる傾向にあります。ですから人と関わる仕事をしてきた経験、例えばアルバイト経験でもいいのですが、そういった経験がある人は順応しやすいかもしれません。
技術力は、未経験だとどうしても経験者に比べて不利になりますが、その分をコミュニケーション能力など別の部分で補う、という総合力で戦うことができます。
技術力が高くてもコミュニケーションが苦手だと壁にぶつかりますし、逆もまた然りです。経験がない分、他の部分でどうカバーするか。そういった視点を持っている方が良いと思います。
寺田: 技術力を、何か他のスキルで補えるポジションがIT業界にもあるということですね。
小山: はい。ただ、過信は禁物です。技術を後回しにしていい、という話ではありません。エンジニアである以上、技術があってこそですが、未経験で最初はない状態からスタートするので、そこは必死に頑張らなければいけません。でも、「技術がないから全くダメ」というわけではなく、今まで培ってきた経験を活かせるところは必ずあります。
寺田: なるほど、希望が持てました。
6. クロージング
寺田: 未経験でも活躍できるビジョンが見えた気がしますが、永江さん、いかがでしたか?
永江: 誰もがなれるかと言うと正直そうではありませんが、能力が高く、強い興味を持っている方であれば、チャンスは十分にあると思います。
寺田: これを参考にしていただいて、IT業界を目指したいという方は、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
この番組はSpotify、Apple Podcast、Amazon Musicで配信中です。
ポッドキャストへのフォローとレビューもぜひお願いいたします。
番組へのご質問やリクエストは、専用フォームか、各種SNSから受け付けております。気になることがありましたら、ぜひお寄せください。


