2025/08/13
インフラエンジニアのホントのところ #14|未経験からインフラエンジニアになれるのか?採用と現場の本音
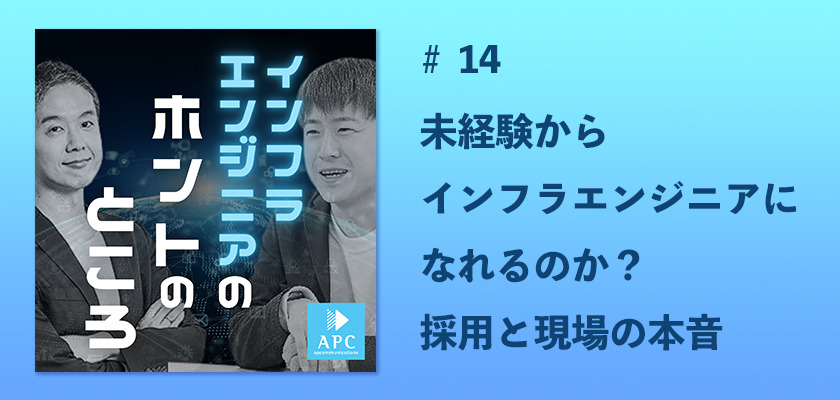
ITインフラって、「なんだか難しそう」「地味で大変そう」と思われがち。
でも実は、社会を支える根幹にある、とてもやりがいのある仕事なんです。
そんなリアルをお届けするPodcast 「インフラエンジニアのホントのところ」。
MCにはベンチャー女優の寺田有希さんを迎え、当社の副社長 永江耕治と採用責任者 小山清和が、現場・経営・採用の視点から語ります。
今回のテーマは「未経験からインフラエンジニアになれるのか?採用と現場の本音」。
「インフラエンジニアって、未経験でもなれるの?」
この疑問に、元エンジニアの経営者と採用責任者が本音で回答!
今業界が注目される理由、必要な資格や準備の進め方、会社選びにいたるまで、徹底的に解説します。
<目次>
1.オープニング
2.未経験者がインフラエンジニアを目指すメリット
3.未経験からの第一歩に必要なのは、事前の学習
4.業界に対する解像度を高めるには?情報収集の方法と注意点
5.会社選びのポイントと、自分を選んでもらうための準備
6.クロージング
1.オープニング
寺田:言葉は有名でも、何かと知らないことが多いインフラエンジニアの世界。キャリアや将来性、魅力など、ついつい隠れがちな「本当のところ」、インフラエンジニアのキャリアの真実を、業界のプロであるエーピーコミュニケーションズの永江さん、小山さんと共に徹底解剖していきます。
永江: エーピーコミュニケーションズの永江です。インフラエンジニア業界歴は23年以上で、現在は取締役副社長をしております。どうぞよろしくお願いいたします。
小山: エーピーコミュニケーションズの小山です。私は10年以上のIT業界での採用経験と7回の転職経験を活かし、現在は人事として採用責任者を務めています。当社では採用責任者をしています。よろしくお願いします。
寺田: そして、同じくMCを務めます、ベンチャー女優の寺田有希です。
さて、夏も本番ですが、巷では夏祭りやフェスなど色々ありますよね。インフラエンジニアの「フェス」や「祭り」のようなものはあるんですか?
永江: 「祭り」と呼ぶかは分かりませんが、毎年恒例の大きなイベントは結構あります。私たちが関わっているITインフラの分野で、当社も昔から毎年出展しているのが「JANOG(ジャノグ)」というイベントです。年に2回、だいたい1月と7月に開催されていて、毎回開催地が変わるのですが、今年は島根県で7月31日から8月2日にかけて開催されました。
寺田: お二人も参加されているんですか?
永江: 毎回ではありませんが、何回かは参加したことがあります。
寺田: こういうイベントは、行った方がいいのでしょうか?
永江: 行ったことがない方は、一度は行ってみるといいと思います。
技術発表があったり、企業が出展していたりして、すごく勉強になります。参加者限定の交流会もあるので、新しい出会いが生まれることもありますし、いいイベントだと思います。
寺田: 小山さんは何か注目のイベントはありますか?
小山: 6月から8月は、大手プラットフォーマーが大掛かりなカンファレンスを2~3日間かけて開催することも多く、盛り上がる時期ですね。当社も海外のイベントに参加したレポートを技術ブログで配信しています。
もう少し秋になると、インフラもやや関連する「東京ゲームショウ」もあります。ゲームにはインフラが大事で、「あのサービスの裏側は実はAWSが…」といった話もあったりします。新しいゲームの発表だけでなく、技術的な話を聞く目的で行っているエンジニアの方も結構いらっしゃると思いますよ。
寺田: そういう見方は面白いですね。
小山: ソーシャルゲームの裏側には必ず何かしらのインフラがあって、その基盤を支えている会社がありますからね。
2. 未経験者がインフラエンジニアを目指すメリット
寺田: 本日のテーマは「未経験でインフラエンジニアになるには」です。
前回の「未経験でもIT業界に転職できるって、ホント?」で、未経験でもIT業界への転職ができるということが明らかになりました。では、実際にどうすれば未経験からインフラエンジニアになることができるのでしょうか。そして、インフラエンジニアを目指すメリットはどこにあるのでしょうか。
まず、採用責任者をされている小山さんにお伺いします。今、インフラエンジニアを目指すメリットはどこにありますか?
小山: IT業界はこれからますます人材が不足することが明らかになっており、企業側も未経験者の採用を積極的に検討しています。その中でも特にクラウドエンジニアやセキュリティエンジニアなど、インフラエンジニアの領域に関わる人材のニーズは高まっています。
ですから、今は経験がなくても、そういった成長産業の中でビジネスパーソンとしてのキャリアを築いていけるチャンスがある、というのは非常に大きなメリットだと思います。
また、前回も触れたようにデメリットもありますので、「伸びているから大丈夫だろう」と安易に考えるのではなく、自分自身で正しい知識を身につけ、適切なポジションや会社を選ぶ必要はありますが、現状ではメリットの方が多いのではないでしょうか。
寺田: どういう仕事なのか、どれが自分に合うのか、どういう会社に入るべきなのか、何も考えずに入るだけではダメなんですよね。
小山: そうですね。入りやすくはなっていますが、入り口に入ったからといって、そのまま成長できるかは別問題です。その中で自分自身でサバイブしていかなければならない、という側面もありますので。
寺田: 業界のことを知って知識をつけた上で、自分を成長させることが大事。ただ、未経験者にとっての受け皿は広く、成長産業である、ということですね。
小山: はい、そうです。
3. 未経験からの第一歩に必要なのは、事前の学習
寺田: 次にご自身もインフラエンジニアとして23年以上の経歴を持つ永江さんにお話を聞いていきます。どうすれば未経験からインフラエンジニアになることができるのでしょうか?
永江: 事前に自分なりに学習しておくことが必要になります。何も知らず、特に準備もしていないけれど「入りたいです」というのは、ほぼ不可能に近いと思います。
寺田: 業務経験はなくても、例えば自分で触ってみたことがある、といった何かしらの経験は必要ということですね。
永江: 「実務経験はないけれども、勉強をしていて、ある程度の知識はあります」ということを証明できる何かがある方が望ましいです。
寺田: それはどういったものが証明になりますか?
永江: 一番分かりやすいのは、やはり資格ですね。
特に経験がなく、新卒でもない、というタイミングであれば、ITに関する知識を習得できることを証明するためにも、例えば「基本情報技術者試験」や、インフラで言うとネットワークのciscoの資格である「CCNA」、クラウドであれば「AWS認定資格」などを持っていることはプラスに働きます。
寺田: 専門的な資格というよりも、全体的な知識を網羅しているような資格の方が望ましいのでしょうか?
永江: そうとも限りません。
「基本情報技術者試験」はITの基礎知識を証明するのにすごく良い試験なので、持っていた方が良いと思います。ただ、この試験は簡単ではないので、例えばネットワークの仕事をしたい人は「CCNA」を取得して業界に入ってくる方もいますし、クラウドであればAWSの資格を持って入ってくる方もいます。
寺田:やりたい分野が決まっているのであれば、そういった専門的なものを取得するのが良いと?
永江:そうですね、何をやりたいかによって変わってきますね。
4. 業界に対する解像度を高めるには?情報収集の方法と注意点
寺田: 事前にどういった準備ができるか、という点で考えると、まずはどの分野に進みたいかを探す、ということになりますかね。
永江: そうですね。まずは何をしたいのか、業界のこと自体を知る必要があります。
寺田: この番組でも、分野が細分化されていて専門知識も多岐にわたる、というお話がよく出ますよね。
永江: まずはどういう業界であるか、そして技術領域だけでなく、「技術の工程」があるということも知る必要があります。
寺田: 工程、ですか。
永江: システムを作る場合、要件定義、設計、構築、運用といった流れになります。その運用のフェーズでも技術的に高いレベルが求められる仕事もあれば、オペレーションに近い仕事もあります。技術の幅も、工程の幅も、そして求められるレベル感もそれぞれ違うんです。
寺田: そこを正しく理解しておくことが大事なんですね。
永江: そうです。どこから入って、どこに行きたいのか。完全に把握するのは難しいですが、業界に対する解像度が高ければ高いほど、業界に入りやすくなりますし、具体的に何を準備すればいいかも見えてきます。
寺田: 未経験だと、その知識を得ること自体が難しそうです。どうやって勉強すればいいのでしょうか?
永江: いろんな手段があります。
一つは、インターネットを活用して独学する方法です。ブログやYouTube、SNSなど、今は情報がものすごくたくさんあります。ただ、情報が多すぎるゆえに、どの情報が良い情報なのか、その見極めが難しくなるという側面もあります。
寺田: その見極め力、磨きたいですね。
永江: 自身でできる方もいますが、人から教えてもらうことも有効です。
寺田: 現役のエンジニアの方から情報をいただく、ということですね。
永江: 業界経験者から聞くのもいいですし、今はビジネスとしてスクールや人材紹介業をされている会社もあるので、そういったところから情報を得るのも一つの方法です。
ただその場合は、その人たちが皆さんからどういうメリットを得るのか、という仕組みを考えることも大事です。
寺田: それはどういうことでしょう?
永江: ビジネスとしてやっている方が発信する情報の場合、全て信用できるとは限りません。その人たちがどういう仕組みでお金を得ているのかを考える必要があります。例えば、スクールなら入学してもらうこと、人材紹介ならどこかの会社に入社してもらうことがゴールになっている場合もあります。
もちろん、エンジニアになろうとしている方のキャリアを真摯に考えてくれる会社や担当者もいますが、そこを見極めなければいけません。
寺田: それは難しいですね。
永江: あるいは、直接信頼できる人から教えてもらう、という手もあります。
寺田: それが一番良さそうに聞こえますね。
永江: それは関係性次第です。関係性が強くないのに「私のためにあなたの時間をたくさん割いて、調べて教えてください」となると、相手にメリットがありません。
寺田:いずれにせよ、まずは自力で調べるというスタンスが必要ですね。その姿勢があって初めて、助けてくれる人も現れるかもしれません。他人任せだけではダメ、ということですね。
永江: そして、誰かに頼る時は、その人に対する想像力が必要です。その人がどういう人で、その人の時間を使わせてもらうということを想像する力も必要だと思います。
5. 会社選びのポイントと、自分を選んでもらうための準備
寺田: 分野を選び終わった後、どの会社に入るかという判断も必要です。会社選びのポイントはどこでしょうか?
永江: 未経験者という前提でお話しすると、まず「未経験者をどれくらい受け入れている会社なのか」という点があります。
その上で、私個人の観点ですが、エンジニアのことと、その会社がサービスを提供しているお客様のこと、その両方を真摯に考えている会社が良いと思います。どちらかに偏っていると、結局レベルの高い仕事はできません。この両立はすごく難しいことですが、それができている会社は、きちんとした会社だと思います。
寺田: 両立できているかどうかを、こちら側が見極める方法はありますか?
永江: 応募して面接まで進んだ際に、面接官の方に、ビジネスについてどれだけしっかり考えられているか、逆に質問してみることです。
ただ、そのためには応募者側にもある程度のビジネススキルがないと難しいでしょう。結局のところ、何かを見極めるには、それに見合うだけの深い考えや洞察力を磨く意識がないと難しい、ということです。
寺田: では、専門分野を見極める力と、会社を見極める力、その両方を伸ばすことが、未経験で転職を目指す上でのスタート、ということですね。
永江: そしてこれは、未経験だからできない、ということではありません。未経験でも、こういうことができている人は活躍できる人なんです。
準備もせず、深く考えられていない方は、そもそも良い会社に入るのが難しい。逆に未経験でも、それだけベースがしっかりしている人は、良い会社とのご縁が生まれやすいですし、入社後も活躍する確率が高いと思います。
寺田: なるほど。経験の有無ではなく、スタートラインに立てていないから難しいんですね。
では最後に採用責任者の小山さんにもお聞きしたいのですが、エーピーコミュニケーションズも未経験で転職することは可能ですか?
小山: はい。「未経験」の定義にもよりますが、これまで永江さんが話してきたような準備ができている方であれば、可能性はあります。
やはり、その職種になるために事前に意欲を示すことが大事です。重要なのは、採用担当者の視点に立ち、「この人ならぜひ採用したい」と思ってもらうにはどうすれば良いかを考えることです。経験者は過去の実績がスキルの証明になりますが、未経験の方は、その職種に就きたいという意欲をご自身の行動で証明する必要があります。
例えば、当社の採用ページで求める人物像を理解した上で、ただ「頑張ります」と伝えるだけでなく、資格取得やスクールでの学習といった、努力を裏付ける具体的な「エビデンス」を示していただきたいです。
当社には、過去に経験の浅い状態で入社し、活躍している社員が実際にいます。だからこそ私たちはポテンシャルを信じていますが、そのポテンシャルを「信じさせてほしい」。それを示すことが、未経験からの転職では特に求められると思います。
寺田: 自分を採用するメリットを、必ず用意しておかなければいけないんですね。
小山: そして、ただ資格を持っていればいいというわけではなく、当社のビジネスモデルや事業領域を見た時に、どういった資格を持っているとアピールになるだろうか、と考えることも大事です。他の会社を受ける場合も、その会社が注力している分野の資格や実績があった方が、採用したいという気持ちは高まります。
寺田: 資格やキャリアパスの考え方については過去の放送でもお話しいただいていますので、そちらも参考に、皆さんぜひ自分をアピールできることを見つけていただけたらなと思います。
6. クロージング
寺田: 今回もありがとうございました。いやぁ、深かったですね、永江さん。
永江: そうですね。未経験の方が聞きたい内容だったかというと、もしかしたら「こんなことは聞きたくなかった」という方もいるかもしれませんね。
寺田: 耳も心も痛いかもしれないですね。
永江: でも、人材紹介会社やスクールの方がよく言う話とは違う話をすることに、このポッドキャストの価値があるかなと思っていますので。
寺田: 耳の痛いことに向き合える方が、きっとお二人がおっしゃるように伸びる方なのかな、と思いました。
永江: 本当にめちゃくちゃ活躍できる人はいるんです。でも、そういう人は、やはりそれだけの準備や考え方ができている人なんですよね。
寺田: 小山さん、言葉にしてみていかがでしたか?
小山: 私自身も未経験から人事の世界に飛び込んだ時は大変でしたし、その後、経験を積んで転職する時も苦労したので、キャリアは難しい部分があるなと、自分の経験と重なる部分もありました。
ただ、私は「人の可能性に向き合える人事でいる」ということを大事にしているので、こうして話したからには、それを実践しなければと、自分にプレッシャーをかける意味でも話しました。人の可能性を信じて、採用に向き合っていきたいと改めて思いましたね。
寺田: 素晴らしい回答ですね!小山さんがどうやって異業種転職を叶えたのか、その大変だった話も今後ぜひお聞きしたいです。
小山: めちゃくちゃ大変でしたけどね(笑)。
寺田: その話、参考になりそうです。ぜひお願いします。
この番組はSpotify、Apple Podcast、Amazon Musicで配信中です。
ポッドキャストへのフォローとレビューもぜひお願いいたします。
番組へのご質問やリクエストは、専用フォームか、各種SNSから受け付けております。気になることがありましたら、ぜひお寄せください。


