2025/08/27
インフラエンジニアのホントのところ #16|インフラエンジニアはリモートワークが叶うのか?
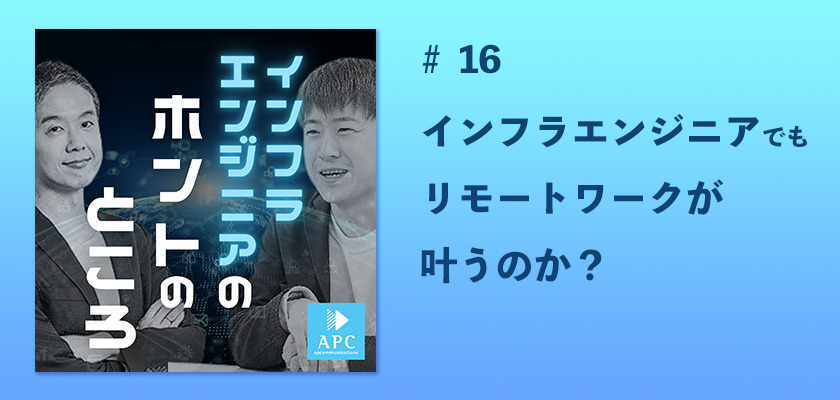
ITインフラって、「なんだか難しそう」「地味で大変そう」と思われがち。
でも実は、社会を支える根幹にある、とてもやりがいのある仕事なんです。
そんなリアルをお届けするPodcast 「インフラエンジニアのホントのところ」。
MCにはベンチャー女優の寺田有希さんを迎え、当社の副社長 永江耕治と採用責任者 小山清和が、現場・経営・採用の視点から語ります。
今回のテーマは「インフラエンジニアはリモートワークが叶うのか?」。
出社のイメージが強いインフラエンジニアでも、リモートワークは叶うのか!?
その実態はもちろん、必要なスキルやマインド、求人のリアルに至るまで、元エンジニアの経営者と採用責任者が、徹底解剖していきます。
<目次>
1.オープニング
2.インフラエンジニアのリモートワークは叶うのか?
3.エーピーコミュニケーションズにおけるリモートワークの実態
4.リモートワークを叶えるために必要なスキルと人物像
5.「リモートOK」求人の実態と会社選びのポイント
6.クロージング
1.オープニング
寺田: 言葉は有名でも、何かと知らないことが多いインフラエンジニアの世界。キャリアや将来性、魅力など、ついつい隠れがちな「本当のところ」を、業界のプロであるエーピーコミュニケーションズの永江さん、小山さんと共にインフラエンジニアのキャリアを徹底解剖していきます。
永江: エーピーコミュニケーションズの永江です。インフラエンジニア業界に23年以上携わっており、現在はエーピーコミュニケーションズで取締役副社長をしています。どうぞよろしくお願いいたします。
小山: エーピーコミュニケーションズの小山です。私は10年以上のIT業界での採用経験と7回の転職を通じてキャリアを形成してきた人事です。エーピーコミュニケーションズでは採用責任者をしています。よろしくお願いします。
寺田: そして、MCを務めます、ベンチャー女優の寺田有希です。さてさて、お二人は今日もご自宅からですか?
永江: そうです、自宅からです。
小山: 私も同じく自宅からです。
寺田: 在宅ワークも多いかと思いますが、効率よく仕事をするための工夫やこだわりなどはありますか?
永江: そうですね。オンラインだとミーティングがたくさん入れられてしまうので、良い側面もあるとは思うのですが、以前よりミーティングの数がかなり増えてしまいました。
ですから、例えば資料作成の時間などをあらかじめスケジュールで確保しておかないと、一日中ミーティングが何日も続くという形になってしまいます。ある程度、自分の作業時間を確保するようにしています。
寺田: ミーティングが増えたというのは、永江さんご自身のことですか? それとも世の中の流れとしてでしょうか?
永江: まずは私自身がすごく増えました。他の方からも、そういった話はよく聞きますね。
オンラインミーティングは30分単位で入れることができますし、会議室を確保する必要もないので、集まりやすくなっている面もあるのかなと思います。
寺田: 小山さんはいかがですか?
小山: 私はずっと座って仕事をしていると、股関節が硬くなるなど、体に支障が出てしまいました。特に初期の頃は、それが原因で一度体を壊してしまいました。以来、色々と工夫していて、実はデスクの下や脇には筋トレグッズやEMSマシンが置いてあります。仕事をしながら足の裏をほぐしたり、鍛えたりしています。
寺田: そんなことをしているんですか?
小山: 実はそうなんです。他にも握力を鍛える器具もあって、考え事をしながらそれを握ったり、チューブのようなものを使って、座りながら股関節周りの筋肉を鍛えたりしています。もちろん仕事に支障が出ない範囲でですが。
寺田: アスリートですね。
小山: いえいえ。でも座って仕事を続けていると、仕事が終わった後に股関節の硬さやお尻の痛みを感じます。良い椅子に座っていても限界がありますね。
寺田: きっと多くの方は、体が硬くなりすぎて、そのことにさえ気づかないのだと思います。小山さんは日頃から運動をされているから、敏感にその違いを感じるのでしょうね。小山さんのように体を動かしておくのは大事ですね。
小山: ちょっと、「本当にちゃんと仕事しているのか?」と永江さんに思われたのではないかと心配になりましたが…(笑)。仕事はちゃんとしていますので、自己フォローしておきます。
2. インフラエンジニアのリモートワークは叶うのか?
寺田: 本日のテーマは「インフラエンジニアはリモートワークが叶うのか」です。開発エンジニアはリモートワークができるけれど、インフラエンジニアは毎日出社しなければいけない、そんな常識もかなり変わってきているようです。
とはいえ100%ではありません。どうすれば叶うのか、リモートワークの可能性や目指す方法、必要とされるスキルなどを徹底解剖していきたいと思います。
まずは一般論として、採用責任者もされている小山さんにお聞きしたいのですが、現在、インフラエンジニアのリモートワークは一般的に叶うものなのでしょうか?
小山: 結論から言うと「叶います」。これまでの回でも少し触れましたが、昔のインフラエンジニアは物理的な対応が必要だったので、リモートワークとは縁遠かったと思います。
しかし最近は、クラウドの普及はもちろん、インフラをコードで管理できるようなツールも次々と生まれてきました。もちろん、緊急時など物理的な対応が必要な場合もありますが、それ以外の時は在宅でも仕事ができるようになってきています。当社でも週1回以上リモートワークをしている社員が92%おり、圧倒的にリモートで働く人の方が多いです。
数年前と比べると大きく変わったと思いますね。
寺田: 実際に、リモートワークが可能な案件数も増えているということですよね。
小山: そうです。「リモートOK」という案件が増えています。ただ、これは会社のスタンスにもよると思います。
そういった案件を基本的には請けない方針の会社もあれば、積極的に請ける会社もあります。クライアントワークの場合はお客様の意向もあるので、全てをコントロールできるわけではありませんので、取引先企業のリモートワークに対する考え方も影響してきます。
3. エーピーコミュニケーションズにおけるリモートワークの実態
寺田: 次に、エーピーコミュニケーションズさんについてお聞きしたいと思います。経営者でもある永江さん、現在、リモートワークが可能な案件はどのくらいあるのでしょうか?
永江: 当社で言うと、約8割の社員がほぼリモートワークです。残りの1割が半分程度の出社、もう1割がほぼフル出社という割合です。何らかの形でリモートワークをしている社員は9割にのぼります。
これは昔からではなく、コロナ禍以降、2020年から急激にこの形に変わりました。それ以前は、ほとんどリモートワークをしていませんでした。
2020年の2月か3月頃から急に切り替わり、現在に至るまで約5年半が経ちますが、その間に社員数は350名から480名ほどに増えました。リモートワーク率の割合は変わっていないので、案件数自体が増えているということになりますね。
寺田: リモートワークといっても、東京近郊に住んでいて必要に応じて出社する方と、完全に地方にお住まいの方とでは大きく違うと思うのですが、その点はいかがですか?
永江: それに関してもコロナ禍以降に変わりました。私たちは東京にしかオフィスがないので、コロナ禍前は社員は東京近郊に住んでいる人のみでした。しかし現在は、北海道から沖縄まで、様々な場所に住んでいる社員がいます。関東圏以外に住んでいる社員は70名を超え、全体の15%前後になっています。
寺田: そのように完全にフルリモートを叶えている方々は、どのようにお仕事をされているのですか?
永江: 基本的に、ほとんどの社員がリモートでの仕事をしています。これができるようになった大きな要因は、やはりクラウド化がかなり進んできたことだと考えています。
もちろん、一部、現地で作業をしなければいけない場面がゼロになったわけではありません。ただ、常時それをしなければいけないわけではないので、結果として8?9割の社員がリモートで業務を遂行できています。特にクラウド関連の仕事が多くを占めるようになり、リモートワークが成立するようになったという状況です。
寺田: やはり鍵はクラウドなのですね。
永江: そうですね。そこが非常に大きく影響していると思います。
4. リモートワークを叶えるために必要なスキルと人物像
寺田: ではここからは、実際にどうすればリモートワークを叶えていけるのかを考えていきたいと思います。まず永江さん、リモートワークが叶いやすい分野というと、やはりクラウドになるのでしょうか?
永江: そうですね。オンプレミスの仕事になると物理的な機器を扱うため、どうしても現地に行かないとできない作業が発生します。そう考えると、やはりクラウドの割合が多い仕事の方が、リモートワークはしやすいですね。
寺田: そうなると、どのようなスキルや経験があればリモートの案件を任されやすいのかが気になります。やはりクラウドの知識と経験は必須でしょうか?
永江: 必須になってきますね。
ただ、クラウドを扱う前提として、基本的なネットワークやサーバーの知識が必要になります。その知識が不要になるということはありません。その上で、AWSやAzure、OCIといった、いわゆるパブリッククラウドに関するスキル、知識、経験が求められます。
寺田: クラウドの知識だけではダメなのですね。
永江: そうですね。クラウドを理解するということは、基本的にインフラの知識が必要になる、ということです。
寺田: では、必要なスキルとしては、インフラ全般のスキルと、その上でのクラウドのスキルということですね。他にもありますか?
永江: リモートワークを実現するためには、という観点ですと、前回の「エンジニアのフリーランス」の話と少し共通する部分ですが、「自律的に仕事ができる」ということが非常に重要になります。
対面で会うことが難しい環境では、一人で仕事を完結できるスキルがないと厳しいです。当社の地方在住の社員に関しても、完全に未経験で、まだエンジニアとして独り立ちできていないという方にはリモートワークを認めていません。
採用の場面においても、当社はキャリア採用、つまり経験を積んだ方の採用が多いのですが、その中で地方在住の方の面接においては「自律的に仕事を進められるかどうか」を非常にシビアに見ています。そのスキルは必須です。
そういう人であれば、リモートワークが可能と言えると思います。
寺田: スキルももちろん大事ですが、どのような人がリモートワークの案件を任せてもらいやすいのでしょうか?
永江: まず大前提として、その仕事で求められる最低限の技術知識やスキルを持っていることが必要です。
その上で、リモートでのコミュニケーションになるので、例えばテキストでのコミュニケーションがしっかり取れることが重要です。自分の意見や質問をきちんと文章にできる、ドキュメントにまとめて他の人に伝えることができる、といった基本的なスキルが非常に大切になります。
また、必要に応じて自分から相談や質問ができることも重要です。待っているだけではリモートでの連携は難しくなります。
寺田: コミュニケーションスキルというか、チームで仕事ができる力、というところでしょうか。
永江: まさにその通りだと思います。
寺田: あとは、緊急時には、出社できる東京近郊の方に任せなければいけない場面も出てきますよね。
永江: そういうケースはありますね。
寺田: そうなると、「この人が地方で頑張っているなら、自分が出社しよう」とチームメンバーに思ってもらえるような関係性も大事になってくるのでしょうか。
永江: そうですね。チームの中に、地方に住んでいるメンバーがいるケースはよくあるのですが、その中で、東京での作業やお客様への対面での説明などが発生した場合、一部のメンバーにお願いすることになります。
そういった際に、お互いにリスペクトし合えるような日頃の仕事ぶりや、感謝を伝えること、自分は現地に行けない分、別のところで貢献するといった姿勢が、チームを円滑に機能させる上で非常に大事だと思います。
寺田: では、リモートワークを叶えたいと思っている方は、これまでお話しいただいたスキルや人物像を意識して、コツコツと実績を積み重ねておくことが大事ですね。
永江: そうですね。そして何より、きちんと「貢献する」ということです。「一生懸命やっています」ではなく、その人が何に対して、どのように、どれくらい貢献しているのか、その価値をきちんと発揮することが大事だと思います。
スキルはあくまで手段であり、成果を出すことができる人であれば、働く場所はそれほど問われなくなってきます。
寺田:誰でもできるわけではなく、やはりスキルと成果が求められますね。
5. 「リモートOK」求人の実態と会社選びのポイント
寺田: では最後に、採用の実態について、採用責任者の小山さんにお聞きします。業界全体として、求人に「リモートOK」と書かれていても、実態は違ったという話を見聞きすることがあるのですが、これは本当なのでしょうか?小山: これは本当にある話です。例えば、面接の時点では「リモートOK」だったけれど、内定が出て入社するタイミングになったら「リモートはなくなりました」というパターンなどがあります。
寺田: そのレベルであるんですね。求人サイトの記載が違う、というレベルかと思っていました。
小山: 入社するまでに会社の方針が変わってできなくなった、というケースですね。「それなら入社しなかったのに」という話を聞きます。
最近、有名なテック系の会社やコンサルティングファームなどで「出社回帰」の流れがあり、「基本的には全員毎日出社してください」となったり、グループ会社に買収されたことで、元々はリモートだったのに出社必須になったり、という話もあります。ひどいケースでは、そもそもリモートワークの制度がないのに、「リモートOK」と嘘を書いて募集している会社もあったりします。
寺田: そんなことまであるんですか?
小山: ありますね。面接の中で、そういった経験をされた方のお話を聞くこともあります。世の中には、とんでもない会社があるものです。これはリモートに限らずの話で、「正社員だと思って入社したら、試用期間中は正社員ではなかった」とか、聞いていた話と違うといったことは、よく聞く話です。
寺田: だとしたら、きちんとリモートワークを叶えたい人は、正しい会社を選ばなければいけません。会社選びについて、どのように考えればよいでしょうか。
小山: これは一種のトレードオフだと思います。会社に対して自分がどう貢献できるか、という点も含めて考えるべきです。
フルリモートで働くことを前提に会社を探す気持ちは理解できますが、中には「リモートさえできれば会社はどこでもいい」というような方もいらっしゃいます。けれど、我々としては、まず企業に興味を持っていただき、自分がどう貢献できるかを伝えていただいた上で、「ただ、家庭の事情などでこういう働き方を希望します」などと伝えていただくのが良い流れだと考えています。
いきなり「フルリモートができるから御社を選びました」と言われても、気持ちは分かりますが、少し戸惑ってしまいます。
我々は、事業を成長させてくれる仲間を求めています。そして、その仲間が安心して働けるようにするための一つの手段として、リモートワークという制度を導入しています。リモートワークが目的として先にあるわけではないのです。
事業の成長があり、そのために従業員が安心してコミットできる環境を整える、という順番です。ですから、まずは自分がどう貢献でき、どんな価値を提供できるのかを伝え、その上で希望を伝える、という方が、お互いにとって良い関係を築きやすいと思います。
寺田: どれだけ貢献できるかを考え、そこをアピールすることが大事なのですね。
小山: そこは感じますね。リモートで活躍している人ほど、スキルレベルも高いという相関関係はあるように思います。因果関係とまでは言えませんが、フルリモートで働いている人とスキルのレベルには、関連がありそうです。
寺田: 最後に、エーピーコミュニケーションズさんでは、最初からフルリモートを希望して、それが叶うことはあり得るのでしょうか?
永江: あります。特に地方にお住まいの方は出社が難しいので、出張ベースでの出社はありますが、ほぼフルリモートに近い形になります。東京近郊に住んでいる社員でも、リモートの割合が非常に高い人は多いので、現状では出社頻度はかなり少ないですね。
寺田: では、初めからその希望も通りやすいのですね。ただ、やはりそこには貢献が伴わなければいけない、と。
永江: はい、その通りです。もちろん、環境としては整っていますが、「活躍するつもりがある」「活躍する意思がある」という大前提が非常に大事です。その上で、会社として優秀な方々により良い環境を提供していく、というスタンスです。
6. クロージング
寺田:リモートワークはすごく魅力的ですが、その前提を履き違えないように考えなければいけませんね。
永江: そうですね。
小山: あと、健康被害もありますからね。「リモートワークをするようになってから、体が痛くなった」という人は周りにも増えています。座りっぱなしで移動が減ることによる腰痛や筋力低下など、病気がちになる人も意外と多いです。
働きやすいから健康でいられるかというと、それは全く別の話だなと個人的には感じています。
寺田: 通勤すると、嫌でも歩きますからね。
小山: そうなんです。階段をヒーヒー言いながら登っていたのが、いかに体にとって大事だったのかと気づかされます(笑)
寺田: スキルや貢献度だけでなく、健康もトレードオフに含まれるのですね。
小山: 5年くらいリモートワークを続けていると、健康面で失うものも意外とあるなと感じます。
寺田: 確かに。その点も皆さん、ぜひ参考に考えてみてくださいね。
この番組はSpotify、Apple Podcast、Amazon Musicで配信中です。
ポッドキャストへのフォローとレビューもぜひお願いいたします。
番組へのご質問やリクエストは、専用フォームか、各種SNSから受け付けております。気になることがありましたら、ぜひお寄せください。


