2025/09/03
インフラエンジニアのホントのところ #17|インフラエンジニアが年収を上げる方法
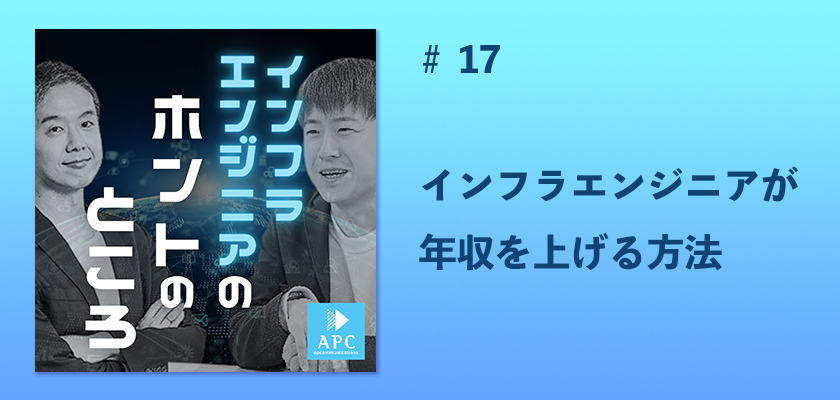
ITインフラって、「なんだか難しそう」「地味で大変そう」と思われがち。
でも実は、社会を支える根幹にある、とてもやりがいのある仕事なんです。
そんなリアルをお届けするPodcast 「インフラエンジニアのホントのところ」。
MCにはベンチャー女優の寺田有希さんを迎え、当社の副社長 永江耕治と採用責任者 小山清和が、現場・経営・採用の視点から語ります。
今回のテーマは「インフラエンジニアが年収を上げる方法」。
「転職」だけじゃない!
年収アップに直結するスキルや、選ぶべき会社の探し方まで、「年収を上げるにはどうすれば…?」という疑問に、元エンジニアの経営者と採用責任者が本気で答えます。
<目次>
1.オープニング
2.インフラエンジニアの平均年収と市場の実態
3.年収アップにつながる重要ポイント!
4.年収が上がりやすい会社の選び方
\\\
\\\
1.オープニング
寺田:言葉は有名でも、何かと知らないことが多いインフラエンジニアの世界。キャリアや将来性、魅力など、ついつい隠れがちな「本当のところ」を、業界のプロであるエーピーコミュニケーションズの永江さん、小山さんと共にインフラエンジニアのキャリアを徹底解剖していきます。
永江: エーピーコミュニケーションズの永江です。インフラエンジニア業界には23年いて、現在はエーピーコミュニケーションズで取締役副社長をしております。どうぞよろしくお願いいたします。
小山: エーピーコミュニケーションズの小山です。私は10年以上のIT業界での採用経験と7回の転職を通じてキャリアを形成してきた人事です。当社では採用責任者をしています。よろしくお願いします。
寺田: MCを務めます、ベンチャー女優の寺田有希です。さて、今回は私がすごく聞きたいことを、お2人にお聞きできたらと思うんですけれども。お勧めする「最強のAI」は何でしょう? IT業界の第一線で活躍されている方々が、どんなAIを使っているのか知りたいと思いまして。
永江:『 X(旧Twitter)』や『YouTube』などで日々色々な情報を見ていますが、一時期は『ChatGPT』が優勢だったのが、『Gemini』が追い抜くなど、優位性が数日単位で目まぐるしく変わるようなイメージですね。ですので、「何が最強か」という問いへの答えは、その時々で変わっていく印象です。
当社ではGoogleの『Gemini』を全社で使える環境にしているので、必然的に使う機会が多いですね。そして最近の『Gemini』は、以前と比べて格段に良くなっていると感じます。小山さんはどうですか?
小山: そうですよね。一時期は本当に『ChatGPT』、通称「チャッピー」が良いという話が多かったですが、最近は『Gemini』を使っている人の方が多い印象です。
『X』を見ていても、画像生成などで「こんなものができました」と投稿している方が増えていて、直近でアップデートがあったのだと思いますが、その精度の高さを感じます。外部の方々の反応からも、性能が上がっていることが伝わってきますね。
寺田: 業務にも活用されているのですか?
永江: エンジニアはもちろんですが、エンジニアでなくても、例えば人事の小山さんも使っていますよね。
小山: はい、チーム内で使っているメンバーもいますし、会社全体としてエンジニア以外のメンバーも活用しています。
永江:当社はオンラインミーティングなどもGoogleのツールを使っているのですが、会議は基本的に動画で録画して、AIが自動で議事録を取ってくれます。勝手に要点をまとめてくれたりもするので、その辺りは以前より格段に楽になりました。長い会議でも、かなり正確に議事録を取ってくれますね。
「誰がどう発言したか」という話者分離も正確です。具体的に私が活用している例を挙げますと、経営会議などでファシリテーションをする機会が多いのですが、その振り返りに使っています。
自分で作った振り返りのフォーマットがありまして、ファシリテーターとしての評価項目が11項目ほどあります。そのフォーマットをテキストで用意しておき、「この観点で評価してください」とGeminiに指示を出すと、議事録の全発言を分析して、「ここはできていた」「ここはできていなかった」といった評価レポートを自動で作成してくれます。
寺田: それは全て『Gemini』で行っているのですか?
永江: そうです。プロンプト自体は自分で作りますが、一度作ってしまえば、使い回せますから。
寺田: プロンプトが重要なんですね。いかにプロンプト力をつけるか、ということですね。
永江: 結構長いプロンプトを用意しています。
寺田: 今度ぜひ、プロンプトの作り方を教えていただきたいです。
永江: はい、また別の機会にぜひ!
2. インフラエンジニアの平均年収と市場の実態
寺田:本日のテーマは「インフラエンジニアが年収を上げるには」です。
働き方ややりがいももちろん大事ですが、やはり年収も大事ですよね。インフラエンジニアが年収を上げたいと思った時、どんなことを考え、何をすればいいのでしょうか。転職事情や評価されやすい分野、身につけるべきスキルや考え方まで、徹底解剖してまいります。
寺田: それではまず、採用責任者の小山さんと共に、現在の市場をチェックしていきたいと思います。今のインフラエンジニアの平均年収は、どのくらいなのでしょうか?
小山: 統計によって多少の違いはありますが、厚生労働省が出している「job tag(ジョブタグ)」という統計によると、全国の平均年収は752万円です。ただ、これは平均年齢が41.4歳での数字なので、若干年齢が高い層に引っ張られている可能性はあるかと思います。 実態としては、おそらく600万円台の中盤から後半くらいが現実的なラインではないでしょうか。
また、これは全国平均なので、東京都内など産業が集中している場所では、もう少し高くなる傾向があると思います。
寺田: それは、この業界の年齢層が高いということではなく、調査対象の年齢層が高かったということでしょうか?
小山: その可能性はあると思います。この統計の平均年齢は、当社の平均年齢と比べても5?6歳高いです。大企業の平均年齢が40代前半から中盤くらいになることが多いので、統計を取った会社の規模感などの影響で、少し年齢層が高めに出ているのかもしれません。
寺田: 「20代」「初任給」というと、どのくらいになりますか?
小山: 例えば、新卒から2年目くらいの20代前半ですと430万円強となっています。全産業の平均年収が530万円程度だったと思うので、20代の中盤から後半で500万円台に達するこの業界は、高い水準にあると言えます。
ただ、実際には年齢よりもスキルが大きく影響します。この「job tag」では、スキルレベルが大きく4段階に分けられていまして、エントリーレベルからジュニア層で400万円前半から600万円、ある程度できるようになったミドル層で400万円中盤から700万円、一人で業務を完遂できるシニア層で500万円から700万円後半、そしてスペシャリストレベルになると600万円から1,000万円近くまで、という分布になっています。
寺田: スキルを磨いて上を目指せば、年収1,000万円以上も狙えるのですね。
小山: 狙えます。スキルをしっかりと向上させれば、年収も上がっていく可能性が高い分野だと言えるでしょう。もちろん、どの会社に入るか、どこに住んでいるかという要素も影響しますが。
3. 年収アップにつながる重要ポイント!
寺田:ここからは、元エンジニアで現在経営者をされている永江さんと共に、エンジニア目線で切り込んでいきたいと思います。まずは1つ目の質問です。
【質問1】「年収を上げやすい分野やスキルとは何なのでしょうか?」
永江: 非常にシンプルなルールがあります。それは「需要が大きく、供給が少ない」分野である、ということです。例えばクラウドの中で最も有名なAWSは、需要が非常に大きいですが、目指す人も多いため、供給、つまりエンジニアの数もかなり増えています。
ですから、AWSを目指すのも一つの道ですが、需要は大きいものの競合となるエンジニアも多いという状況です。時代の流れに合わせて、他のベンダーの資格を取得するといった選択肢も考えられます。
寺田: 需要があっても、供給が増えすぎてしまうと、自分の価値を高めづらくなるということですね。
永江: そうですね。以前は持っているだけで希少価値があった資格も、保有者が増えるにつれて価値は上がりづらくなります。
一方で、非常に希少性はあっても、需要があまりない技術というのもあります。誰も知らないような難しい資格を持っていても、その仕事自体がなければ年収には繋がりません。そこにお金を支払うお客様がいないと、ビジネスとして成立しないということですね。
寺田: 「需要と供給のバランス」を常に読んでいく必要があるということですよね。
永江:そうですね。今、その技術が成熟しすぎていないか、といった視点は年々変わっていくので、アンテナを張り続けることが重要です。
寺田: その情報は、どうやってチェックすればいいのですか?
永江: 一つはインターネットで調べることですが、よりリアルな情報を得るなら、多くのお客様と接点があり、市場の動きを肌で感じている人に話を聞くのが良いでしょう。例えば、SIerで働く人などです。
なかなか直接会うのは難しい場合は、『YouTube』や『X』などで情報を得ることもできます。ただし、その情報が本当に正しいかどうかの見極めは必要になります。
寺田:次に2つ目です。
【質問2】「転職しなければ年収は上がらない」といった記事をよく見かけるのですが、これは本当なのでしょうか?」
永江: 必ずしもそうとは言えません。どの会社に所属し、どんな仕事をしているかによります。もちろん、特に若いエンジニアの方にとっては、転職が年収アップのきっかけになるケースは多いです。しかし、社内でしっかりと評価されれば、同じ会社にいても年収を上げていくことは十分に可能です。
寺田: 3つ目です。
【質問3】「社内で評価を上げていくために、評価に繋がりやすいスキルはありますか?」
永江: 皆さん技術スキルに注目しがちですが、それは持っていることが前提です。その上で、マネジメントスキルや、広い意味でのコミュニケーションスキルといった、技術以外のスキルを持っているかどうかが、評価に大きく影響します。
寺田: この番組でも「コミュニケーションスキル」は頻出ワードですが、やはり大事なのですね。
永江: 非常に大事です。何よりも、お客様の課題を解決できるかどうかが重要ですので、技術力はもちろん、そういったビジネス視点やリーダーシップを持っている人は、数が少ないため評価に繋がりやすいです。
寺田: 聞いていると、多岐にわたるスキルが必要で難しそうに感じます。
永江: そこも先ほどの「需要と供給」の原則と同じです。
技術力があり、かつマネジメントやビジネスの視点も持つ、そういったバランスの取れた人材は、企業が非常に欲しがる一方で、数が極端に少なくなります。だからこそ、高い報酬が支払われるのです。
もちろん、技術一本で突き抜けるという道もありますが、年齢を重ねても市場から求められ続けるほどの技術力を維持するのは、相当な努力が必要です。ご自身の特性に合わせて、スキルを組み合わせることで希少性を出すのか、一つの道を極めるのか、戦略を考えることが有効です。
寺田: では4つ目です。
【質問4】「年収を上げようと思うと、資格の取得が真っ先に思い浮かぶのですが、資格は年収アップに繋がりますか?」
永江: はい、年収アップに役立つ場合が多いです。特に、まだ年収が高くない若い方ほど有効な手段になります。
もちろん、ある程度の年齢になっても、資格がないよりあった方がプラスに働きます。ただ、どれくらい効果があるかは、その方の現在の年収や年齢によって変わってきます。
寺田: 特に効果が高い資格などはありますか?
永江: それは、今どの会社にいるか、あるいは、どの会社に就職あるいは転職したいかによります。多くの会社には技術戦略があり、力を入れている分野への投資を積極的に行います。その会社が注力し、事業を伸ばそうとしている分野の資格こそが、その会社において年収アップに繋がりやすい資格と言えます。
寺田:会社が求めている資格を取るということでしょうか?
永江:そうですね。
寺田:それはもう社内でアンテナを張っているしかないですか?
永江:社内であれば、多くの会社で事業戦略や今後の方向性が打ち出されていると思います。そのため、会社がどちらへ向かっていきたいのかという情報は、全くないわけではなく、ある程度読み取れるはずです。その点は、非常に参考になる情報だと思います。
寺田: では最後です。
【質問5】「年収がアップしている人に共通していることはありますか?」
永江: 今日は資格の話が多かったので、もちろん資格を取ることも 1 つの方法だとは思いますが、私の考えは、継続的に学び直しをしている、あるいは新しいスキルを獲得するために挑戦し続けている、という点です。どの資格が有利か、という状況は常に入れ替わっていくので、「これを一つ取れば安泰」ということは決してありません。
そして、その根底には、自分なりのキャリアプランをしっかりと考えられている、という共通点があるように思います。「こういう狙いがあるから、この方向に進んでこのスキルを獲得する」といった計画があるからこそ、ゴールに向かって行動しやすくなるのではないでしょうか。
それに関連して、自分の市場価値、つまり現在地を正しく把握できていることも重要です。今、自分がどういうスキルを持っていて、新たにこの強みを獲得していくことでより評価されるということを把握できるというのは、すごく大事かなと思います。
そしてもう一つ加えるなら、自分の実績を言語化して、他者にきちんと伝えられる「自己アピール力」も大切なスキルです。
寺田: そのアピールが難しいですよね。自慢のようになってもいけませんし。
永江: 伝え方は色々あります。例えば当社には、ブログをたくさん書くことで非常に多くの読者を持つ社員がいます。彼は、上司に直接アピールするのは得意ではないけれど、アウトプットとして残り続けるものを書くことは自分に向いている、と考えて実践しています。
その結果、社内外で広く認知され、それが彼の市場価値を高めることに繋がっています。社内からなのか社外からなのか、どっちがスタートなのか分からないところはありますが、このようにアピールの仕方は人それぞれです。自分に合った方法を見つけることが大切です。
寺田:まずはアピール方法を考えるということですね。
永江:口頭で説明する方が得意な人もいれば、文章の形で伝える方が得意な人もいるでしょう。人によって適した表現方法があるのだと思います。
そして、こういった「どの資格がいいですか」「どうすれば年収が上がりますか」といったご質問に対しては、おそらく皆さん、分かりやすい一つの答えを求めていらっしゃるのだろうと感じます。
寺田:はい、まさにそれを求めてしまっていました。
永江:しかし、現実はそう単純ではないのです。丁寧にお答えするとすれば、「決まった一つの正解はない」ということになりますね。
寺田:そうですね。安易に楽な道を探そうとしてはいけませんね。大変失礼いたしました。
永江:いえいえ、答えを探求しようとする姿勢は、非常に素晴らしいことだと思います。ただ、そこでは「自分は何者で、今どんな立場にいるのか」という自己分析が欠かせません。さらに、ご自身の思考の特性、例えば物事への向き不向きや、好き嫌い、興味の有無といった点も大きく影響してきますので。
4. 年収が上がりやすい会社の選び方
寺田: 最後に、採用責任者の小山さんにお聞きします。どの会社に所属するかは、年収を考える上で非常に重要な要素だと思いますが、どのような会社を、どういう視点で選べばいいのでしょうか?
小山: あまり話題にはなりませんが、重要な観点として、「その会社がどのような事業で収益を上げているか」を見ることをお勧めします。
例えば、インフラの中でも運用・監視・保守といった業務と、クラウドやネットワークの自動化といった領域とでは、ビジネスモデルも収益性も異なります。
会社の「利益率」も重要です。有価証券報告書などを見れば、その会社の利益率が分かります。業界を問わず、利益率が高い会社の方が年収も高くなる傾向があります。
寺田:有価証券報告書を見る、ですか。
小山:そうですね。上場企業であればIR情報が必ず公開されていて、平均年齢や在籍年数なども確認できます。中長期的に見れば、体力があり、きちんと収益を上げている会社の方が、存続の可能性も高いですし、社員への還元や新しい事業への投資もできます。年収の原資は利益ですから。これはエンジニアに限らず、会社選びの際に非常に重要な視点だと思います。
寺田: 会社選びで有価証券報告書を見る、という視点は初めて聞きました。成長産業かどうかを見極めた上で、さらに会社の体力を見る、ということですね。
5. クロージング
寺田: お2人のお話を聞いて、一筋縄ではいかないということも含めて、非常に参考になりました。
永江: 資格の話で言えば、なぜ企業が特定の資格を求めるのか、お客様やITベンダーとの関係性の中でどう需要が生まれるのか、といった背景もあります。そういったメカニズムもどこかでお話しできると面白いかもしれません。
寺田: ぜひお聞きしたいです。小山さんはいかがでしたか?
小山: 普段、面接などで今日のような話をすることはほとんどないので、転職を考えている方には特に参考になったかもしれません。改めて、会社選びは一つの側面だけではいけないと感じましたし、特に新卒の方々には、こういった視点でも会社を見るといいよ、と伝えていけるといいなと思いました。
寺田: 本当ですね。このポッドキャストをぜひ聞いていただきたいです。皆さん、参考にしていただけたらと思います。
この番組はSpotify、Apple Podcast、Amazon Musicで配信中です。
ポッドキャストへのフォローとレビューもぜひお願いいたします。
番組へのご質問やリクエストは、専用フォームか、各種SNSから受け付けております。気になることがありましたら、ぜひお寄せください。


