2025/11/05
インフラエンジニアのホントのところ #26|なぜ上がらない?スキルはあるのに年収が伸びない人の共通点
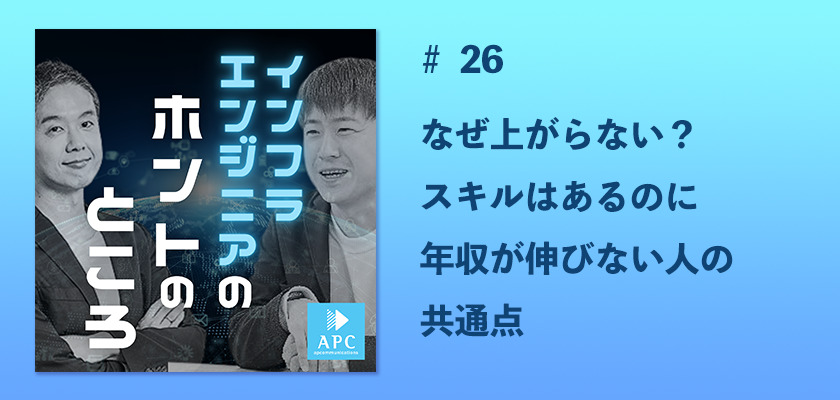
ITインフラって、「なんだか難しそう」「地味で大変そう」と思われがち。
でも実は、社会を支える根幹にある、とてもやりがいのある仕事なんです。
そんなリアルをお届けするPodcast 「インフラエンジニアのホントのところ」。
MCにはベンチャー女優の寺田有希さんを迎え、当社の副社長 永江耕治と採用責任者 小山清和が、現場・経営・採用の視点から語ります。
今回のテーマは「なぜ上がらない?スキルはあるのに年収が伸びない人の共通点」。
実力はあるのに年収が上がらない……その悩みは、社内での見せ方や行動次第で変えられます!
年収を伸ばしている人の共通点を解き明かしながら、必要な視点や行動などを、元エンジニアの現役経営者と採用責任者が徹底解剖します。。
<目次>
1.オープニング
2. なぜ年収は頭打ちになるのか?
3. 年収を伸ばす人の共通点は、「掛け算」のスキル
4. スキルの選び方と、評価に変える「伝え方」
5. 年収アップのための「環境選び」と「スタンス」
6. クロージング
1.オープニング
寺田:インフラエンジニアのホントのところ。言葉は有名でも、何かと知らないことが多いインフラエンジニアの世界。この番組は、キャリアや将来性、魅力など、ついつい隠れがちな「ホントのところ」、インフラエンジニアキャリアの真実を、業界のプロであるエーピーコミュニケーションズの永江さん、小山さんと共に徹底解剖していくポッドキャストです。今回も始まりました、「インフラエンジニアのホントのところ」。
永江:エーピーコミュニケーションズの永江です。インフラエンジニア業界に23年以上携わっており、現在はエーピーコミュニケーションズで取締役副社長をしています。どうぞよろしくお願いいたします。
小山:エーピーコミュニケーションズの小山です。私は10年以上のIT業界での採用経験と、7回にわたる転職でキャリアを形成してきた人事です。エーピーコミュニケーションズでは採用責任者をしています。よろしくお願いします。
寺田:そしてMCを務めます、ベンチャー女優の寺田有希です。
さてさて、今日お聞きしたいことなんですけど、お2人がモチベーションを上げるため、またはモチベーションを保つためにしていることは何かありますか?
永江:モチベーションを上げるためというか、原動力になっているところで言うと、今、娘が18歳なんですけれども、その成長を日々見守っていくということがモチベーションの源ですね。
寺田:もう先週から素敵すぎます。
小山:じゃあ、僕がちょっとオチを作らなきゃいけないですかね。
寺田:小山さん、ありますか?
小山:僕は自分がチャレンジすることとか、始めたことをあえてSNSに投稿したりするんですよ。自分で自分を煽る、というか。
例えば、直近で「これやります」と宣言したものだと、語学アプリ『Duolingo』を「始めました」というのを投稿しました。そうすることによって、知り合いから「今これどうなってます?」って聞かれるわけじゃないですか。そこで、聞かれた時に「やってない」って言うと、「なんだこの人、口だけなのか」って思われますよね。
そうならないようにするために、やり続けるんですよ。「あれどうなってるの?」って聞かれた時に、「やってますよ、これだけ続けてます」って言えるようにと、自分のモチベーションを保つ。「モチベーションの炎を絶対に絶やしてはいけない」という感じでやっています。
寺田:これ、大事って言いますよね、宣言するって。
小山:そうなんです。実際、今290日ぐらい続いてます。
寺田:もうすぐ1年行けそうですね。
小山:はい、1日も途切れてないです。
寺田:本日のテーマである「自身のスキルの上げ方」といった話にもつながってまいります。
2. なぜ年収は頭打ちになるのか?
寺田:本日のテーマは、「なぜ上がらない?スキルはあるのに年収が伸びない人の共通点」です。経験もスキルもあるのに、なぜか年収が伸びない。そんな時はどう考え、どう対処していけばいいのでしょうか。一歩先へ進むための方法を徹底解説していきます。
現在、経営者としても活躍されている永江さんと共に、「なぜスキルがあるのに年収が上がらないのか」について、解剖していこうと思います。
スキルがあるのに年収が上がらない人って、実際、結構多いですか?
永江:割合として多いかどうかは、どの観点から見るかによるので一概に言いづらいんですが、それなりにいると思っています。
ただ、若いうちはスキルが上がっていけば、年収も上がりやすいんだと思うんですよね。でも、それ以上の役割を求められるような年次や年齢になっていった場合に、上がり続けるかどうかで言うと、そこは「上がりが止まる」という人も、それなりにいるかなと思います。
寺田:行き詰まるタイミングが出てきてしまう人が、一定数いらっしゃるんですね。
永江:個人で、何かその「天井」みたいなところに当たってしまうという人はいると思います。
寺田:なぜ天井に当たってしまうのでしょうか?
永江:そこは「スキルがある」とはどういうことか、という話でもあるかなと思うんです。多分、技術スキルという話ですよね。例えば、技術にも「旬」な技術というものは、やはりあるわけなんですよね。
給料のお金の出所がどこなのか、というところが根本的にあると思っていて、まずはお客様がいて、技術に対する対価として支払われるわけです。
「スキルがある」と言っても、それが今や多くの人が身につけている技術なのか、それとも、新しいトレンドの技術で、その技術を持つエンジニアは少ないという場合なのか。後者だと報酬は高くなっていくんですよね。
変化にどんどんついていって、新しいスキルを身につけ続けている人であれば、年収は上がっていく傾向にあると思います。ですが、例えば「この分野ではスキルがあります」となっても、旬が過ぎていたりすると、年収Upに結びつかないことがあるんですよね。
寺田:時代を読んで、スキルも上げ続ける、違う分野にも挑戦し続けることが大事なんですかね。
永江:そうですね。なので、「技術力が高いから年収が高い」というのは、完全にイコールというわけではないんですよね。
そこにはやはり「支払う人(お客様)」がいるということを忘れちゃいけなくて、求められている分野のスキルレベルが高いと報酬が高くなる、という話なんです。
寺田:ここを履き違えてはダメですね。他に、年収が上がらない原因として、どんな要素がありますか?
永江:あとはおそらく、年収が上がらなくなって悩むのは、若いうちよりは、ある程度の年齢になってからの方が増えてくるんだと思うんです。
その場合は、「期待される貢献が何なのか」という視点が重要になります。それは、「技術で引っ張ってもらいたい」ということかもしれないですし、「チームに対してもっと貢献してもらいたい、マネジメントをしてもらいたい」ということかもしれない。
年収が上がれば上がるほど、期待される役割が重くなったり、要素が増えたりするので、そこに対して、自分がどう応えられているかが大事だと思います。
寺田:なるほど。ご自身で考えていく必要があるんですね。
永江:そうですね。年収を上げる前段階として、市場価値を上げるという話があると思うんですが、一つの技術分野という狭い範囲でスキルを高めていけば年収が上がり続けるかというと、多くはそうではなかったりします。
あるいは、業界の中で特別目立つ「有識者」になるという、すごく狭くて厳しい道を行くか。
そこに到達しているのに年収が上がっていないのか。そこそこのレベルなのであれば、技術スキル以外にもマネジメントや他のスキルと組み合わせていくことが必要になっていくと思います。
必ずしもマネジメントをしなければいけない、というわけではないんです。企業から見て付加価値が高い、年収が高い人ってどういうことなのかを調べていくと、他にもいくつかの分野があると思います。そういった面も含めて、求められるレベルに届いていない、ということがあるんだと思います。
寺田:それを探っていくのが大事ですね。
永江:そうですね。
寺田:スキルがあるのに評価されない人の共通点はありますか?
永江:まずはメタ認知がうまくできていないことが多いと思います。
市場としてどういう評価がされるのか。お客様から報酬をもらえることをやっているのか。所属している企業の中でどれぐらい貢献していると思われているのか。こういうところが、うまく認知できていない可能性はあるかもしれません。
あるいは、実際には貢献しているんだけれども、しっかり評価者に伝わっていないという可能性もあるかもしれないですね。
寺田:「こういうことをしてますよ」と、例えばチームメンバーや上司の方に伝えていないと?
永江:「やっているから、きっと誰かが黙っていても見てくれているだろう」と思ってしまう。でも、そこは周りも気づきづらいことがあるんだと思うんですよね。それを伝えていく、ということも大事だと思います。
寺田:伝えるって、大事なんですね。
3. 年収を伸ばす人の共通点は、「掛け算」のスキル
寺田:ここからは、実際に年収アップをしていくためにどういうことができるかについて、採用責任者もされている小山さんと一緒に考えていきたいなと思います。
実際に年収を伸ばしている人の共通点ってありますか?
小山:ありますね。全員ではないですが共通点はありまして、「一点突破」じゃない人ですね。
寺田:と言いますと?
小山:自分の専門性だけじゃない部分も、価値を高めたりするような「サブスキル」を持っている方が、年収を伸ばしていっていると思います。
寺田:武器として、超強力な武器を3つも4つも持て、ということではなく、能力としてそこまで高くなくてもいいから、数を持つべきということですか?
小山:そうですね。エンジニアであれば、技術力以外のところを磨いていく。例えば、スクラムマスターの資格を持っている方とかもいますよね。あとはプロジェクトマネジメント系の資格を取る人や、育成に悩んでコーチングの資格を持っているエンジニアの方もいます。
やはり「掛け算」で、自分の価値を高めていっています。これ、足し算じゃないんですよね。掛けるものが多ければ多いほど価値が上がっていって、専門性以外の部分でも評価してもらえる、ということです。
4. スキルの選び方と、評価に変える「伝え方」
寺田:そのスキルがどういうものがいいのか、すごく聞きたいんですけど、技術力以外で、掛け算の数字がより高くなりそうなスキルってありますか?
小山:例えば、「チームをどううまくやっていくか」というところで、コーチングの資格は、マネジメント界隈だと取り入れた方がいいと言われています。僕がコーチングのスクールに通った時も、マネジメント職の方は結構いらっしゃいました。
あとは、スクラムマスターですとか、変わった方だと社労士の資格を取った方もいましたね。
寺田:社労士ですか?
小山:その方は今もう経営者になっちゃってますけど、元エンジニアです。正しい知識を持って経営する、ということです。
今トレンドになっているところを攻めに行くのか、それとも独自の立ち位置を作っていくのか。ニッチなところ、他がなかなか真似しづらいところを攻めていくのか。
寺田:それは、どっちの選択をするかが重要だと思うんですけど、どうやって決めればいいんですかね?ニッチに行くか、流行りに行くか。
小山:個人的には、ニッチに行くより、まず一旦ポピュラーになっているものからやった方がいいと思います。ニッチは結構リスクもあるので。もちろん、ニッチな方でガツンと行く人もいますけど。
寺田:パンチ力は強そうですよね。
小山:そうですね。あるんですけど、流行り廃りもありますし、真似されちゃうこともある。採用トレンドも、時間が経つと当たり前になって消えていっちゃうんですよね。そうなった時に、そこだけで部分突破してきた人って、価値が下がったりする。
なので、まずは掛け算できるものをちゃんと増やしておいて、その中で「もしかしたら、ここ行けるかも」という形にした方が、リスクは少ないかなと思います。一時的に跳ねたとしても、平均でならすと実は下がっている、ということにもなりかねないので。
年々上がっていく可能性を高めていくためには、今のトレンドを押さえておくことが重要だと思います。
寺田:このスキルを身につけたり、何か資格を取ったりした後、それを実際に成果とか評価に変えていくのって、ちょっとステップが違いますよね。
この変えるために必要なこと、すべきことってありますか?
小山:スキルって、磨き続けなきゃいけないんですよ。有名な『7つの習慣』という本でも、最後の7つ目で「刃を研ぐ(自分を磨き続ける)」という話がありますけど、結局スキルって、身につけた後、実践していかないと錆びるんですよね。
あとは、スキルを持っていても、みんなが分かってくれるわけではないので、自分で「こういうことができますよ」「興味がありますよ」とアピールしていくこと。自分でちゃんと営業していくことが大事かなと。
寺田:それが結構難しいと思ってしまいます。この営業方法、自分の価値の伝え方って、具体的にどうしていけばいいんですか?
小山:上司との1on1とか、雑談とかでもいいんですよ。「いや、最近ちょっとこういうのやってて…」みたいに、今やっていることを伝える。
寺田:そうなんですね。「これ始めたんですけど」とかでもいいんですか?
小山:そうです。私のクライアントだった方も、それがきっかけで新設部署に異動できることになって、やりたいことができるようになった、と言っていました。「こういうことに興味があってやりたいんです」「大学院でこういうことを学んでいて」と言い続けたんですよね。
「こんなこと言うと自慢だと思われるんじゃないか」とか、そういう恐れってあると思うんですけど、ほとんどの場合、一方的にそう思ってるだけなんです。
誰かにそう言われたわけではないのに、勝手に気にしちゃって言わない、ということの方が多い。実はそれが意外と次の一歩につながることってあると思うんですよね。
上司が全部わかってくれている、なんてことはやっぱりないので。努力していることを、自慢にならないように伝え方には気をつけつつも、アピールすることは年収を上げていく、評価をされていくためには必要な要素だと思います。
寺田:他の回でもお話しいただいたかと思いますが、例えばブログを書く、といった伝え方もありですか?
小山:それも一つだと思います。それを見て「公式のブログ書いてよ」と言われたり、「エヴァンジェリスト的なことをやってみないか」という話になるかもしれないし、「執筆してください」「登壇してください」って話が来るかもしれない。
私も実際、自分で営業しに行ったり、アピールしたりして、その機会を得たことがありますが、意外とそれが自分の評価になるケースもありますからね。
寺田:じゃあ、アウトプットの仕方は上司に直接でもいいし、ブログでもいいし、できるやり方でアウトプットする、と。
小山:そうですね。ただ、伝え方を間違えると、会社の評判や自己評価を下げることにもなるので、伝え方は重要です。煽ったり、「これが全てだ」という話し方をするのは、また違う話なので、気をつけないといけないですね。
5. 年収アップのための「環境選び」と「スタンス」
寺田:年収を上げていく、評価してもらうためには、会社や環境選びが重要かなと思うんです。年収が伸びやすい会社かどうか、どう見極めていけばいいですか?
小山:分かりやすいところで言うと、その会社の賃金形態、モデル年収ですね。「何歳でどれくらいになるか」という記載です。実際になれるかどうかは本人の問題もありますが、そこを1つの指標にする方法もあります。
ただ、従業員が少ないとブレ幅が出たりするので、注意は必要です。例えば、従業員数が少ないホールディングス会社の平均年収がすごく高く出ていても、実際は20人ぐらいの平均だったりして、参考にならないこともあるので。
あとは、産業によって利益率が全然違うので、利益率が高い会社の方が給与の原資が多く、年収は上がりやすい。IT業界、特に自社サービスをやっている会社は、サービスが急に跳ねて賞与が大幅に出たりするので、上がりやすかったりします。逆に、原価があるものだと利益が下がるので、昇給はするけど昇給率がそんなに高くないケースがあります。
あとは、ベンチャーやスタートアップという考え方もあります。IPOをした時のストックオプションなどでガツンと上がるかもしれませんが、会社が倒産する可能性も大企業よりは高いので、そこはリスクですね。
こういう情報は多角的に見た方がいいです。ただ、年収が上がりやすい業界・会社に入ったからといって、自分がそうなるか、というのは別問題だという視点も大事ですね。
寺田:と言いますのは?
小山:結局、入ってからのパフォーマンス次第、というところがあります。伸びやすい会社に入っても、そこから上がらない、というケースもあります。入った時がピーク、みたいな。
寺田:伸ばせない。
小山:そうなんです。そういうケースも見てきました。理論上はそうでも、それが全部自分に当てはまるわけではなく、上がっている人はやはり自分を磨くアクションをしている。会社が年収を上げてくれる、というわけではないんですよね。
寺田:じゃあ、まずは年収を上げていくために、会社選び、その前の産業選びが大事、と。
小山:そうですね。あとは、仮に年収が上がっても、自分のやりたくないことをやれるか?というところもあるので、そこは注意ですね。年収は上がってるけどやりがいを感じない、このまま続けられるだろうか、という状態だと不健全ですし。
私も転職7回してますけど、回数を重ねるたびに、見る角度が増えていきました。失敗している場合は、少ない情報や、ある一面だけを見て決めていることが多いですね。
寺田:他に、年収を上げていくために大切なことってありますか?
小山:「何歳の時に、年収がどれぐらいになっていたいか」を逆算して考えておくことは、結構大事かもしれないです。
「この年齢でこれぐらい」というのがあれば、「じゃあ、あと5年しかない時に、どういうアクションをすれば、5年後に年収1000万にたどり着けるんだろうか」というマイルストーンが見えてくるので。
それで会社を選んだり、行動を考えたりする。選ぶ業界を間違えると、そもそも希望する年齢で希望する年収まで行かない、ということも普通にあるわけですから。
終身雇用の時代は、会社が主役であり、会社が成長することが前提でした。そのため、会社は様々な制度を作り、給与体系も長く勤めた方が報われるような報酬体系にしていました。また、従業員に「会社にいたい」と思ってもらうために福利厚生を充実させていました。
しかし、そこから時代は変わり、会社が成長し続けるという前提が崩れた「人的資本経営」の世の中になっています。そのため、少し語弊があるかもしれませんが、会社をうまく利用して自分を成長させる、という姿勢も大事だと思います。
逆に言えば、会社側も、従業員が「残りたい」というメリットを感じてもらうために、様々な機会を提供していく必要があります。人を単なる「資源(リソース)」ではなく「資本(キャピタル)」として捉え、どう投資すれば「この会社にいたい」と思ってもらえるかを考えるようになっています。
当社でも永江さんがその辺りを旗振り役として進めていますが、私自身、従業員がうまく会社を活用して成長していく、という姿勢が大事だと考えています。というのも、会社がいつどうなるかは、どこの会社であっても分からないからです。「え、あの会社が?」と驚くようなニュースもあったかと思います。
現代はそのような不確実な時代ですので、会社に依存するのではなく、会社をうまく活用しながら、自分を高めていくスタンスが非常に大事なのではないかと思いますね。
寺田:確かに。環境選びも大事だけど、そういう会社に頼りすぎない自分作り、考え方作りも大事ですね。
小山:そうですね。どの職種にも限らず、そういう人がやっぱり活躍して、しっかりと年収も上げていっているなと、共通して感じます。
6. クロージング
寺田:やっぱり年収を上げていくって大変ですね。いろんなことを考えていかなきゃいけない。
小山:そうですね。そんな簡単には上がらないです。
寺田:難しいですか?転職し続けても、年収を上げるのは。
小山:下がったことありますからね、転職して結構大きく下がってしまって、本当に生活が苦しい時もありました。
寺田:ええ!
小山:結構大変でしたね。心が荒んでいく感じがしました。
でも、そこで気づいたのが、「自分はできる、価値がある」と思っていたものが、実は市場ではそうでもなかった、ということだったんです。そこで、自分を磨いて市場価値を上げていかなければいけない、他責じゃダメだ、という気づきになったのも、その時でした。
まあ、今思えばいい体験だったと思いますけど、もう1回やれと言われたら絶対無理です(笑)。
寺田:永江さんも、経営者として、そういうことは考えられますか?
永江:そうですね。私の場合は多くの人を見てきた経験からですが、やはり「メタ認知」は重要だと思います。客観的に自分が市場の中で、組織の中でどう見えているのか、どういう価値と捉えられているのかを、ちゃんと把握できるかどうかは、ものすごく大事なことかなと思います。
寺田:まさに小山さんがおっしゃっていたことと共通してますよね。自分の価値を見誤っていた、という話と。その考え方も参考になるものがたくさんあったと思うので、ぜひぜひ皆さんも参考に動いてみてください。
この番組はSpotify、Apple Podcast、Amazon Musicで配信中です。
ポッドキャストへのフォローとレビューもぜひお願いいたします。
番組へのご質問やリクエストは、専用フォームか、各種SNSから受け付けております。気になることがありましたら、ぜひお寄せください。


