2025/09/10
インフラエンジニアのホントのところ #18|インフラエンジニアは子育てと両立できるのか!?
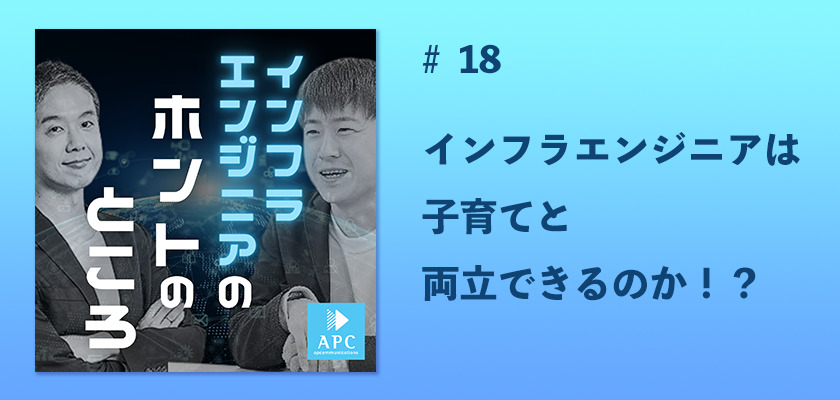
ITインフラって、「なんだか難しそう」「地味で大変そう」と思われがち。
でも実は、社会を支える根幹にある、とてもやりがいのある仕事なんです。
そんなリアルをお届けするPodcast 「インフラエンジニアのホントのところ」。
MCにはベンチャー女優の寺田有希さんを迎え、当社の副社長 永江耕治と採用責任者 小山清和が、現場・経営・採用の視点から語ります。
今回のテーマは「インフラエンジニアは子育てと両立できるのか!?」。
「子育てに向いてない」は、もう古い!?
夜間や緊急対応など、両立が難しいイメージがありますが、現場のリアルは変化しています。
子育てとキャリアを両立するために必要な考え方やスキル、そして就職先の選び方まで!元エンジニアの経営者と採用責任者の2人が、徹底解剖します。
<目次>
1.オープニング
2.インフラエンジニアは子育てを両立できるのか
3.両立のリアル。夜間・障害対応の現状は?子育てのしやすさは?
4.エーピーコミュニケーションズの現状と、子育て支援に積極的な会社の見極め方は?
5.クロージング
1.オープニング
寺田:言葉は有名でも、何かと知らないことが多いインフラエンジニアの世界。キャリアや将来性、魅力など、ついつい隠れがちな「本当のところ」を、業界のプロであるエーピーコミュニケーションズの永江さん、小山さんと共にインフラエンジニアのキャリアを徹底解剖していきます。
永江: エーピーコミュニケーションズの永江です。インフラエンジニア業界には23年いて、現在はエーピーコミュニケーションズで取締役副社長をしております。どうぞよろしくお願いいたします。
小山: エーピーコミュニケーションズの小山です。私は10年以上のIT業界での採用経験と7回の転職を通じてキャリアを形成してきた人事です。当社では採用責任者をしています。よろしくお願いします。
寺田: そして、MCを務めます、ベンチャー女優の寺田有希です。
最近、「10代がなりたい職業トップ10」というのを調べていたのですが、なんと日本、アメリカ、イギリスの全てで「エンジニア」がランクインしていたんです。お2人はこの現状をどうご覧になりますか?
永江: ずっと昔からそうだったわけではありませんよね。何年ぐらい前からでしょうか。
小山: この10年くらいではないでしょうか。それまでは、エンジニアの「エ」の字も入っていなかったと思います。
永江:そうでしたよね。
寺田: 若い世代からも注目度が上がっているというのは、お2人にとっても喜ばしいことですよね。
永江: そうですね。日本では労働人口が減り、エンジニアも足りなくなると言われていますから、その中で興味を持つ人が増えるというのは、ポジティブなことだと思います。
寺田:小山さんはどうですか?
小山: 採用する側としては嬉しいですね。また、「夢がある仕事」だと思ってもらえている側面もあると感じます。例えば、お金を稼げる、手に職がつけられる、何かを創りたい、社会貢献したい、といった様々な想いが、この結果に繋がっているのではないでしょうか。
過去の多くのエンジニアの方々が頑張って築き上げてきたものが、子供たちの目に魅力的に映るようになったのだとすれば、それは非常に良いことだと思います。
2. インフラエンジニアは子育てを両立できるのか
寺田: 若い世代からも注目が上がっているインフラエンジニアですが、今日はそんなお話にも少し通じるテーマをご用意しました。本日のテーマは「インフラエンジニアは子育てを両立できるのか」です。夜間対応や急な呼び出しなど、両立が難しそうなイメージがありますが、実際のところはどうなのでしょうか。現場のリアルを徹底解剖していきます。
それではまず、採用責任者の小山さんにお聞きしたいのですが、「インフラエンジニアは子育てとの両立が難しい」という意見をよく目にします。現状はいかがでしょうか?
小山: 確かに、そう言われ続けてきた時代が過去にありました。当時は、女性にとっては、両立は無理と言っても過言ではないほど難しい仕事だったと思います。
しかし現状では、当社にも子育てをしながら働く女性エンジニアはたくさんいますし、男性でも育休を取得したり、子育てと両立したりしている社員はかなり増えました。以前に比べれば、両立しやすい環境になっていると思います。
過去はインフラエンジニアの仕事内容的に難しい場面はありましたが、クラウド化などが進んだことにより、働き方が大きく変わってきました。このあたりが大きく影響していると思います。
寺田: では、現状では両立されている方が実際に多くいらっしゃるのですね。
小山: はい、いらっしゃいますね。
3. 両立のリアル。夜間・障害対応の現状は?子育てのしやすさは?
寺田: 次は、元エンジニアで現在経営者の永江さんと共に、現場のリアルを探っていきたいと思います。やはり「夜間対応」や「突発的な障害対応」がネックになるというイメージが強いのですが、実際の現場はどうなっているのでしょうか?
永江: 当社の場合になりますが、以前は24時間365日対応の夜間対応案件も複数ありました。しかし、事業戦略上、そうした分野の案件にはあまり携わらなくなってきており、今では担当している社員は全体の1%程度です。そのため、突発的な障害対応も夜間対応も、ゼロではありませんが、昔に比べると本当に少なくなりました。
寺田: 業界全体でも、物理的に現場で対応しなければならない業務は減ってきているのでしょうか?
永江: 減ってきていると思います。クラウド化の影響も大きいですが、オンプレや物理的なネットワーク機器がなくなったわけではありません。企業や組織によってはオンプレを選択するところも一定数あります。ですので、そういったお仕事に携わる場合は、変わらず対応が必要になると思います。
寺田: なるほど。その違いを、働く側もしっかりと理解しておくことが大事ですね。
永江: 所属する会社や転職先の会社が、どういった案件をどのくらいの割合で扱っているかによって、働く環境は大きく変わってくるでしょうね。
寺田: では、インフラエンジニアとして子育てをしやすいキャリアというのはあるのでしょうか?
永江: これも当社の話になりますが、やはりリモートワークができると子育てはしやすいですよね。
当社の場合ですと、全体の約8割がほぼリモートワークで、残りの1割が部分的にリモートワーク、もう1割はほぼ毎日出社をしています。そういった意味では、多くの社員が子育てしやすい働き方を実現できていると言えます。
寺田: それを可能にしているのは、やはりクラウドですか?
永江: はい、クラウドを扱う案件の方がリモートワークはしやすいですね。
寺田: ということは、子育てと両立しやすいキャリアを築くためには、「クラウドのスキル」を身につけることが重要になるわけですね。
永江: そうですね。クラウドのスキルを身につけていた方が、両立しやすい環境を得やすいと思います。
寺田: どうすればリモートワークを叶えられるかという点については、以前の回でお話ししていますので、そちらもぜひ聞いていただきたいですね。スキルを身につけたからといって、一筋縄ではいきませんから。
永江: はい、そうですね。
寺田: ありがとうございます。永江さんは常々、最新情報を追い続ける「キャッチアップ」の重要性をお話しされていますが、子育て中もそれは怠れないですよね。
永江: はい、技術の移り変わりが激しい分野ですので、継続的なキャッチアップは必要だと思います。
寺田: どのように時間を作ればいいのでしょうか?
永江: これは個人のキャリアの考え方にもよります。長期的な視点で考えるなら、一定期間は子育てに完全に集中するという選択も、人生においては「あり」だと思います。
一方で、子育てをしながら学びたいという場合も、昔に比べて学習環境は格段に良くなっています。インターネット上の情報や、ポッドキャストのような音声メディアを活用すれば、何かをしながら新しい情報を得ることも可能です。
寺田: なるほど。そういったツールを駆使するか、あるいは割り切るか、ですね。
永江: そこはそれぞれの人生のあり方次第だと思います。
4. エーピーコミュニケーションズの現状と、子育て支援に積極的な会社の見極め方は?
寺田: 最後に、会社の見極め方という観点でお話をお聞きします。エーピーコミュニケーションズは、ジェンダーダイバーシティの推進で「シルバー企業」に認定されたそうですね。おめでとうございます!
永江: ありがとうございます。
寺田: ダイバーシティという考え方は、子育てや育休と深く関わる分野だと思いますが、エーピーコミュニケーションズにはどのような子育て支援制度があるのでしょうか?
永江: 今回認定をいただいた大きな理由として、リモートワーク制度や働く環境が整っている点が評価されたと聞いています。
また、育児や出産などに合わせた柔軟な働き方を支える制度も整備しており、特に育休制度は手厚く用意しています。その結果、男性社員の育休取得率は現在約8割にのぼり、これは全国平均と比べてもかなり高い割合だと思います。
寺田: 8割はすごいですね!
永江: ただ、休息に制度を整えてきたため、課題もあります。育休を取る人が増える一方で、お客様へのサービス品質は維持しなければなりません。これは、現場で支えてくれる周りのメンバーや、管理職をはじめとする社員みんなの協力なくしては成り立たないと感じています。
ですから、制度を利用する側も、支えてくれる人たちへの感謝や理解を持つことが、非常に大切になってくると感じています。
寺田: その関係性なくしては語れないですね。
採用責任者の小山さんにもお聞きしたいのですが、制度があっても、実際に使えるかどうかは別問題だと思います。その点、エーピーコミュニケーションズでは皆さん活用されているのでしょうか?
小山: そうですね。私のチームでも、この数年で男女1名ずつが産休・育休を取得しました。私自身も子育て経験があるので、子供が小さい時期に関われる時間は限られていると実感しており、個人としてもどんどん取得してほしいと思っています。他の部署を見ても、制度を利用しているメンバーは珍しくなく、ごく普通に活用されていると感じます。
寺田: 制度が形骸化している会社に入ってしまうと大変だと思いますが、子育て支援に積極的な会社は、どうやって見極めればいいのでしょうか?
小山: 制度があることと使えることは、また別問題になってくるケースがあります。では、どこを見て判断するのかというと、これは私の経験則ですが、経営者や上司になる人が、子育てや育休を経験しているかどうかは一つの大きなポイントです。
経験がないことが悪いわけではありませんが、やはり人間は体験して初めて相手の気持ちに寄り添える部分があります。制度を運用する側にその体験がないと、なぜ休むのか理解されず、制度が使いづらい状況が生まれがちです。
私はちょうど世代の狭間で人事の仕事もしており、子供がいなかった頃は、「なぜ男性が育休を取るのだろう」と正直、疑問に思ったこともありました。今思えば未熟な考え方でしたが、いざ自分がその立場を体験してみると、彼らの気持ちがよく分かりました。「ああ、これはこうなるよな」と、腑に落ちたのです。
寺田:やはりご自身で経験されると、全く違いますか?
小山:ええ、全く。180度見方が変わりましたね。そういった経験は他にもたくさんあります。ですから、単に「制度がある」からと安心するのではなく、「その制度が実際に活用されているか」まで、きちんと見極めることが重要だと思います。
寺田: 制度が実際に使われているかどうかは、どうやって確認すればいいのですか?
小山: 例えば、当社では男性の育休取得率などをウェブサイトに掲載しています。必ずしも公開義務のない情報も、かなりオープンにしています。
そういった情報を積極的に出しているかどうかは、誠実さの一つの指標になると思います。
実際に質問した時に口ごもるような会社もありますし、ひどいケースでは「制度はあるけど使った人はいない。君が第一号だね」と言われた、という話も聞いたことがあります。
寺田: ええ!最近の話ですか?
小山: はい。ですから、制度の有無だけでなく、企業がどのような情報を、どこまで公開しているかを確認しにいく姿勢が大事だと思います。
寺田: 永江さん、経営者として、できていない部分まで公開されているのはすごいですね。
永江: はい。例えば、当社の女性管理職比率は今年5.7%と、まだまだ低いという自覚があります。しかし、そうした課題も含めて全てを公開し、透明性を確保するところから始めようと考えています。
寺田: 課題とも向き合われている、ということですね。
5. クロージング
寺田: 子育てとダイバーシティは、非常に重要かつセンシティブなテーマですが、大変参考になりました。
永江: 当社だけでなく、世の中全体がもっとこういった点を重視するようになってくれるといいなと思います。
小山: 本当にそうですね。求職者も企業もフラットに向き合い、正しい情報に基づいてお互いが判断できるような社会になるのが理想ですね。
寺田: はい。ぜひ皆さんも、今回の考え方を参考にしてみてはいかがでしょうか。
この番組はSpotify、Apple Podcast、Amazon Musicで配信中です。
ポッドキャストへのフォローとレビューもぜひお願いいたします。
番組へのご質問やリクエストは、専用フォームか、各種SNSから受け付けております。気になることがありましたら、ぜひお寄せください。


