2025/10/08
インフラエンジニアのホントのところ #22|会社員インフラエンジニアが「自分の価値を高める」方法とは?
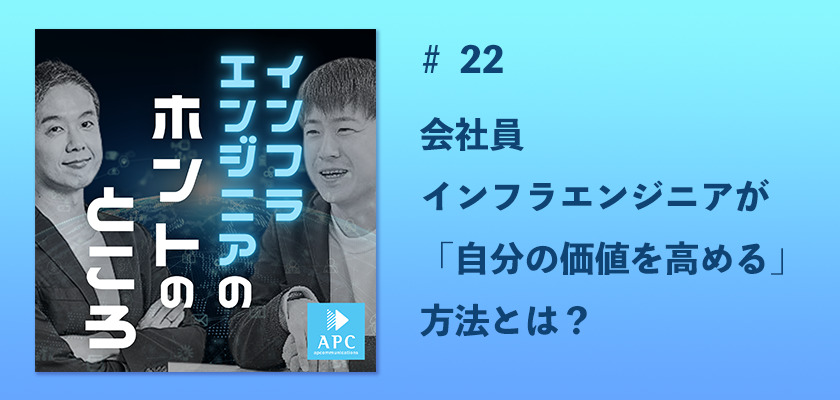
ITインフラって、「なんだか難しそう」「地味で大変そう」と思われがち。
でも実は、社会を支える根幹にある、とてもやりがいのある仕事なんです。
そんなリアルをお届けするPodcast 「インフラエンジニアのホントのところ」。
MCにはベンチャー女優の寺田有希さんを迎え、当社の副社長 永江耕治と採用責任者 小山清和が、現場・経営・採用の視点から語ります。
今回のテーマは「会社員インフラエンジニアが「自分の価値を高める」方法とは?」。
評価されない、成長できないーー変化の激しいインフラ業界で、埋もれず、必要とされ続ける人材になるには?
転職に頼らずキャリアを築くための考え方やスキルの磨き方などを、元エンジニアで現役経営者の永江と採用責任者の小山が徹底解剖していきます。
<目次>
1.オープニング
2.「なりたい自分」から逆算する、市場価値の高め方
3.価値ある人の共通点は「見返りを求めないギブ」
4.現代のインフラエンジニアに求められる価値とは
5.社内での評価を高める方法とは?
6.業務外スキルと資格の有効性
7.クロージング
1.オープニング
寺田:言葉は有名でも、何かと知らないことが多いインフラエンジニアの世界。キャリアや将来性、魅力など、ついつい隠れがちな「本当のところ」を、業界のプロと共にインフラエンジニアのキャリアを徹底解剖していきます。
永江:エーピーコミュニケーションズの永江です。インフラエンジニア業界には23年以上携わっており、現在はエーピーコミュニケーションズで取締役副社長をしています。どうぞよろしくお願いいたします。
小山:エーピーコミュニケーションズの小山です。私は10年以上のIT業界での採用経験と、7回にわたる転職でキャリアを形成してきました。エーピーコミュニケーションズでは採用責任者をしています。よろしくお願いします。
寺田:そしてMCを務めます、ベンチャー女優の寺田有希です。
この番組は、元エンジニアで現役経営者の永江さんと、採用責任者の小山さんという、現場を知り尽くしたエーピーコミュニケーションズのお2人と共に、インフラエンジニアのキャリアを徹底解剖していくポッドキャストです。
2. 「なりたい自分」から逆算する、市場価値の高め方
寺田:本日のテーマは、「会社員インフラエンジニアが自分の価値を高めていく方法」です。クラウド化や自動化など変化の激しいインフラ業界で、会社員インフラエンジニアとして自分の価値を高めていくにはどうすればいいのでしょうか?
年収をアップさせていく方法に関しては第17回で配信をしていますので、そちらも参考にしていただきながら、今回は「仕事に困らない人になるために」という視点で、スキル、経験、働き方など、リアルな戦略を徹底解剖していきたいと思います。
さて、小山さん、市場価値を高めていくためにすべきこととは、ずばり何でしょう?
小山:市場価値についてはこれまでの配信でも触れていますが、資格の難易度と需要、すなわち市場価値は必ずしも比例しません。重要なのは「何をもって市場価値とするか」を明確にすることです。名声なのか、収入なのか。まずは自分が市場価値を高めた先にどんな状態を目指すのか、ゴールを定めることが重要です。
たとえば「年収1000万円を目指す」と決めたら、理想の自分と現状のギャップを整理し、「何ができるようになれば理想に近づけるか」を具体化する。資格を取ること自体が目的になったり、世の中の流行を追いかけるのではなく、「自分はどうなりたいか、どうありたいか」をはっきりさせることが第一歩です。
私は副業でキャリアコーチングもやっているのですが、そこでは「Will(やりたいこと)」「Can(できること)」「Must(求められること)」を整理してもらいます。漠然と考えるよりも、「自分はどういう状態になりたいのか」をはっきりさせることが、市場価値を高める第一歩だと思います。
転職も同じで、年収1000万円を目指しているなら、その給与水準に達しない会社にずっといても実現できませんよね。「1000万円もらえる会社はどんな会社か、そこに入るためには自分の価値をどう上げればいいか」という風に考えていく、ということだと思います。
3.価値ある人の共通点は「見返りを求めないギブ」
寺田:「自社にいて成長できる人とできない人の違い」も伺おうと思っていたのですが、まさにそこが違いですか?目的の解像度が高いかどうか、ということなんでしょうか。
小山:それに加えて、これは私の周りで市場価値を上げていっている人の特徴なんですが、「Give」の数が多い人ですね。
寺田:おお、「Give」の数ですか!
小山:はい。ただし、よこしまな気持ちだったり、見返りを求めたりするGiveではないんです。
寺田:見返りをもらうつもりもなく、純粋にGiveしている数、ということですよね。
小山:そうです。それが後々、伏線が回収されるように、良い結果につながっている人が結構いるんですよ。私自身の人生でも、見返りを求めてやったGiveよりも、何気なく「これは自分が知っていることだから手伝おう」と思ったことの方が、後で何倍にもなって返ってきたという経験があります。
自社内にいても、違う部署の人と交流した時に少し助けるとか。もっと小さいことで言えば、掃除やゴミ捨てを手伝うとか、そういうのもGiveだと思うんです。意外とそういう細かいところって、周りの人は見ていたりしますよ。
寺田:そんな小さなGiveでいいんですね。
小山:それによって、どんどん信頼が上がっていくんです。すると、何かあった時に「あの時助けてくれたな」と思い出してもらえる。「あ、そうだ、あの人にお願いしようかな」「この前助けてもらったし、ちょっと…」みたいなことが起こるんです。
だから、自分のキャリアや自分のことばかり考えて「Takeくれくれ」という人は、周りから人が遠ざかっていきますよね。
寺田:「この人に頼むと見返りを求められそう」と思うと、頼みづらくなってしまいますしね。
小山:そうですね。例えば人事のコミュニティに行って、いきなり「どうやったらエンジニア採用できますか?」と質問しかしない。これは完全なTakeですよね。
そうではなく、「私たちの会社ではこういう取り組みをしていて、こんな課題があるのですが…」というように、まず自分の情報や経験をGiveする。そうすると相手も「そうなんですね。うちではその時こうしていますよ」と返してくれる。GiveしたからTakeが返ってくる、という関係性がすごく大事だと思います。
私の周りにいる経営者や起業家の方々も、すごい経歴なのに本当にGiveの精神がすごいんです。本当に申し訳なくなるくらいGiveしてくださるんです。
寺田:それはついていきたくなりますね。
次に、転職せずにキャリアアップしている人もいると思いますが、そういう方々がされている工夫や共通点はありますか?
小山:社内で活躍されている方は、良いタイミングで自分で希望して異動するなど、チャンスを主体的に作りに行っていますよね。「会社がチャンスをくれない」という言葉は、そういう方からは出てきません。
寺田:ああ、そうなんですね。
小山:行きたい部署の人に、全然違う部署から営業のようにアプローチして、異動できるよう働きかける、といった具合に意図的に作りに行っています。資格を取ってアピールするとか。
寺田:社内にいるからといって、止まっているわけではないんですね。
小山:はい。じっとしているように見えて、その人の見えないところでは、ものすごい高速でエンジンが回っていて、色々なところに情報発信をしたり、自分を売り込んだりしているんですよね。
寺田:大事ですね、売り込むのは。
小山:そうですね。これが全てではないと思いますが、そういう動き方をされています。行きたい部署があれば、まずその部署に直接連絡して話を聞きに行く、といったことですね。大企業だと、部署が違うともはや他社のように関係性が遠いこともありますから。
4.現代のインフラエンジニアに求められる価値とは
寺田:では、市場価値を高めるための概要をつかめたところで、具体的にどういう力を身につけていくべきかを探っていきたいと思います。これはお2人にお聞きしたいのですが、今の時代、インフラエンジニアに求められている価値とはどういうものでしょう?
永江:まずインフラエンジニアとして、ベースとなるのはやはり技術力です。ITインフラに関する、求められる技術領域において、専門家として価値を提供できること。これが基本になります。
そして、技術は変わり続けますし、新しい領域も生まれてくるので、それに対して常にキャッチアップできる力も必要です。
もう一つ、これがとても大事なのですが、その技術を用いて、お客様に対して価値を提供すること。つまり、「技術力を顧客価値に転換できる力」です。課題を発見し、設定し、解決するところまでつなげられる人は、やはり高い価値を提供できる人材になると思います。
寺田:お客様の姿を想像する、というのは前回も永江さんがおっしゃっていましたね。やはり大事なんですね。小山さんはいかがですか?
小山:自分の専門領域以外の業界に興味を持つのも良いのではないでしょうか。例えば、かつてはリアルなビジネスでしか成り立たないと思われていたものが、ITの発展によって必ずしもそうではなくなっていますよね。
そういった変化の中に、エンジニアとして入り込める余地や、業界の構造を変えられる可能性があるかもしれません。
そういう視点を持っておくと、ふとした時に「そういえば、あの業界ではこうやっていますよ」という話ができるようになります。自分の業界以外のことを詳しく知っている人は意外と少ないので、これは結構な強みになります。
寺田:視野を広げておくのも大事ですね。
5.社内での評価を高める方法とは?
寺田:では永江さん、会社員インフラエンジニアとして価値を高めるという視点で、「自社で評価されていないな」と感じる場合はどうしたらいいのでしょうか?
永江:多くの会社には、「会社をこうしていきたい」というビジョンや、数年間の事業計画があると思います。
その前提でお話しすると、会社には「こうなりたい」という理想と、「まだできていない」という現実の間にギャップがあるはずです。経営陣や管理職は、そのギャップを埋めてくれることを社員に期待しています。ですから、会社の目標と現状のギャップを埋める働きができる人は、評価されやすくなると思います。
なので、まずは「それを自分は把握しているか?」というところからスタートすると良いのではないでしょうか。
寺田:会社が目指す目標と、現在のギャップを知りに行くんですね。
永江:そうです。「一生懸命頑張っているのに評価されない」ということはよくあると思いますが、大事なのは「何かを一生懸命やっている」ことではなく、「価値を提供できているか、それが相手に届いているか」です。
そして、その提供するものが需要のあるものかどうかも重要です。その視点を持つのはなかなか難しいかもしれませんが、情報は社内にあるはずなので、聞きに行くことから始めてもいいと思います。
6.業務外スキルと資格の有効性
寺田:スキル自体も身につけなければいけないと思いますが、それが社内の業務で身につけられるものばかりではないですよね。今の業務で使っていない技術やスキルは、どう探し、どう身につければいいのでしょう?
永江:これはIT業界の良いところだと思うのですが、年々、様々な手段でスキルや知識を獲得できるようになっています。しかも、昔に比べてコストもかからなくなってきています。
インターネット上には、動画などたくさんの情報があります。もちろん書籍もそうですし、IT業界の特徴として、至る所で勉強会が開催されているんですよね。そのほとんどが無料で参加できるものなので、積極的に参加するのも一つの手です。知識だけでなく、人と接して人から学ぶことで、より多くのものが得られますから。
寺田:自分で調べるだけでなく、人に会いに行くのも大事ですね。では最後に、市場価値を高める上で「資格」が頭に浮かびますが、資格の取得は価値に直結しますか?
永江:有効な手段の一つではありますが、決して万能ではありません。その人がどれくらいの経験年数かによっても、例えば若いエンジニアなのか、ベテランエンジニアなのかで、有効性が変わってきます。
まだ経験が浅い方にとっては、体系的に学んだことを証明する手段として、すごく有効だと思います。また、会社が「この資格は多くの人に取ってほしい」と推進しているものに協力・貢献するのも、評価ポイントだと思います。
ただ、それはあくまで部分的なものです。「誰が」「何を」という状況によって価値が変わり、資格はきっかけにはなりますが、それだけで評価され続けるわけではありません。
寺田:会社が求めている資格を取りに行くのは、良い選択でしょうか。
永江:そうですね、プラスにはなると思いますが、その資格を1個取ったからといって、永久に評価が続くわけではありません。常に新しい何かを学び続ける必要はありますね。
寺田:止まれないですね。技術のキャッチアップも、資格取得も。
永江:そうですね。きっかけにはなるけれど万能ではない。プラスになる度合いも、人や状況によって変わってくる、ということです。
7.クロージング
寺田:価値を高めていく方法は、なかなか難しいかもしれませんが、色々な視点を聞けました。永江さん、いかがでしたか?ご自身も色々考えてこられたと思いますが。
永江:そうですね。意外と気づいていない人が多いかもしれないと思うのは、「自分の会社の戦略や事業計画を研究する」ということです。そういう人はあまり多くないかもしれませんが、経営者としては、それはとても大事なことだと思います。
寺田:そこにヒントがたくさんあるんですね。
永江:はい。一番身近なところに落ちているヒントだと思います。
寺田:小山さんはいかがでしょう?価値の高め方。
小山:色々ありますが、まず自分自身の気持ちに向き合うことが大事なんじゃないかなと思います。
目標を立てるのが苦手だったり、間違った目標を立ててしまったりする人も多いのですが、それは「何をやるか(What)」から決めてしまうことが多いからだと思うんです。それよりも、「そもそも自分はなぜそれをやりたいのか、どういう風に仕事をしたいのか(Why)」という部分に、正直に向き合うことが大事なのではないでしょうか。
寺田:自分自身の解像度を上げることですね。その辺も参考にしていただけたらと思います。
この番組はSpotify、Apple Podcast、Amazon Musicで配信中です。
ポッドキャストへのフォローとレビューもぜひお願いいたします。
番組へのご質問やリクエストは、専用フォームか、各種SNSから受け付けております。気になることがありましたら、ぜひお寄せください。


