2025/10/20
【プロフェッショナル職】「やりたいから」を突き詰めた先がプロの道になる。技術への情熱が、キャリアを拓く
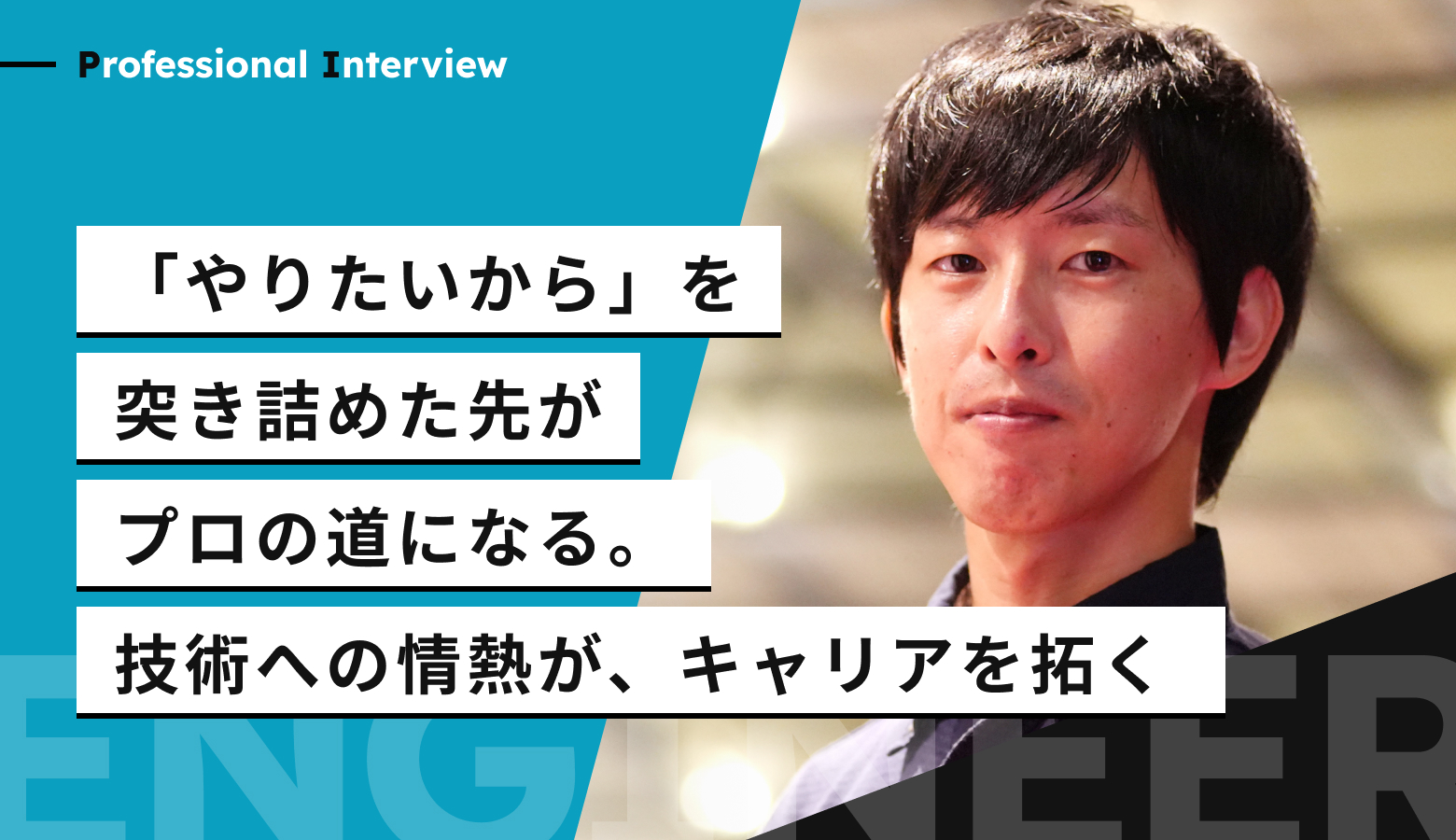
エーピーコミュニケーションズ(以下、APC)には、エンジニアがエンジニアであり続けるための「キャリアパス」が複数あります。
紹介するのは「プロフェッショナル職(以下、プロ職)」です。ミッションは、専門分野を掘り下げ、技術力を持って社内外のエンジニアから一目置かれる存在を目指すこと。そのために社内外の技術イベントや勉強会での登壇、書籍出版、OSSの開発やコントリビュートなど多岐にわたる活動を通じて、日々、自己研鑽をもとにアウトプットを続けています。
今回は、徳島からフルリモートで勤務し、社内外で精力的にアウトプット活動を行う埜下さんに話を聞きました。なぜプロ職を選んだのか。その原動力である技術への情熱や、アウトプットを通じて得られるもの、そして今後の展望について語ってもらいました。
APCのキャリアパス制度設立の背景や概要は以下でもご紹介しています。ぜひこちらもご覧ください。
APCだから叶う、エンジニアがエンジニアであり続けるキャリアパス
* * * *
埜下 太一(ののした たいち)
ACS事業部 Cloud Infrastructureチーム / シニアプロフェッショナル
東京のSIerでキャリアをスタートした後、徳島の企業でインフラエンジニアに転身。「もっと技術的に強くなりたい」という思いから、2023年APCへ入社。現在は徳島からフルリモートで勤務している。専門はMicrosoft Azureを中心としたクラウド技術で、顧客のSRE支援などに従事。 2024年・2025年にMicrosoft MVPを受賞。3児の父。
未経験からインフラの世界へ
—— 最初に、現在の業務内容について教えてください。
埜下:現在は、Microsoft Azure(以下、Azure)におけるクラウドネイティブ/プラットフォームエンジニアリングの導入支援事業をしているACS事業部に所属していて、シニアプロフェッショナルとして、主に二つの役割を担っています。 一つは、小売業界のお客様に対するプロジェクト支援です。SRE(Site Reliability Engineering)チームにAPCのメンバー4名ほどで参画し、お客様のシステムを進化させるための技術支援に深く携わっています。
もう一つは、業務やプライベートで得た技術的な知見を社外に発信する「アウトプット活動」です。会社や個人のブログで技術ノウハウを発信したり、技術コミュニティや各種イベントでの登壇といった形で積極的に行っています。
—— 埜下さんは、最初からインフラエンジニアを目指していたのですか?
埜下:いえ、最初のキャリアは中小のSIerで、システムの設計や要件定義を経験しました。
大きな転機が訪れたのはその後です。妻の出身地である徳島へ移住し、未経験ながらインフラエンジニアとしての道を歩み始めました。
きっかけは、前職の面接でかけられた「インフラ担当が不足している」という一言です。当初は「本当に自分にできるのか」という不安からのスタートだったのですが、実践と学習を重ねるうちに探究心に火がつきました。知れば知るほど、インフラ技術の奥深さと面白さに、夢中になったんです。
このままでは終われない。業界の最前線を知り、転職を決意
—— そこから、どのような経緯でAPCに転職したのですか。
埜下:前職では安定した環境で働かせていただいていましたが、技術者としてさらに高いレベルの挑戦をしたいという想いが強くなり、少しずつ物足りなさを感じるようになっていました。「このままでは、自分の成長は止まってしまう」という危機感にも似た感情だったと思います。
そんな中で芽生えたのは「もっと技術を磨きたい」「もっとスキルアップしたい」という気持ちでした。その想いを決定的にしたのが、ある技術イベントで目にした、業界の最前線で活躍するエンジニアたちの姿です。世の中には、すごいエンジニアが星の数ほどいる。その事実を突きつけられ、衝撃を受けたんですよね。
—— 最終的にAPCへの転職を決めた理由は何ですか?
埜下:技術イベントやコミュニティで、APCのエンジニアが登壇している姿をよく見かけていて、良い印象を持っていました。エンジニアがエンジニアらしく技術を追求することを応援している会社なんだと感じていました。しかも、当時自分が興味を持っていたAzureの技術と、APCが注力している分野が重なっていたことも大きかったです。
また、私は徳島在住でフルリモートが必須条件だったので、そこをクリアした点も後押しになりました。技術的な方向性、そして働き方。すべてのピースが合致したとき、「APCしかない」と確信し、入社を決めました。
目指したのではなく、辿り着いた。プロ職という自然な選択
—— 入社後、マネジメントではなく「プロフェッショナル職」を選んだのはなぜですか?
埜下:正直なところ、大きな迷いはありませんでした。なぜなら、APC入社以前から自分が取り組んできたことが、APCのプロ職の定義と同じだったからです。
—— どういうことでしょう?
埜下:お客様の課題を解決するエンジニアリングそのものに純粋な楽しみを感じ、この仕事をずっと続けていきたいと思っていましたし、以前から個人で技術ブログでの発信を続けていたんです。そんなとき、上司との1on1で「埜下さんは、プロ職だよね」という話になり、ごく自然な流れで決まりました。
ですから、実際にプロ職になった今も「プロ職だからアウトプットしなければいけない」という義務感は全くありません。自分が「面白い」「やりたい」と感じる活動を続けていたら、それが結果的にプロ職の在り方そのものだった、という感覚なんです。
「人とのつながり」がキャリアを広げる
—— プロフェッショナル職として働く上で、大切にしている考えや姿勢はありますか?
埜下:アウトプットによって新たな機会を生み出す、という姿勢です。
実は、私は人前で話すのが得意ではありません。それでも登壇などでのアウトプットに挑戦し続けるのは、一歩踏み出すことで得られるものの方が圧倒的に大きいと信じているからです。目標に向かって臆することなく突き進むという「勇往邁進」という言葉を大事にしているのですが、この言葉で自分を奮い立たせ、「当たって砕けろ」くらいの気概でチャレンジしています(笑)。
—— それだけ得られるものがある、と。
埜下:そうですね。一番は「人とのつながり」です。
アウトプットを始めた当初は、ブログに「悩みが解決しました」といった反応をもらえるのが純粋に嬉しかったんです。そこから登壇の機会が増えると、その反応がよりダイレクトに伝わってきました。同じ技術領域で話せる仲間が増えていくことが、本当に楽しくて!仲間と情報交換することで、自分一人では知り得なかった新しい技術や知識に触れることができ、自身の成長にもつながっています。
それから、顔見知りが増えることで、新しいコミュニティにも参加しやすくなり、さらに活動の輪が広がっていく。このポジティブな循環が、アウトプットを続ける大きなモチベーションになっています。
そして、これはコミュニティ活動だけでなく、日々の業務でも同じです。特にリモートワークでは、自分が今何に取り組んでいるのか、どんなことに困っているのかを意識的に発信しないと、誰にも伝わりません。自分の活動を発信することで、周囲からアドバイスをもらえたり、有益な情報が入ってきたりと、プラスになることばかりです。やったことをきちんと発信することが、次のチャンスに繋がるのだと、日々の業務を通じて改めて実感しています。
エンジニアとしての“原点”への挑戦
—— どんな方がAPCのプロ職に向いていると思いますか?
埜下:APCのプロ職は、自分の探究心に従って活動していることを、会社が評価してくれる。すでにアウトプットが習慣化されているエンジニアにとっては、すごくありがたい制度です。
だからこそ、プロ職を目指す方には、アウトプットそのものに楽しさや自分なりの意義を見出せる人であってほしいと思います。「やらなければいけない」という義務感で始めてしまうと、継続するのは困難でしょう。自分の中から湧き出る「動機」が、何よりも重要だと感じています。
—— 最後に、埜下さんの今後の目標について教えてください。
埜下:大きな目標が二つあります。一つは、書籍の執筆です。執筆経験のある知り合いが増えてきて、ブログや登壇とはまた違う、体系的なアウトプットの形に興味が湧いてきました。執筆は商業誌でなくてもできるため、積極的に挑戦してみたいです。
もう一つは、「Developers Summit(デベロッパーズサミット:デブサミ)」という技術イベントに登壇することです。このイベントは、私が前職時代に初めて参加して、「世の中にはこんなにすごい技術や人がいるんだ」と知るきっかけになった、いわば原点とも呼べる場所なんです。いつか自分が登壇者として、あの場所で話すことで、かつての自分と同じようなエンジニアの新たな転機となるきっかけを作れたら、これほど嬉しいことはありません。
* * * *
エーピーコミュニケーションズでは中途も新卒も積極的に採用中です。
お気軽にご連絡ください!
▼エンジニアによる技術情報発信
tech blog APC
Qiita






